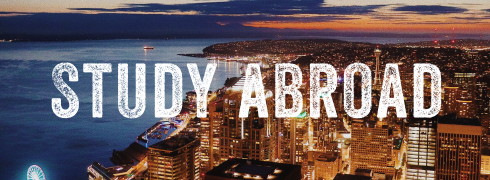グリフィス大学
自然豊かなオーストラリアでの、本格派留学。

大学概要

世界中から人々が集うゴールドコーストで、
本格的な学習体験を。
■スケジュール
・期間:1セメスター(約4ヶ月)
・時期:2月上旬~5月下旬(1年次修了後)
・対象:国際教養学部2年生
■基本情報
・名称:グリフィス大学(ゴールドコーストキャンパス)
・設立:1971年
・所在地:オーストラリアクイーンズランド州ゴールドコースト
・留学生数:約9,000人(約130ヶ国)
本格的な学習体験を。
■スケジュール
・期間:1セメスター(約4ヶ月)
・時期:2月上旬~5月下旬(1年次修了後)
・対象:国際教養学部2年生
■基本情報
・名称:グリフィス大学(ゴールドコーストキャンパス)
・設立:1971年
・所在地:オーストラリアクイーンズランド州ゴールドコースト
・留学生数:約9,000人(約130ヶ国)
カリキュラムの特徴

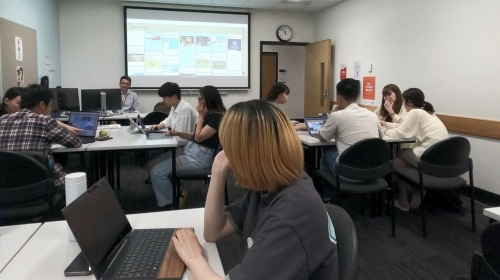
■Direct Entry Program (DEP):英語学習コース
学部授業聴講レベルの語学力習得を目指した本格的な英語学習コース。
プレゼンテーションやディベートの実践、エッセイの執筆など、英語での実践力が鍛えられるカリキュラムです。
◇特徴
-本コースの履修に必要な語学スコアの提出は不要です。
-現地到着後、英語のプレイスメントテストを受験し、6段階のクラスレベルに分かれます。
-授業は基本的に午前中の実施となります(8.15 am – 12.45pm)
学部授業聴講レベルの語学力習得を目指した本格的な英語学習コース。
プレゼンテーションやディベートの実践、エッセイの執筆など、英語での実践力が鍛えられるカリキュラムです。
◇特徴
-本コースの履修に必要な語学スコアの提出は不要です。
-現地到着後、英語のプレイスメントテストを受験し、6段階のクラスレベルに分かれます。
-授業は基本的に午前中の実施となります(8.15 am – 12.45pm)
参加資格(語学能力)
特になし
居住形態

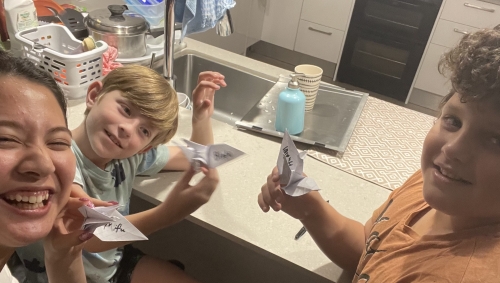
■ホームステイ
・キャンパスからバスで30~40分圏内のホスト家に滞在
■アパート
・キャンパスからバスで30~40分圏内のホスト家に滞在
■アパート
現地での様子