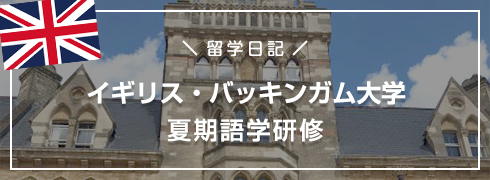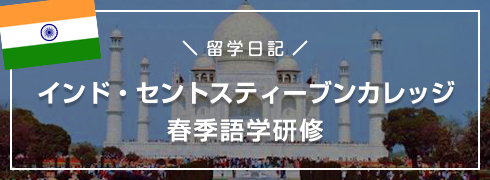- 文学部トップ
- 2022年度入学者以前カリキュラム
- 哲学・歴史学
哲学・歴史学
哲学と歴史学の両面から「人間とは何か」に迫る。

今、私たちはどんな時代を生きているのでしょうか。私たちが生きる「いま」を長い時間と広い空間の中で深く考え、そこから「未来」のあるべき姿を構想できるようになることが、大学の学問の醍醐味です。そこで必要となるのが、「人間とは何か」という問いを中心に学問を再編成することであり、混沌きわまる現代こそ、そのような探究が求められています。そのために、実証を重んじる歴史学と、理念を尊ぶ哲学は、きわめて大切な学問です。哲学・歴史学メジャーでは、西洋から東洋までの、そして古代から現代までの知の蓄積を継承しながら、新たな知を形成しゆく力を養います。
主な開講科目
イントロダクトリー
- 哲学・思想への招待
- 歴史学への招待
ベーシック
- 哲学概論
- 仏教思想概論
- 倫理学概論
- 考古学概論
- 歴史学概論
- 比較文化史概論
アドヴァンスト
- 東洋思想史
- 言語哲学
- 中央ユーラシア史
- 西洋文化史
- 東洋文化史
開講ゼミ一覧

《西洋哲学》 伊藤 貴雄 教授
ヨーロッパ哲学史上最大の巨人であり、現代哲学の基礎を作ったカントの著作などを学びながら、グローバル化する現代の思想的・社会的課題への示唆を読み取り、問題解決への方途を探ります。たとえば、自由とは、正義とは、世界市民とは、等々の問いを皆で議論しながら、多角的な視点で世界秩序を捉え直していきます。さらに、哲学は、私たち自身の人生観・価値観を大きく広げ、深めてくれます。人類的古典(グレートブックス)に触れ、自分で考える勇気や、他人と討議する力を養い、未来を生き抜く「創造的精神」を身につける演習にしていきたいと思っています。
ヨーロッパ哲学史上最大の巨人であり、現代哲学の基礎を作ったカントの著作などを学びながら、グローバル化する現代の思想的・社会的課題への示唆を読み取り、問題解決への方途を探ります。たとえば、自由とは、正義とは、世界市民とは、等々の問いを皆で議論しながら、多角的な視点で世界秩序を捉え直していきます。さらに、哲学は、私たち自身の人生観・価値観を大きく広げ、深めてくれます。人類的古典(グレートブックス)に触れ、自分で考える勇気や、他人と討議する力を養い、未来を生き抜く「創造的精神」を身につける演習にしていきたいと思っています。

《現代哲学》 蝶名林 亮 准教授
本演習では哲学的に物事を考察する力を養い、私たちが現在直面している諸問題を適切に考えるために必要な対話力・創造力を養っていきます。具体的には、以下の二つのことに取り組みます。①現代哲学諸分野において重要であると考えられている本や論文を検討します。これまではメタ倫理学の古典であるG. E. ムーアやJ. L. マッキーの著作や、現代形而上学に関する著作などを検討してきました。今後は徳倫理学や認識論に関する著作を検討する予定です。②哲学を活用することで現代社会が直面する諸課題についてどのように考えることができるか、ディスカッションを通して検討し、理解を深めていきます。福祉の分野に関する問題、会社における倫理などを検討する予定です。
本演習では哲学的に物事を考察する力を養い、私たちが現在直面している諸問題を適切に考えるために必要な対話力・創造力を養っていきます。具体的には、以下の二つのことに取り組みます。①現代哲学諸分野において重要であると考えられている本や論文を検討します。これまではメタ倫理学の古典であるG. E. ムーアやJ. L. マッキーの著作や、現代形而上学に関する著作などを検討してきました。今後は徳倫理学や認識論に関する著作を検討する予定です。②哲学を活用することで現代社会が直面する諸課題についてどのように考えることができるか、ディスカッションを通して検討し、理解を深めていきます。福祉の分野に関する問題、会社における倫理などを検討する予定です。

《日本近現代史の基礎研究》 季武 嘉也 教授
幕末以降から現代にいたるまでの日本の歴史について、まず、史料を読むということで歴史がどのようにして成り立っているのかを理解します。さらに、概説書を読んで、現代の日本社会がどこからきて、どこに向かおうとしているのかを探ります。その上で、自由なテーマで卒論を書いてもらおうと思っています。
幕末以降から現代にいたるまでの日本の歴史について、まず、史料を読むということで歴史がどのようにして成り立っているのかを理解します。さらに、概説書を読んで、現代の日本社会がどこからきて、どこに向かおうとしているのかを探ります。その上で、自由なテーマで卒論を書いてもらおうと思っています。
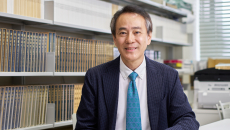
《日本古代・中世・近世史の基礎研究》 坂井 孝一 教授
日本の古代・中世・近世の歴史について幅広く学びます。専門書から参考になる箇所を抜き出して輪読し、内容に関する討論を行い、日本社会の特徴や著名な人物の生き様について考えます。さらに、興味のあるテーマについて研究発表をしてもらい、各人の日本史に対する理解を深めます。
日本の古代・中世・近世の歴史について幅広く学びます。専門書から参考になる箇所を抜き出して輪読し、内容に関する討論を行い、日本社会の特徴や著名な人物の生き様について考えます。さらに、興味のあるテーマについて研究発表をしてもらい、各人の日本史に対する理解を深めます。

《近世東アジア史の研究》 村上 信明 教授
中国の明・清代の政治や社会・文化・外交について学んでいきます。明代は中国における様々な「伝統」のかたちがほぼ固まった時期で、『三国志演義』などの著名な文学作品がうまれた躍動感溢れる時代です。清代はモンゴルやチベット・新疆といった地域が一つの政権によって統治され、現代中国の国家的枠組みが形づくられた時期です。この明・清の歴史を学ぶことで、近世東アジア史への理解を深めていきたいと思います。
中国の明・清代の政治や社会・文化・外交について学んでいきます。明代は中国における様々な「伝統」のかたちがほぼ固まった時期で、『三国志演義』などの著名な文学作品がうまれた躍動感溢れる時代です。清代はモンゴルやチベット・新疆といった地域が一つの政権によって統治され、現代中国の国家的枠組みが形づくられた時期です。この明・清の歴史を学ぶことで、近世東アジア史への理解を深めていきたいと思います。
≪西洋哲学≫ 福谷 茂 教授
西洋哲学の歴史にはいくつかのピークの時代がありますが、17世紀がそのうちの一つであることに異論を唱える人はいないでしょう。デカルト(1596-1650)、スピノザ(1632-1677)、ライプニッツ(1646-1716)の時代は短期間に哲学が大変貌を遂げたエクサイティングな時期です。眼には見えませんが、この時代の哲学者たちはいわば一つのコミュニティに属していて、書簡を交換したり、ときには実際に面会に出かけて共に最前線に立ち、情勢判断とアイディアとを共有していました。彼らに遅れて、そして遠くから、そのメリットを生かしながら彼らの思考を総括していたのがカント(1724-1804)です。沸騰するこの知的世界をのぞきこみ、そのうえで今度は自分なりの土俵において彼らを対話させてみるのが哲学史研究の醍醐味です。こうしたことを目的にして演習を行いたいと思います。
西洋哲学の歴史にはいくつかのピークの時代がありますが、17世紀がそのうちの一つであることに異論を唱える人はいないでしょう。デカルト(1596-1650)、スピノザ(1632-1677)、ライプニッツ(1646-1716)の時代は短期間に哲学が大変貌を遂げたエクサイティングな時期です。眼には見えませんが、この時代の哲学者たちはいわば一つのコミュニティに属していて、書簡を交換したり、ときには実際に面会に出かけて共に最前線に立ち、情勢判断とアイディアとを共有していました。彼らに遅れて、そして遠くから、そのメリットを生かしながら彼らの思考を総括していたのがカント(1724-1804)です。沸騰するこの知的世界をのぞきこみ、そのうえで今度は自分なりの土俵において彼らを対話させてみるのが哲学史研究の醍醐味です。こうしたことを目的にして演習を行いたいと思います。
≪倫理学≫ 成田 和信 教授
この演習は、倫理学を学びたい学生のための演習です。3年生では、アリストテレスの『二コマコス倫理学』の日本語訳を丁寧に読みながら、幸福、徳、意志の自由、責任、勇気、正義、友情などといった倫理学の様ざまな問題について考察します。4年生では、履修者それぞれの卒論のテーマに関する文献を全員で読みながら、それをもとにした議論を通じて、履修者それぞれが卒論のテーマに関する考察を深めていくことをめざします。
この演習は、倫理学を学びたい学生のための演習です。3年生では、アリストテレスの『二コマコス倫理学』の日本語訳を丁寧に読みながら、幸福、徳、意志の自由、責任、勇気、正義、友情などといった倫理学の様ざまな問題について考察します。4年生では、履修者それぞれの卒論のテーマに関する文献を全員で読みながら、それをもとにした議論を通じて、履修者それぞれが卒論のテーマに関する考察を深めていくことをめざします。
≪西洋史≫ 帆北 智子 准教授
西洋(ヨーロッパ、アメリカ)の歴史について幅広く学んでいきます。各ゼミ生が自身の研究テーマを主体的に追究できるよう、歴史学の特徴やその基礎的な研究手法を学び、必要に応じて原語文献の読解もおこないます。また、西洋史という切り口から歴史を学ぶことによって、現代社会が抱える諸問題や世界のありように対する洞察力を養ったり、自己の探求や他者との相互理解にも深く目を向けたりといった、歴史学がもつアクチュアルな側面にも触れてほしいと思います。
西洋(ヨーロッパ、アメリカ)の歴史について幅広く学んでいきます。各ゼミ生が自身の研究テーマを主体的に追究できるよう、歴史学の特徴やその基礎的な研究手法を学び、必要に応じて原語文献の読解もおこないます。また、西洋史という切り口から歴史を学ぶことによって、現代社会が抱える諸問題や世界のありように対する洞察力を養ったり、自己の探求や他者との相互理解にも深く目を向けたりといった、歴史学がもつアクチュアルな側面にも触れてほしいと思います。