哲学は人生の心強い「友」
台風が近づく8月末、研究室にうかがうとそこは、いかにも「哲学者の部屋」らしい空間でした。「国会図書館にない本もあります」と言うだけあって、話題は古今東西の歴史、文学、芸術と多岐に渡り、聞けば聞くほど哲学の魅力と面白さのイメージが広がりました。哲学との出合いの原点は「小中学校時代の先生方の授業です」と“少年の顔”に戻って語る表情が印象的でした。
<div style="text-align: right;"><span style="color:#808080;"><span style="font-size:14px;">※掲載内容は取材当時のものです。</span></span></div>
このたび、『ゲーテ=シラー往復書簡集』を共訳されましたね。
大変ありがたくも、ドイツ文学者の森淑仁先生(日本ゲーテ協会前会長)、田中亮平先生(本学文学部教授)から画期的な翻訳プロジェクトに誘っていただきました。
振り返ると、昔から良い縁に恵まれていたと思います。私は熊本出身ですが、小中学校でお世話になった先生方が、実に興味深い授業をしてくださったんです。
例えば、小学校の音楽の先生はロッシーニの「ウィリアム・テル序曲」を聴かせながら、これはドイツの詩人シラーの劇が元になったオペラで、スイス独立の英雄テルが主人公だと、楽曲の背景を話されました。
中学校の国語の授業では、太宰治の『走れメロス』について、この物語の元になったシラーの詩と比較しながら、みんなでいろんな解釈を考えました。また数学の先生は、幾何学の話のときに、ドイツの文豪ゲーテが自然科学者でもあったことを教えてくださいました。
このような先生方のおかげで、私は、偉大な芸術・文学・哲学を更に深く知りたいと思うようになりました。今回、縁あるシラーとゲーテの翻訳ができ、恩師たちの導きに感謝しています。
カントやショーペンハウアーなどドイツ哲学がご専門とうかがいました。

卒業論文のテーマがカントの『純粋理性批判』でした。ゼミの指導教授の石神豊先生(本学文学部教授)が勧めてくださったのです。ところがカントの本はすごく難しいんです。抽象的な概念で埋め尽くされています。最初、この本は何を言っているんだろうと戸惑いました。卒論は苦しみながら書いたんですよ。提出も締め切り間際の2分前という有り様でした(笑い)。
でも、書きながら、この抽象的な概念の霧の中から、やはりカントの背負っていた時代の課題というものが少しずつ浮かび上がってくるように思えて、いつの間にか彼の哲学に魅了されるようになっていました。
今、研究者として、カント哲学のどういうところに惹かれていますか?
カントが決して完璧な人間像を説いていない点です。一般には、毎日決まった時刻に決まった場所を散歩していた、まるで聖人君子のようなイメージが定着していますが、カント自身はもっと人間くさい人物でした。
ドイツ文学者の池内紀さんが『カント先生の散歩』(潮出版社)の中で書いておられますが、もともとカント自身が友人との待ち合わせに遅れて置いてけぼりにされたこともあったそうです(笑い)。
彼の倫理学にはどこか厳しいイメージがありますが。
それはあくまで、人間のもつ弱さに対する、カントの温かいまなざしが前提にあってのことです。私の好きなカントの一説にこうあります。
「嫌なことが重なり悲しみのあまり希望も失って、生きる喜びをすっかりなくしてしまっているのに、この不幸な人間が気丈にも、気落ちも打ちのめされもせずに、かえって自分の運命に憤慨し、死を望みながらも自分の生命を維持するとすれば、……それでこそ彼の信条は道徳的な内実をもつ」(平田俊博訳)
これは『人倫の形而上学の基礎づけ』の一節です。幸運に恵まれ生きる喜びに満ちている人が「自分の生命を維持する」ことは、ごく当然のことであり、特に「道徳的」な行為とは言えません。しかし、不運におそわれ絶望して死を望むにまで至った人が、それでもなお「自分の生命を維持する」ことは、とてつもなく勇気を必要とすることであり、それゆえ「道徳的」な行為と言えます。
たとえば、ベートーヴェンのような生き方でしょうか。
そう思います。ベートーヴェンは私も大好きです。彼もカントを愛読していました。ベートーヴェンの例が高尚すぎるという方には、漫画『ドラえもん』で説明してみましょう。
例えば、勉強好きで天才の出木杉が「勉強する」のは当然であり、とくに感動的とは言えませんが、勉強嫌いで凡人ののび太が「勉強する」のは尋常ならぬ勇気を必要とするわけで、実に感動的ではないでしょうか。
もっとも、その際にドラえもんの道具に頼らない、という前提条件が必要ですが。のび太がドラえもんに頼らずたった一人でジャイアンに立ち向かったエピソード「さようならドラえもん」が感動的な理由は、ここから説明できます。
この世に苦しみのない人間などいません。もっと強い人間に生まれたかったと思う人もいるでしょう。でも、強い人間が強く生きるのは当然であって、とりたてて賞賛するほどの価値はありません。弱い人間が、それでもなお強く生きようとするところに意味があるのであって、その姿に触れた他の人々にも勇気を与えることになるんです。
そう考えると、カントの「道徳的」という言葉は、「価値ある」という言葉で表現することもできるでしょう。「それでもなお!」という勇気は、それ自体が価値の創造と言えるのではないでしょうか。
カントは平和論でも有名ですね。
カントの考えは、今日の「国際連合」の源流の一つとされるほど、政治的にも影響を与えています。しかし、彼の平和論の中核をなすのが、「世界市民」という概念であることについては、案外知られていません。そこで研究者たちと一緒に『現代カント研究12─世界市民の哲学─』(共著)で論じてみました。
カントの唱えた「世界市民」とは、ただ外国語ができるとか、外国に行っているとか、そんなことではありません。カント自身はそれほど外国語が堪能ではなかったし、一生涯、故郷のケーニヒスベルクから出なかった人です。
では、カントの言う「世界市民」とは?
私なりにまとめると、3つのポイントがあると思います。
①「多様な価値観」があることを認めること。自分の属する文化とは異なる文化にも、開かれた態度で接しようとすること。
②同時に、「普遍的な原則」を探究すること。文化は多様だと言っても、やはりどこでも誰にでも通用する規範があるのではないか。それを考えること。
③しかし、多様な価値観を認めることと、普遍的な原則を探究することとは、相反する場合もあります。どちらにも偏らずに両者を「調和」させようとすること。ここが一番難しく、それだけに大事な点です。
以上の3点がそろって初めて「世界市民」と言える、というのがカントの洞察です。とくに、多様性と普遍性をどう調和させるかは、移民問題で揺れる現代ヨーロッパで非常に重要なテーマになってきています。日本に住む私たちにとっても、これから益々避けられないテーマと言えるでしょう。
そういう「世界市民」を育てるために教育が必要なのですね。
カントは「教育学」という学問を初めて大学教育に取り入れたことでも知られています。近代の教育学の先駆者の一人と言っても過言ではないでしょう。次世代のペスタロッチやヘルバルトに絶大な影響を与えました。
カントは若い時に戦争で苦い経験をしています。本当はもっと早く大学教授になれたはずなのに、当時のドイツ(プロイセン)が戦争をするために国家予算を軍事に当てて教授のポストを削ったために、就職が遅れたんです。
ですから、彼の言う「世界市民」という言葉も、ただ頭の中で思いついたものではないのです。ドイツの軍国主義の被害に遭いながら、しかしそれを個人の問題として終わらせるのではなく、「いかにして平和な世界を創出するか」という人類的次元の問いに昇華させたところが、哲学者らしいと思います。
カントの箴言に「人は、人によりてのみ人となり得べし」とありますね。

『教育学講義』にある言葉です。ただしカントは決して教育を万能視したわけではありません。ある意味で「教育」は、大人の作った「鋳型」に若者をはめこむ傾向があります。人間の成長とは果たしてそういうことでしょうか? とはいえ、外からの何の強制もなしに人間が成長することは可能なのか? このディレンマをカントは問いました。
彼は述べています。「木が野原に一本だけで立っていたら、曲がりくねって伸びてしまう。しかし森の中に立っていれば、まわりの木々の抵抗を受けながら真っ直ぐに伸びて、空気と光を自分の上に求めるだろう」(趣意)。教育のディレンマを表現した見事な言葉だと思います。
人生もまた一つの学校と言えます。そこでは誰もが生徒です。教師も人間である以上、教育はどこまでも手探りの連続です。カント自身、『教育学』という本を完成することはなく、その講義録を教え子が編集して出版しました。私はこのことにも深い意味を覚えます。「未完成」であることが、後世の人間を更なる「完成」へと向かわせるのだと思います。
宮沢賢治の言葉にも「永久の未完成、これ完成である」とあります。
賢治の言葉に共感します。教育とはそういうものだと思います。教員は学生よりも年齢が少しだけ先輩というだけです。知的にも、人間的にも、どちらがより完成か未完成かは分かりません。教員が学生から学ぶことの方が、あるいは多いのかもしれません。
よく、親が子どもから学ぶことのほうが多い、という話を聞きますが、それと同じことかもしれません。子どもが親に反抗しながら成長していくように、学生は教師を乗り越えながら新たな真理を形成していく。でも「乗り越えられる」ことに喜びを持つのが、親であり教師であると思います。
カントの後継者たちにはどんな人がいますか。
一般には、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルといった、いわゆる「ドイツ観念論」の哲学者たちが知られています。しかし、私自身は、もう少し下の世代のショーペンハウアーに注目して博士論文を書きました(『ショーペンハウアー 兵役拒否の哲学 ―戦争・法・国家―』)。ニーチェに大きな影響を与えた哲学者です。
ショーペンハウアーも若い時に戦争を経験しています。19世紀の初め、ドイツがフランスと戦争をする時に「徴兵制」を導入しました。でも彼は、「私はいかなる仕方であれ腕力によってではなく、知力によって人類に奉仕するように生まれついていること、そして私の祖国はドイツよりももっと大きいということ、これを深く確信していた」という理由で兵役を拒否しました。
こうした経験から、ショーペンハウアーは「なぜ人間と人間は争うのか」「国家とは何か?法とは何か?」「果たして人類は進歩しているのか?」と、深い哲学の思索へと入っていったのです。
哲学は一見、抽象的な概念を並べているように見えますが、偉大な著作の背景には、やはり人類の歴史が刻印されていることに気づかされます。
ベートーヴェンがカントを愛読していたとおっしゃいましたが。
ベートーヴェンは交響曲第9番で、シラーの詩『歓喜に寄す』に音楽を付けましたが、その作曲ノートに、「我が上なる星輝く天空と、我が内なる道徳法則」というカントの言葉を記しています。
当時ヨーロッパはフランス革命後の激動の時代でした。血で血を洗う闘争の社会から、いかに平和な民主社会を実現していくか。この問いを、ベートーヴェンはカントと共有していました。ある意味で、ベートーヴェンの音楽も、カントが探究した「道徳法則」の芸術的な表現と言えるかもしれません。
ベートーヴェンとカント。このテーマについては、以前、石川県西田幾多郎記念哲学館でも講演したことがあります。今秋、仙台でも講演する予定です。機会があれば一冊本を書いてみたいとも思っています。
昨年、ドイツで在外研究をされたそうですね。そのときのエピソードがあれば教えてください。
マインツ大学のショーペンハウアー研究所で、一年間お世話になりました。第一線で活躍する学者の方々と交流でき、夢のような毎日でした。ドイツにいて特に感銘を受けたのは、市民生活の中に読書サークルなど、哲学的な団欒をする習慣が定着していることでしょうか。
ドイツに行って最初の一週間が経ったときのことです。レストランで食事をしていると一人のおじいさんから「研究者ですか?」と声をかけられました。「はい、哲学の研究で日本から来ました」と答えると、「では、今度訪ねていらっしゃい。いっぱい本を持っているから」とおっしゃるのです。
次の週にうかがうと、本当に家全体が図書館なんです。その方は88歳で、エーデル博士という著名なドイツの神学者・思想家でした。若いころにヘルマン・ヘッセと文通をし、哲学者ヤスパースにも学び、ヴァイツゼッカー元統一ドイツ大統領などとも対話を重ねてきた知識人だったのです。
それは素敵な出会いでしたね。
このエーデル博士を囲む読書サークルがあって、毎月一緒に食事をするんです。老若男女が一緒にワインを飲みながら、さまざまな話題で議論の花を咲かせます。相対性理論や量子力学といった物理学の話から、移民問題など現代の政治問題まで。そういう議論の習慣が根付いているんですね。
帰国する前、エーデル博士のお宅にあいさつにうかがいました。すると博士は私に一通の手紙を渡されて、「私の夢はアジアの若い人と対話をすることだ」と言われました。「私はキリスト教の伝統で育ったが、私の考える神の概念はおそらくアジアの思想に近いのではないかと思っています。ここに私の質問を書いておきました。もしよければあなたの意見をうかがいたい」、と。
博士のみずみずしい好奇心、真摯な探究心、そして何より外国の一学徒に対する温かな思いやりに、私は胸一杯になりました。ヨーロッパ知識人の「知への愛」を肌で知った瞬間でした。
学生へのメッセージをお願いします。

本学に入学したころ、ある先生がこうおっしゃったんです。「大学の4年間は、お金を出して買った4年間です。買ったのは単なる授業ではない。自分の時間だよ。その時間を、人に何を言われようと、自分で判断して使いたまえ」。
私自身は、できるだけ多くの歴史上の古典を読みたいと思って、4年間努力したつもりですが、確かに、人生で一番本を読めたのは学生時代でした。もちろん、本を読むだけが勉強ではないのですが、純粋に読書に没頭できる時間が「権利」として与えられているという点で、やはり学生時代は特別だと思います。
受験生にも一言。
私も高校時代、成績が伸び悩んで苦しんだ時期がありました。そんな時に、ソクラテスの「不知の自覚」という言葉を知りました。「知らない」という自覚があるからこそ、「知への愛」も湧いてくる。逆に、「もう分かった」という満足は、更なる探究を怠る油断になってしまうこともある。なので、「知らない」「分からない」ことは決して恥ずかしいことではなく、むしろ「知りたい」「分かりたい」という思いを起こさせてくれる素晴らしい「愛知力」の発露なんですね。
目先の成績に一喜一憂することなく、壁にぶつかった時こそ、自分の中に「愛知力」が宝石のように輝いていることを信じていただきたいと思っています。
最後に、哲学の効用について教えてください。
人生、迷った時には哲学が支えになります。ただしそれは、必ずしも哲学者たちが答えを教えてくれるからではありません。答えを求めて「考え抜いていく」勇気を教えてくれるからです。
私たちが人生でぶつかる問いには、往々にして「正解」が存在しないものです。そうした問いに出合った時に、哲学書はいわば悩みの「質」を転換してくれます。世界について、人間について、通常では思いつかない視点を提供してくれるので、目の前の悩みが吹き飛ぶ思いになります。それで一歩先に進むことができます。もちろん人生は、自分の足で歩むほかないのですが、そのための心強い「友」が哲学であると言えるでしょう。
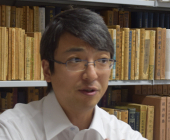
[好きな言葉]
「私は考える、故に私は存在する」(デカルト)
「汝自身の悟性を使う勇気を持て」(カント)
「良書を読むための条件は、悪書を読まぬことである」(ショーペンハウアー)
[性格]
オープン。ただし単独行動を好む。
[趣味]
音楽・美術鑑賞。(ドイツでの在外研究中は、毎週のように教会の無料コンサートに足を運んだ。モーツァルトが葬られたウィーンの共同墓地、ベートーヴェンが「遺書」を書いたハイリゲンシュタットを訪ねた時は、思わず目頭が熱くなった)
[最近読んだ本]
松本清張「断碑」「菊枕」「石の骨」。(学問の世界も、しょせんは人間の世界。清張はそのことを恐ろしいほど鮮やかに描く。権力欲や名誉欲に翻弄される主人公たちの姿は、哀れを誘うが、憎めない。同じような欲望は自分のなかにもあるのだから)
[経歴]
- 創価大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(人文学)
- (財)東洋哲学研究所研究員。日本ショーペンハウアー協会理事
- マインツ大学哲学科ショーペンハウアー研究所客員研究員(2015-16年)
- 『ゲーテ=シラー往復書簡集(上・下)』(共訳)、潮出版社、2016年。
- 『ショーペンハウアー 兵役拒否の哲学―戦争・法・国家―』(単著)、晃洋書房、2014年。
- 『現代カント研究12―世界市民の哲学―』(共著)、晃洋書房、2012年。
- 『ヘルマン・ヘッセ エッセイ全集8―時代批評―』(共訳)、臨川書店、2010年。
- 『ショーペンハウアー読本』(共著)、法政大学出版局、2007年。
- 『ヘルマン・ヘッセ全集4―車輪の下・物語集Ⅱ―』(共訳)、臨川書店、2005年。
- 『ヘッセ 魂の手紙―思春期の苦しみから老年の輝きへ―』(共訳)、毎日新聞社、1998年。







