「空心菜」で社会貢献?―カンボジアの水上生活者をサポートするプロジェクトに挑戦!

茎の中が空洞であることから名づけられた「空心菜」は、アジア地域を中心に野菜の一種として炒め物や汁ものの具、お浸しなどの食材に用いられています。この「空心菜」を用いて、アジア最大の湖であるカンボジアのトンレサップ湖に住む人々の水環境意識を高めることを目的に、本学グローバル・シティズン・シップ(GCP)の学生6名が「空心菜プロジェクト」に挑戦しました。
本年8月には、熱帯湖の保全管理をテーマにカンボジアで開かれた国際シンポジウムの主催者からの招聘で、「空心菜プロジェクト」のポスター発表、ワークショップの講師を務めるなど現地の人達から大きな反響を呼びました。
本プロジェクトの立案は昨年(2016年)9月からGCP(※1)授業科目の一環でスタート。船戸明美さん(教育学部4年)、永峰正一さん(経営学部3年)、田村広来さん(経営学部3年)、加藤孝征さん(経済学部3年)、斎藤歩美さん(経済学部3年)、遠藤葵さん(教育学部3年)の6名で活動を続けてきました。今回は、船戸さんにプロジェクトに込めた思い、現地の人達の反応、これまでの大学生活の学びなどを語っていただきました。
8月にカンボジアでの国際会議で発表したんですね。発表の概要を教えてください!
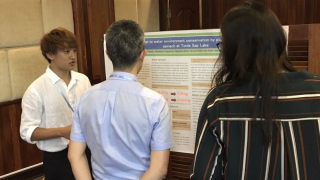
本年8月24日から26日にかけてカンボジアのシェムリアップで開かれた国際シンポジウム「The 2nd International Symposium on Conservation and Management of Tropical Lakes」(主催:カンボジア工科大学、東京工業大学、地球環境戦略研究機構(IGES)、山形大学)に、一緒に「空心菜プロジェクト」に取り組むメンバーと参加してきました。
私たちは、カンボジアにあるアジア最大規模の湖、トンレサップ湖に住む水上生活者の環境意識の啓発と水質浄化を目的とした「空心菜プロジェクト」に関するポスター発表を行いました。

また、シンポジウムの公式プログラムにあたるトンレサップ湖の視察ツアーでは、現地の公的機関職員や研究者、現地の水上生活者を含めた約70名を対象として、プロジェクトに関連するワークショップを水上村で実施しました。
私たちが取り組む「空心菜プロジェクト」は、カンボジアの食卓で日常的に登場する野菜で水質浄化能力をもつ空心菜を用いて、トンレサップ湖の水質改善と現地住民の環境意識の向上を同時並行で行うものです。トンレサップ湖の水上生活者の船やイカダに水耕栽培用の浮島を直接取り付けることで、各家庭での栽培を可能にしながら、空心菜栽培促進イベントと独自の環境教育を並行して展開していきます。
「空心菜プロジェクト」に込めた思いを教えてください。
トンレサップ湖での魚の水揚げ高はカンボジアでの内水面漁業の半数を占めており、約300万人が湖の天然資源に依存していると言われています。また、湖の氾濫原に住んでいる120万人のうち、32万人が湖での水上生活を送っています。近年、水中への過剰な養分の排出により水中の窒素やリンが過剰に増える「富栄養化」とそれによる「アオコ」の発生が問題になっていました。アオコが増殖すると水中の酸素を大量に消費し、魚が生存できないなどの問題がおこるため、水質の著しい悪化の印として知られています。
水質改善の先行研究を調べていく中で、中国野菜の一種である空心菜の栽培が水質浄化活動に効果的な手法の一つであることを知りました。空心菜を用いるメリットとして、機械等の導入が不要で低コストである点、現地の生態系に害を及ぼさない点、現地住民にとっても日常的に馴染みがある野菜である点や、栄養価が高く有用な栄養源である点などが確認されました。

水質管理に詳しい水質工学の先生や、過去に空心菜による水質改善研究を行なっていた農学の先生、現在も空心菜を用いた水質浄化活動に取り組んでいる農業高校の先生やNGO団体等にインタビューを実施。その結果、有効性とニーズがあるものの活動が継続しなかった理由が明らかになりました。その結果、1点目に水上生活者に対し、空心菜の栽培方法や水質浄化のプロセス等の知識伝達が困難であること、2点目に水上生活者の水環境に対する意識が高くないことが判明したためです。
空心菜の水質浄化能力や水耕栽培の実現性は先行研究により証明されていることから、それを利用する住民のサポートが課題であることを認識し、「水上村で生活する人たちの水環境意識を向上させる」ことを「空心菜プロジェクト」の目標に定めました。科学的に論証された水質改善の研究成果を活用し、メディエーター(仲介者)のような立ち位置で、水上村の人達の生活改善を実際にサポートできればと考えたのです。

水上村でのワークショップに参加した人たちの反応はどうでしたか?

プロジェクトを進めるにあたって、現地の実状に即しているかを特に心がけていました。カンボジアをはじめ発展途上国では、様々な団体や人たちが教育や環境活動など社会貢献に取り組まれていると思います。今回のプロジェクトも現地の人達の確証的なニーズがなければ、続けるつもりはありませんでした。
ワークショップの前に、水上村に足を運び、そこで生活する人たちにインタビューした結果、私達が感じていたことは、水上生活者の課題でもあることを認識しました。

水上村で実施したワークショップでは、参加者と一緒に、空心菜を水上で簡単に栽培するための竹製浮島を製作しました。現地の方から「実際にやってみたいと思う。これならできそうだ」と言っていただけたことが嬉しかったです。アフリカで水質改善に取り組む団体の方も参加しており、「うちの国でもやれそうだ。応用性がある取り組みだね」と声をかけてくだったことも、印象に残りました。
また、今後も水上生活者の方が人の力に頼らず簡単に自分達で栽培できるよう、水質改善の必要性や空心菜栽培のための教材やマニュアルも作成しました。
「空心菜プロジェクト」の取り組みを通して感じたことを教えてください。
「空心菜プロジェクト」は地球的規模の課題に対する解決策を考案するGCPの授業科目のひとつである「プログラムゼミⅣ」の一環で立案しました。この授業は、テーマごとにグループが構成され、問題発見から課題解決の企画立案までを半年間かけて行い、最後にプレゼンテーションするものです。GCPは学部横断型で学生が集まるため、一つのトピックにも様々なアイディアが出て議論が深まるのが特徴でもあります。今回のプロジェクトの立案に際しても、文献調査と議論を徹底しながら、学内だけでなく学外の研究者や各種団体にアプローチするなど、精力的に取り組みました。その結果、水質改善に取り組む様々な方とのネットワークができ、今回のカンボジアでの国際シンポジウムへの参加に繋がりました。

私自身としては、これまでユースとしてどのように具体的に社会のために行動できるのかを考えていました。海外留学や国外の学生会議などに参加する中で、同世代のユースが次世代を担う自覚に立ち、各国で自発的に社会貢献活動する姿を見て、日本でも同じようにできるのか、社会が受け入れてくれるのか疑問を抱いていました。しかし、今回の取り組みを通して、熱意と信念を持って社会にとって有益な働きかけをして、必要性を感じてもらえれば、年齢や立場は関係なく応援していただけることを肌で感じました。

今回のプロジェクトには、留学時代の経験も生きているんですね。

ここからは私個人の話になりますが、高校3年生の時、ボランティアでカンボジアに1週間行った際、トンレサップ湖に訪問しました。茶色に濁った様子や川岸に散乱するゴミ、その湖の上で生活している人がいることに衝撃を受け、このような環境問題を何とかしたいとの気持ちが芽生えました。今思えば、今回のプロジェクトにも繋がる体験だったと思います。
大学入学後の1年次の夏には、小学校の先生をアシストするボランティアで、アフリカのタンザニアに3週間行きました。授業を受ける子どもたちの目の輝きが強く印象に残りました。教材も不足する中で教科書を友達とシェアするなど、恵まれない教育環境でも学びを渇望する子どもたちに対し、自分に何ができるのかを考える機会となりました。世界で起きている課題を自分の目で確かめる重要性を感じるとともに、社会が求めていることに対して柔軟に対応できる力をつけていこうと思いました。

また、大学3年次には第2外国語を習得しようとスペイン語圏のデル=バーリエ大学(ボリビア)に交換留学し、観光とビジネスを専門に学びました。ホームステイ先のホストファミリーから、ボリビアのコチャバンバで2000年に発生した「コチャバンバ水紛争」の話を聞きました。国営から民営化された水道事業を一民間企業が独占したことで水道代金が5倍以上に上昇。それに対し、市民が武器を片手に反対運動を起こし死傷者が出たとの実態を聞きました。水資源は人間の生存に必要不可欠であることを再認識し、それまで以上に水問題に関心を持つようになりました。
今思えば、日本を離れて様々な国を訪れて、自分の目で見たことや直接聞いたことが、今回の「空心菜プロジェクト」に少なからず生きたのかもしれません。
最後に大学生活を振り返っての感想をお願いします!
「留学に行ったから英語力が伸びたんだよね?」と言われることが多いですが、英語の勉強は学内で続けてきました。留学生と触れ合う機会が多いことも創価大学の魅力の一つですが、数多く展開される英語での授業や英語でディスカッションするイングリッシュフォーラムなど、学術的かつ実践的な英語力を高める教育環境が整っており、自分のやる気さえあれば英語力を大きく伸ばすことができます。英語ができたからこそ、今回のカンボジアでの国際シンポジウムにも招聘され、多くの人とのネットワークを広げることができました。英語は学内で身につけられる分、留学はスペイン語圏に挑戦し、自身の語学の幅を広げることができました。

また、GCPでは様々な学部から集まる仲間と学ぶ中で多様な考え方を共有できるとともに、GCP担当の先生方の熱意に触れながら、綿密に構成されたプログラムの中で、国際社会で必要とされる数理能力や問題解決力などを効果的に培うことができました。その他、私自身、内閣府主催の「世界青年の船」やアジア開発銀行主催の「アジアユースフォーラム」、「南米ビジネスフォーラム」などへの参加を通し、世界の同世代のユースと対等にディスカッションし、時間を共有できたことは視野を広げる貴重な機会となりました。
世界に目を向ければ、貧困や紛争、環境、教育をはじめ多くの課題があります。根源的な課題を特定し、本質的な解決策を導出、実行する一過程に携わり、持続可能な社会の実現に携わりたいと、私は考えています。本当に困っている人たちのために力をつけ、いつでも柔軟に対応していけるよう成長し続けようと決意しています。そして、今後も自分のいる場所で、「社会が本当に必要とするものは何か?」を常に考え、行動していきます!

[好きな言葉]
“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” (Viktor E. Frankl)
[性格]
好奇心旺盛
[趣味]
散歩、音楽づくり
[最近読んだ本]
「学問のすゝめ」 (著者:福沢諭吉)










