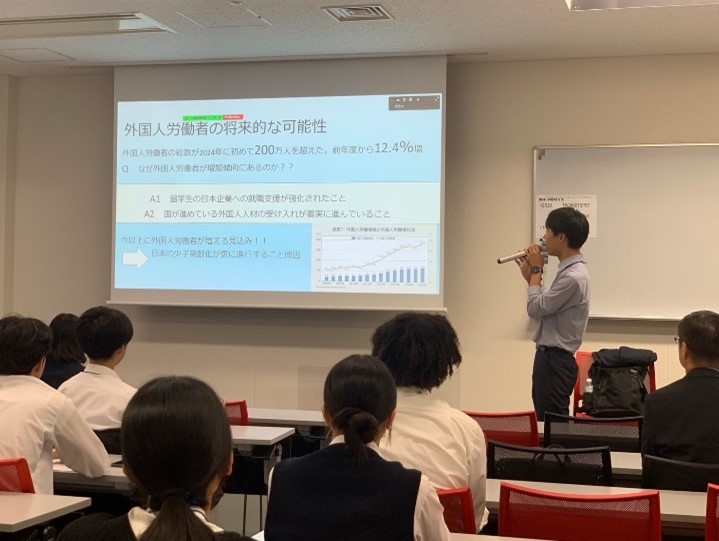創価大学ユネスコスクール支援委員会

創価大学ユネスコスクール支援委員会委員長挨拶
創価大学教育学部・教職大学院は2018年7月、新たに「ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet)」に加盟させていただきました。今後、これまで支援活動を展開してこられた大学と連携協力し、主に東京都北西部を中心に埼玉県、群馬県所在の初等・中等教育機関を対象にユネスコスクール加盟を支援する活動を展開して参ります。
国連が進める「持続可能な開発のための教育(ESD)」、さらにそれに続く「持続可能な開発目標(SDGs)」は、今や世界中の大学で取り組まれる共通課題となっています。国内外の1万を超える学校が結び合い、世界中でESDを推進するユネスコスクールのネットワークに加わらせていただいたことは、本学にとっても大きな喜びであり、本学が持つ特色を大いに発揮するチャンスととらえていきたいと思います。
創価教育の創始者である教育者・牧口常三郎は、「価値といひ得べき唯一の価値は生命であり、爾余の価値は何等かの生命を交渉する限りに於てのみ成立する」と述べ、生命を価値の究極に位置づけました。また主著である『人生地理学』の冒頭において自然環境が人間形成に及ぼす影響の重要性を訴え、自然とのコミュニケーション不足が人間のさまざまな美徳を破壊してしまうと指摘しています。また本学の創立者である池田大作は、2019年の平和提言において、SDGsに対する本学の取り組みを紹介したあと「世界のより多くの大学がSDGsの推進のためにさらに力を注ぎ、誰も置き去りにしない地球社会を築くための行動の連帯を強めていくべきではないでしょうか」と主張しています。
こうした理念に基づいて人間教育、平和教育を進める創価大学では、多くの教職員、学生が、明日のよりよい世界を創造することを目指して学び、これまでもゼミやクラブ活動等でさまざまな行動を展開してきました。そうした取り組みが評価され、2019年のTHE大学インパクト・ランキングにおいて創価大学は、日本の大学の中では4位に相当する101-200位にランクインしました。
このように、本学のマインドはユネスコスクールの理念と極めて強く調和・共鳴するものであり、これからのユネスコスクール支援活動においても、大きな力を発揮できると感じます。支援活動はまだ開始したばかりですが、今後の日本におけるユネスコスクール運動を支える存在になれるよう、関係教員一同、力を合わせて取り組んで参ります。
創価大学副学長
関田 一彦

ASPUnivNet加盟の経緯
国連による「持続可能な開発のための教育(ESD)」を推進する学校として、ユネスコスクール加盟校が広がりを見せており、そのネットワークは世界182カ国で約11,500校に上ると言われています。日本では公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)がユネスコスクール事務局として2008年以来ユネスコスクール加盟の支援をしてきており、2018年4月現在で1,033校の幼稚園、小・中・高等学校、教員養成大学が加盟しています。本学も2022年4月にユネスコスクール・キャンディデート校として承認されました。
また、2008年12月にユネスコスクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet)が発足し、文部科学省とも連携を取りながら、ユネスコスクールに加盟しようとする全国の学校への支援活動を行っています。こうした動きに合わせ、本学でも2018年5月の拡大学長室会議を受けてASPUnivNetに加盟申請を提出し、2018年7月1日の定例連絡協議会にて本学の加盟が正式に了承されました。
《本学の組織》
(1)名称:創価大学ユネスコスクール支援委員会
(2)構成メンバー
委員長 関田 一彦 教職大学院教授/副学長
副委員長 吉川 成司 教職大学院教授/通信教育部長
メンバー 宮崎 猛 教職大学院教授
久保田 秀明 教育学部教授
山内 俊久 教育学部准教授
三津村 正和 教職大学院准教授
島田 健太郎 教育学部講師
津山 直樹 教育学部講師
オブザーバー 鈴木 将史 教育学部教授/学事顧問
山﨑 めぐみ 学士課程教育機構教授
事務担当 吉村 隆幸 教育学部事務室副課長
ユネスコスクールチャレンジ校等応援企画講演会
ユネスコ教育勧告とユネスコスクールの意義
12月10日の「人権デー」を記念し、12月12日(金)16時40分より創価大学教育学部棟1階B103教室において、ユネスコスクールチャレンジ校応援企画講演会「ユネスコ教育勧告とユネスコスクールの意義」を開催致します。
本講演会は人権、平和、持続可能な開発の推進を目的とするユネスコの精神を具体的な教育活動に落とし込んで取り組むユネスコスクールの意義を再確認しつつ、ユネスコスクールチャレンジ校の取り組みについて、関心のある教職員、学生、そして現場の先生方とともに学び合う機会にしたいと思っています。基調講演者であるユネスコ教育勧告特別委員会委員長 風巻浩先生からは、「ユネスコは2023年に教育勧告を改訂した。短縮版の名称では「平和、人権および持続可能な開発のための教育勧告」と呼ばれる本勧告は、人類の未来を創る教育の基本文書となっている。互いにつながりあうことで生き生きするという意味を持つコンヴィヴィアルな関係性が教育で大事であることなど本勧告の内容をユネスコスクールの意義にも関係させて紹介していきたい。」との抱負を頂いています。
〇日時:2025年12月12日(金)16時40分開始
〇場所:創価大学教育学部棟1階B103教室(zoomでのオンライン視聴も可)
〇参加費用:無料
〇申込方法:以下のURLからグーグルフォームに必要事項を入力の上、お申込み下さい。
創価大学ユネスコクラブの活動
創価大学ユネスコクラブが第5回ユネスコスクール関東ブロック大会で分科会の企画及び、シンポジストとして登壇しました。
2024年10月5日(土)に第5回ユネスコスクール関東ブロック大会が玉川大学にて開催され、本学ユネスコクラブのメンバーが参加しました。ユネスコスクールの新たな展開にとってカギとなる若者エンパワメントに向けて教師に求められる新たな役割と課題について多角的に検討する大会です。
午前の部では、次世代の持続可能な社会の担い手である若者への支援と権限付与を効果的に実践できる教師の姿について同志社大学の見原教授による基調講演・シンポジウムが行われました。また、シンポジウムには、創価大学から、ユネスコクラブ (学生団体)の代表・盛島杏莉さん(教育学部3年)と顧問の島田健太郎講師が登壇しました。
午後の分科会では、関東地域のASPUnivNet加盟大学および次世代ユネスコ国内委員会による分科会にて、さまざまな関連テーマについて議論が行われました。創価大学ユネスコクラブの分科会は、「多様な視点を体験的に学ぶ、異文化シミュレーションBafaBafa」というテーマのもと、他者視点の獲得や自分の行動様式を知ることを目的とした体験的な活動を行いました。
分科会の企画を行なったメンバーは、山本航大さん(教育学部4年)、籔本朋華さん(教育学部4年)、盛島杏莉さん(教育学部3年)、郁天華さん(教育学部2年)、国松和明さん(法学部1年)です。本学における留学生支援や外国人労働者の将来についての話をしながら、日本の文化や文化交流の意義について議論が深まりました。
分科会の参加者からは以下のような感想やコメントを頂きました。
「社会により、価値観やコミュニケーションの仕方が異なることを体感できた。新しい文化を知ることは楽しい。」
「仲良くしようという気持ちを持って相手と接することは大切だと思った。しかし、全く違う文化を理解するのはとても難しく感じた。」
参加したユネスコクラブの学生の声を紹介します。
「分科会で行った異文化シミュレーションBafaBafaでは、高校生を中心に擬似的に異文化間の交流のあり方を考えてもらうことができました。自分自身もファシリテーターとして参加し、学校現場における国際理解教育の実践とその課題について深く考えることができた良い機会となりました。」(女子学生)
「自分は初めてユネスコスクール関東ブロック大会に参加し、緊張もありましたが、それまでの準備や打ち合わせが身を結んだと思います。参加してくださった方々が異文化理解の難しさを少しでも感じ、その後の生活に通ずるものを感じ取っていただけたら幸いです。」(男子学生)
「分科会では、異文化シミュレーションBafaBafaのファシリテーターを務めました。参加者の取り組みの声を身近で聞くことができたことが自分の学びにつながったため、とてもうれしく思います。また、他の分科会の様子も最後に聞いて吸収することができ、これからの成長の糧となったと感じました。」(女子学生)
「午前中にシンポジウムにパネリストとして登壇し、他大学の教授や小・中学校、高校の教員達と一緒に若者エンパワメントについて話し合い、教師の役割や目指すべき姿について学ぶことが出来ました。第2分科会では、参加してくださった学生の方や先生方から、異文化を理解することの難しさや文化を知ろうとすることの大切さを感じたという声や、自分の学校や授業においても実践してみたいとの声をいただくことができました。参加してくださった方にとって充実した時間になったことを実感でき嬉しく思います。」(女子学生)
「多くの方が分科会に参加していただいて感謝しています。参加者は高校生から現役教員の方などいらっしゃり、そこでも文化が異なっていました。異文化に触れ、慣れる大変さを日常の中で異文化だと感じた際、受容することは大変難しいことだと思います。留学生が徐々に増加していく中で、教員や生徒は異文化をどう受け入れるか、あるいは文化の違いが譲れない際どのように接するかを私自身も常に考えていきたいです。」(男子学生)