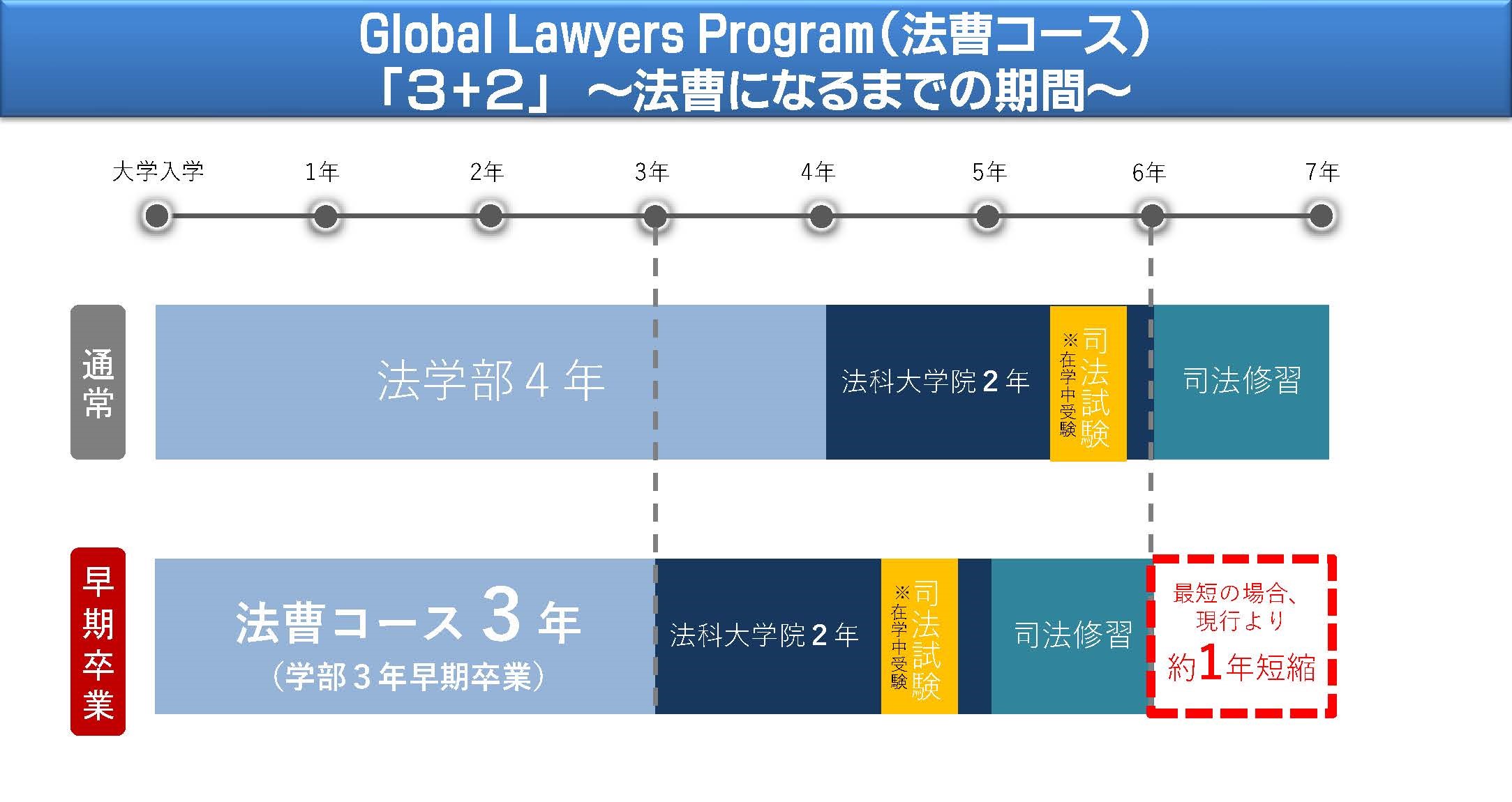学部の特長
市民生活・ビジネス法コース
市民生活を安心安全に送るための 法知識の修得と、 優秀なビジネスパーソンになるための 法律・ビジネス知識を修得します。
コース概要
「市民生活のための法務」では、トラブルに対する法的解決力やトラブルを未然に 防ぐための予防法務としての法的知識など、市民生活に必要な法律の知識修得を 目指します。また、ビジネス法務では、法的思考に基づく問題処理能力の獲得やコンプライアンス意識の定着と向上など、ビジネスパーソンとして身につけるべき 法的および経営学的な基礎知識・専門知識の修得を目指します。さらにビジネス 実務法務検定をはじめとした必要な資格取得に関するサポートも行っています。

科目紹介
科目紹介

労働法
労働法は、とても身近な法律ですが、正しく理解できている人は多くありません。それはハラスメントや不当解雇などのニュースが連日報道されていることからも明らかです。そのため、働く人は自分を守るための知識を持つことが重要であり、また会社側も有能な人材を確保して活かすには人的資源を大切に扱えることがカギになります。本講義では、そうした労働法の基礎理論と今日的な諸問題について一緒に考えます。

ビジネス&ロー・ワークショップⅡ
「世界を変える企業を探せ!」をテーマに、学生主体+グループワークを通じて学ぶ産学連携の課題解決型授業です。「野村證券の支店長講義」「社会人メンターのサポート」「実務家とのワークショップ」「研究発表会」「アジア開発銀行専門官の特別講義」など、ESG※とSDGs、世界の今後から 日経新聞の読み方のコツまで、授業の内容は盛りだくさん。最新の知識と企業分析スキルを身につけるとともに対人能力の獲得も目指します。
※ESG:「環境(Environment)・社会(Social)・企業統治 (ガバナンス・Governance)」

ファイナンシャルプランナー入門
講義では、金融機関への就職活動および就職後の実務にも必要となるファイナンシャル・プランナー(FP)に合格するための知識を身につけます。FPは年金、税金、生命保険、損害保険、 不動産、相続、金融商品など幅広い分野に関わるため、自分の人生においても大いに役立つ資格です。FP試験の特に学科試験に焦点を当て、 実際の学科試験問題に多く取り組む形で学習しながら、まずはFP3級の合格を目指します。
公共政策・行政コース
政策課題や社会の公共的課題を見つめ、演習と実践を交えながら解決するための手法と思考力を養います。
コース概要
「正解のない問題」に取り組む際に必要となる課題発見能力と問題解決能力を身につけることができるコースです。「法律系」と「政治政策系」の2つの系統からカリキュラムが構成されており、両方の専門領域を関連づけながら学ぶことにより、公共政策の総合的な理解を促します。また、八王子市と連携したフィールドワーク、インターンシップ、探究型のワークショップなどを通じて実践形式でリアルな学びを深めることができるのが魅力です。

科目紹介
科目紹介

まちづくり八王子フィールドワーク
キャンパスがある八王子市の全面協力のもと、フィールドワーク(現地調査)によって地域社会を観察することで、直面している政策課題を発見し、その解決策を市側に提案します。毎年、子育て支援、中心市街地の活性化など多彩なテーマを取り上げており、まさに「まちづくり」をリアルに体験できる授業です。こうした探究型学習の実践に取り組むことを通じて、公共政策について、より具体的に学ぶことができます。

公共政策論
私たちの社会は大きな転換期にあります。これまでの仕組みが問い直しを受け、多くの政策分野で新たな制度設計が求められています。直面するさまざまな課題について、政治学と法学を駆使しながら、「正解のない問題」についてその解決策を考えるのが公共政策論です。SDGsの17の目標すべてが公共政策の対象となります。 未来の「社会実装」を考え、創造する最先端の学問領域です。

公共政策ワークショップ
チームでの協働学習を通じて、問題を自分たちで探究するグループプロジェクト型の授業です。 地方創生まちづくり、子育て支援や女性の活躍、 高齢者が輝ける社会、観光と地域経済、災害と危機管理など、現代社会が抱える政策課題についてグループ研究を行い、そこに公共政策の最前線で活躍する実務家たちを招致します。理論と実践を掛け合わせたリアルな学びで即戦力の実力が養えます。
国際平和・外交コース
地球的課題の解決に貢献するグローバルリーダーとして、 平和問題に関する高い専門知識と語学力を身につけます。
コース概要
「人間の安全保障」を理念として、「平和」「人権」「環境」「開発」の4分野と多様なアクターを軸とした国際問題に対する幅広い専門知識を修得します。地球的諸問題の解決に必要なグローバルな視野と世界市民としての人権感覚を磨くべく、理論と実践双方の視点からワークショップやフィールドワークも取り入れ、学びのサイクルを展開していきます。さらに国際社会での活躍を見据え、All Englishでの授業にもチャレンジします。

科目紹介
科目紹介

国際法各論
国際法は国際社会の法で、条約や慣習国際法などを指します。難しいイメージを持つかもしれませんが、とても魅力的で面白い分野です。 第1にダイナミックな法で、領土や海や空、宇宙のルールまで国際法が決めています。第2に、紛争や人権、気候変動など地球的課題の解決と平和に不可欠な道具です。第3に国内法と比べると未熟な法でもありますが、逆に法とは何か、世界とは何かを考えさせてくれます。

International Relations
International Relationsの授業では、国際レベルで各国がどのように相互作用しているかについて学ぶとともに、国益や国家アイデンティティーが、どのように国家間の緊張を生み出すかについても学びます。特に、このような緊張を緩和するために作られた国際機関、経済協力、共通規範などのメカニズムについて学べることも大きな特色です。一緒に世界平和を構築するための道を探ってみましょう。

人間の安全保障論
世界は戦争や貧困、人権、環境など諸課題を抱え、自国中心主義による対立と分断が深まって います。国家の役割や安全保障が問われる中、人間の生存、生活、尊厳に立った新たな安全保障概念として、冷戦後に国連を中心に登場したのが「人間の安全保障」です。「人類の平和を守るフォートレスたれ」との建学の精神にもとづき、あらためて「平和」とは何かについて考えてみたいと思います。
環境・サステナビリティコース
これからの循環共生型社会を実現するために、地球規模の課題に対して法と政策の観点から学びます。
コース概要
法や政策はもちろん、「環境を守りながら社会全体が発展し、心の豊かさも重視した社会」の実現に向けた知識や思考力、問題解決能力を身につけるコースです。 さらにコミュニケーション能力をはじめ、共生を意識し多様性を受容できる力と他者と協働できる力の修得を目指します。また、実践型プログラムを多く取り入れ、 実践的な学びを主体として、SDGsを応用展開できる人材を育成していきます。

科目紹介
科目紹介

環境法
「地球は先祖から受け継いでいるのではない、 子どもたちから借りたもの」(サン・テグジュペリの言葉)。環境法は現在と将来世代のために、環境保全上の支障を防止し、良好な環境の確保を図ることを目的とする法制度です。講義では地球温暖化防止法制、循環型社会と廃棄物・リサイクル、自然環境保全その他環境に関する法制度を学びます。 明日なすべきことを今取り組むことで、地球環境を保全し次世代に継承していけると考えます。

惑星政治学
惑星政治学は、国家の生存戦略を重視してきた国際政治学が人類の絶滅可能性を直視できていないという問題意識から、「地球」との関係で「人間」を捉え直す新しい学問です。「人新世」に突入した現在、人類は、生態系との関係抜きで生存を論じることはできません。頻発する自然災害は、人類が地球に対して行ってきた「戦争」への反撃であり、早急に自然との共生を実現する必要があるのです。

地球共生・平和創造フィールドワーク
この授業では、人間と「地球/大地」との関係を、キャンパスや里山の大地の再生実践を通じて考察。土の手入れを行いながら、水はけや通気性を改善させ、土が単なる物質ではなく、生き物の関係性の網の目でできていることを体感していきます。つまりは、人間は大地の再生に関わっていけることを身体感覚で学び、希望を見出していく授業といえます。日ごろの座学でカチカチに固まった思考を解きほぐしましょう。
リーガルコース
社会生活のさまざまな場面で起こる法的紛争の解決に携わるために、 法律の専門的知識を体系的に身につけます。
コース概要
法律に関するプロフェッショナルを目指すコースです。基本科目となる「憲法」「民法」「刑法」「会社法(商法)」「行政法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」を中心に、それぞれの法領域で各法制度がどのように関係し、正義の実現が図られているのかを体系的に整理して理解・修得します。また、法務演習などで行われる事例問題や判例研究を通じて実例に触れながら解決法を検討し、法適用や諸制度の運用をめぐる課題解決に取り組むことで社会に通用する応用力も養っていきます。

科目紹介
科目紹介

刑法総論/刑法各論
刑法は、どのような行為が犯罪となり、それにど のような刑罰が科せられるべきかを学び、考えます。1年秋の「刑法総論」は犯罪に共通する重要な事項を、2年春の「刑法各論」は犯罪ごとの成立要件を学び、高い専門的知識と論理的思考力を身につけます。2年秋以降は、刑法ゼミや 関連科目の「刑事訴訟法」「刑事司法と医療・心理・福祉の連携」(2026年度開講予定)を履修することで学びを深めることができます。

憲法人権論
日本国憲法の人権規定は、抽象的な文言で書かれているため、その内容を見極めるには「解釈」 が必要です。講義では、各人権内容に関する学説と重要判例に見られるさまざまな「解釈」を適切に理解することに重点を置きます。そして、日本国憲法の人権保障に関する基本的知識と判例法 理を理解し、これらをアウトプットすることを通じて、憲法的な思考力の基礎を修得することを到達点とします。

民法総則
民法は、私人間の権利義務関係について定めた法律で、総則、物権、債権、親族、相続の5編から成り立っています。その中でも民法総則は、主として物権や債権といった財産法に共通するルールを定めています。民法を学ぶうえで大切なことは、条文の背景にある制度趣旨を理解することです。条文の目的や趣旨を考えながら、何度か繰り返して学習していくうちに知識が定着していきます。
アジア平和創造コース
アジアの諸問題を解決するための探究心や構想力、実践力を養うためにアジア研究と公共経営という2つの視点から学びます。
コース概要
変動期に直面しているアジアの法と政治についての深い理解を通じ、「アジアの世紀」に活躍できる問題解決型の次世代リーダーを育成するためのコースです。「構造・主体」「歴史・思想」「政策・実践」の3つの観点を踏まえ、総合的に 基礎から応用まで学習できます。創価大学平和問題研究所(アジア平和・公共性研究センター)やアジア開発銀行(ADB)、他大学をはじめとした外部機関とも連携した研究・教育・実践融合型のプロジェクトも取り扱っています。

科目紹介
科目紹介

アジア公共経営特論
分断と停滞のアジアに対し、共生/協生を基本理念に据えた「アジアの世紀」をいかに構築すべきか。この問いに対し、法学・政治学を中心に、歴史学・社会学・経済学の知見も加味しつつ、学際性と総合性を同時に探究したオムニバス講座を、ユーラシア財団fromAsiaの助成を得て提供します。国内外の第一線の専門家を招致し、アジアの諸問題を解決するための構想力や実践力を養います。

アジア法
地理的に「アジア」はどこを指すのでしょうか。日本を含めた東アジアから西方にトルコあたりまでがアジアと呼ばれています。「アジア法」とは、この広大なアジア地域の各国の法制度と法文化の総体を指す言葉であり、アジアに共通する法ないし法律を意味するわけではありません。本講義の総論では、アジア法を学ぶための方法論と研究史を学びます。各論では個別の国ごとに、その文化と法制度について概観します。

アジア都市協力論
近年、都市や自治体、地域といったサブ・ナショナル(準国家)な単位の機能が強まりつつあります。通常の国家を超える規模で経済的・政治的・文化的影響力を持つグローバル都市が出現したほか、都市や自治体が国境を超えて課題解決のために連携・協力するようになっています。本講義では、こうした都市協力をめぐる理論と事例を学ぶとともに、横浜市や民間企業などの実務者を招いて現場の経験を学びます。