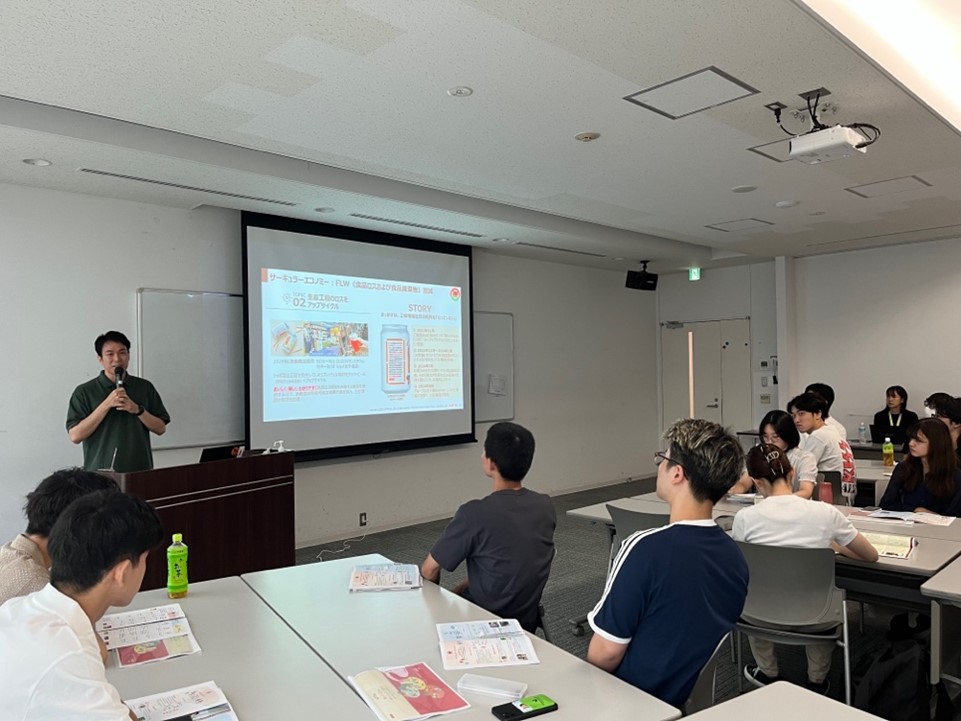SDGs達成に向けて実践する企業を訪問しました(経済学部 掛川ゼミ)

9月10日、掛川 ゼミの学生たちは、株式会社ロッテを訪問し、企業活動の中で「持続可能性」、「循環型経済」、「環境保全」が、どの様に実践されているのか、また、どの様に社会実装されているのかを、実務者の方々から説明を受ける中で、様々な視点や課題を学びました。
まず、株式会社ロッテ サステナビリティ推進部企画課長の飯田さんとスタッフの方々から、温かく丁寧な歓迎を受け、ロッテが目指すサステナビリティのビジョンと戦略である「ロッテ未来チャレンジ2048」について、心身の健康や、サーキュラーエコノミーを含む、非常に包括的な戦略の説明をしていただきました。また、2048年は、ロッテ創業100周年に当たるとのことで、敢えて国際的に広まっている「2050年カーボンユートラル」という目標ではなく、ロッテ独自の目標年を掲げ、脱炭素を目指しているとの話もありました。
また、ロッテとしては、サーキュラーエコノミーを実践していくために、お菓子を入れるプラスチックのトレーを薄くする縦線の本数を増やしたりなど、細かい部分においても工夫をし、プラスチック原料の削減に貢献してきたとのこと。また、持続可能で、責任あるサプライチェーンの構築のために、ガーナでのトレーサビリティが確立されたカカオ豆を「ロッテ サステナブル カカオ」(LSC)と名付け、その割合を拡大しているとのことで、2028年度までに、調達する全てのカカオ豆をLSCに切り替えるとのこと。特に、農園で働く児童がいないように、子供が学校に通うことの重要性を家族に説明したり、村の施設が未整備の場所では、学校建設や井戸の寄贈も行ってきていると、飯田さんは強調されました。さらには、カカオ農園が違法に拡大し、森林減少に繋がっていないかを確認するため、衛星画像やAIを用いてモニタリングも実施しているとのこと。この他には、心身の健康促進のために、「噛むこと」の普及を通してウエルビーングに貢献する市民向け講座を開いたり、また、会社内部では、多様性を尊重し、皆が働きやすい職場環境になるような工夫をしているなどの話がありました。
その後、発行されたばかりの『サステナビリティレポート2025』を読みつつ、同レポートの良い点や、改善した方が良い点について、グループごとに、学生のみんなで、自由な意見を出し合い、発表しました。飯田さんよりは、「学生の皆さんから頂いた意見やフィードバックは、来年度のレポート作成の際に参考にしていきたい」とのお言葉を頂きました。
最後に、全員で写真を撮り、企業訪問を終了しました。「お客様の選択が、しあわせな未来につながっていく」ことを担保する為の様々な工夫や取組みについて、大いに学んだ視察となりました。飯田さんをはじめ、ロッテの皆様、ご協力ありがとうございました。
参加した学生からは、以下の感想が寄せられました。
-
ロッテの新しいものを生み出すという挑戦意欲に感銘を受けました。普段、何気なく食べているロッテのお菓子の背景を知ることができ、企業の皆さんの努力を感じました。
-
「ロッテ ミライチャレンジ2048」の中で素晴らしいと思った活動は、インターナルカーボンプライシングの取組で、自主的にカーボンプライシングを導入し、CO2排出量を削減していく取組が素晴らしいと思いました。また、気候変動などの大きな問題に対しては、一企業だけでは解決できないので、様々なステークホルダーとのエンゲージメントを通し、相乗効果を生み出していく取組が、とても素晴らしいと思いました。
-
「ロッテサステナブルカカオ」(LSC)の取組が素晴らしいと感じ、私たち先進国が、開発途上国を支援できる良い取組だと思いました。
-
今回の企業訪問を通し、通常、消費者からは見えにくい取組を、多く知ることが出来ました。他の企業でも、サステナビリティについて、どのような取組を行なっているか、今後、調べていきたいと思います。
-
「ロッテミライチャレンジ2048」で、長期的な目標を、具体的な6つのマテリアリティに落とし込んでいるのが印象的でした。学生としても、食や環境が、どのように未来に繋がるのかを、あらためて考え直すきっかけになりました。
-
「脱炭素」の取組について、特に、CO2の排出量を減らしていく際の計画は、今後の社会変革や技術変革に期待することがあるものの、もっと積極的で具体的な排出削減の施策を掲げていけると良いのかと、更なる努力を期待しています。