2025年度学修支援だより
学修支援だより【2026年2月号】
学修支援だより【2026年2月号】
Foreword
成長を止めない力——シンガポールに学ぶ「更新」の習慣
国際教養学部長 杉本 一郎
限られた資源や多くの制約のなかで、なぜ小さな都市国家シンガポールは持続的に高い成長を続け、世界でも有数の豊かな国の一つとなったのでしょうか。
その答えの鍵は、「いま強い産業を守る」こと以上に、「次の成長の土台を更新し続ける」という姿勢にあります。港湾都市として外に開き、世界の変化を脅威ではなく機会として捉える。さらに、インフラ整備や透明で規律ある行政によって取引コストを下げ、企業が挑戦しやすい環境を積み重ねてきました。そして、労働集約から技術・知識集約へと産業の重心を移しながら、人材育成と制度の微調整を続け、外からの人・資本・技術を取り込んで競争力を更新してきたのです。
私は博士論文で、この成長の基礎が形づくられた英国植民地時代に遡り、制度と経済の長期的な変化を研究してきました。現在も、長年のシンガポールの友人であるチョイ・キンミン博士とともに『シンガポール経済史』の執筆に取り組んでいます。歴史を追えば追うほど、持続的成長とは“天才的な一手”ではなく、学び直しと改善を日常にしていく粘り強さだと実感します。うまくいかない局面があっても、原因を言葉にし、制度や方法をほんの少し変えて、また試す——その繰り返しが未来をつくっていくのです。
通信教育学部で学び続ける皆さんも、まさに同じ道を歩んでおられます。忙しさや家庭、仕事といった制約は簡単には消えません。それでも、今日の一ページ、今日の一問が、明日の自分の基盤を少しずつ更新していきます。大切なのは完璧さではなく継続です。「小さな実験→振り返り→次の一手」という学びの循環を持てたら、前進は必ず続きます。周囲と比べて焦る日があっても大丈夫です。自分のペースで、できる形で進めばよいのです。
変化を恐れず、学びを止めない限り、成長は続きます。一歩ずつ積み上げた知識と習慣は、ある日、仕事の判断や人との対話の場面で、確かな力として現れてくれます。どうか、ご自身の「更新」を信じて続けてください。その積み重ねこそが、皆さん一人ひとりの成長戦略になります。

教職指導講座
2026年度受験の教員採用試験に向けての具体的な取組
教職キャリアセンター 指導講師 橋本和男
2025年度の教採では、通信教育部および学部の教職課程の学生の皆さんの頑張りで「合格」という栄冠を数多く勝ち取ることができました。特に通教の皆さんは、日々働きながら時間を生み出し、教員免許状取得のための受講や教育実習の体験等に向かい、素晴らしい取組の姿でした。そして、さらに教員採用試験(以下「教採」と表記)への挑戦では、教員を目指しての必死な強い心を感じました。「教育」という子どもの可能性を引き出し伸ばすといった尊い仕事に携わりたいとの願いや思いに根差していました。
本稿では、新たに2026年度に実施される教採に向かわれる皆さんへ、その挑戦の意味や意義を知っていただき、また具体的な取組の方法について解説するために、次の三つの項目でお話ししたいと思います。1「教採の学びは何のために」、2「今後の教採の動向」、3「教採突破の攻略方法」、これからの皆さんの取組に一助となれば嬉しく思います。
1 教採の学びは何のために
まず、総論からお伝えすると、確かに教採は「合格する」ことが目標ですが、合格することが目的ではありません。この挑戦する学びを通して、学校という教育の現場で出会う子どもたちを育むことができる人材に成長することです。
筆記試験(1次試験)の出題内容を見ると「一般教養」「教職教養」「専門教養」が一般的です。改めて「教養」とはなんでしょう?辞書を調べると「教養とは、単なる知識の蓄積ではなく、学問・芸術・精神的修養を通じて得られる、物事に対する包括的な理解力、創造的な活力、心の豊かさ、人格的素養のこと。これらを身につけるプロセスや、人格の形成を意味すること。」とありました。すなわち、教員としての教養とは、全て教育活動を実践するにあたって必要な力を身に付けていくことです。
このように教育に関する「教養」は幅広く様々な領域に関わります。その中で軸となる教養とは何でしょう。それは端的に表現すると、自分自身の「人間教育観」を樹立していく努力を積み重ねていく態度と習慣化です。教採の学びは、その生涯にわたり学び続けていく始まりであり、きっかけです。子どもたちの前に立ち成長を図ることができる人の「資格」は、このように「人間教育とは?」との命題を希求する教員です。
この教養を身に付ける学びは、筆記試験の正しい回答に止まりません、その後の小論文の作文や個別の面談の際にも、自分の考えの根拠となり、表現力を高め説得力につながります。真に子どもの可能性を引き出し伸ばす人間教育の教員を目指していきましょう。
2 今後の教採の動向
今、採用試験のあり方が大きく変容しています。文部科学省の主導により「早期化」「複数回実施」「選考内容の柔軟化」がさらに加速化する見通しです。2027年度からは試験実施の標準日を定め、全国共通の共通試験問題と実施していくとの構想が進んできています。特に試験日の早期化について、文部科学省は、民間企業の採用活動に対抗するため、1次試験の標準実施日を大幅に早めるよう呼びかけています。昨年、2025年度では、実際に長崎県や茨城県など10自治体が5月中に一次試験を実施しました。
また、年間を通じて複数回の受験機会を設ける自治体が増えています。「秋選考」は北海道、滋賀県、神奈川県、川崎市で実施され、現職教員や社会人、また夏の不合格者を対象としています。さらに、社会人が受験しやすいように「SPI3」という適性検査を導入する自治体が増えています。
3 教採突破の攻略方法
①教員採用試験の実施要項を入手
前述のとおり採用試験の形式が毎年変化し続けています。まずは、志願先の自治体が公表する情報を正しく理解することから始めましょう。教採の「実施要項」は例年2月ごろから発出されます。その前に前年度(2025年度)の実施要項に目を通すことをお勧めします。インターネット検索で入手し、次の確認をします。
・一次試験・二次試験の実施日程および試験内容
・3年次受験、または前倒し受験の有無、また受験資格
・秋試験の実施の有無、また受験資格
・前年度からの変更点についての情報の入手と確認
また、教育委員会のHPをブックマークし、最新の情報に関心を持ち更新していくことが大切になってきます。さらに今後開催される「教員採用試験実施説明会」に参加していくこともお勧めします。
②「一次試験(筆記)」の攻略方法
受験する志願先によって「一般教養」「教職教養」「専門教養(小学校全科)(中・高教科専門)」の出題は異なっています。したがって出題内容を調べることは必須です。教採情報サイト(オススメ:教採ギルド)を利用し、一次試験の情報を入手します。
③受験地別の「過去問題」の分析・攻略方法
出題内容の傾向を調べるために「過去問題集」(オススメ:協同出版)を手に入れ、繰り返し問題を解いてみる。実際の筆記試験の解答はマークシート方式なので、知識を覚えて再生することではなく、意味の理解が進んでいるかが問われます。
4 おわりに
教職キャリセンターでは、「個別相談」「対策講座」等で、一次試験へのアドバイスに止まらず、二次試験に向けて「小論文」「個別面接」「模擬授業」の対策講座も開催しています。是非とも予約していただき、ご一緒に学びを進めていきましょう。

学修支援だより【2026年1月号】
学修支援だより【2026年1月号】
Foreword
学の光で人生、社会を照らしゆく、未来を創る挑戦者たちへ!
法学部長 朝賀 広伸
今、多忙な日々の中で、皆さんは「学び」という尊い挑戦を続けていることと思います。その努力は、生涯を通じて社会を変革し、価値を創造し続ける「力」を皆さんに授けてくれるはずです。
生涯学習という名の「自己投資」
「もう一度学びたい」-その想いを、大切にしてほしいと願っています。通信教育で学ぶということは、時間や場所に縛られず、自分の人生に主体性を取り戻す、「自己研鑽」であり「自己投資」です。仕事や生活を両立しながら専門知識を修得する中で培われる自律性と計画性は、卒業後も皆さんを支え続ける最強のスキルとなります。
孤独な学びではない! 生涯の「学友」という宝
皆さんは、決して一人ではありません。スクーリングや様々な交流の場で出会う学友たちは、年齢も職業も背景も異なる、多様な価値観の宝庫です。共に難解な法律を読み解き、社会問題について議論し、励まし合う経験は、単なる知識以上の深い人間的な絆を生み出してくれます。それは、皆さんが卒業した後も続く、最高の財産であり、生涯の応援団となるにちがいありません。
法律×政治×価値創造! 未来志向の学び
法学部は2026年度より「法律政治学科」へと進化し、学びの可能性が飛躍的に広がります!「リーガル」、「市民生活・ビジネス法」、「公共政策・行政」、「環境・サステナビリティ」、「国際平和・外交」など、時代の最先端をいく5つの専門コースで、あなたの関心をより深く追究することができるようになります。
法学部での学びは、法律条文の解釈や適用の仕方を身に付けるだけではありません。「民衆の側に立ち、正義を実現する」という建学の精神に基づき、法律の力と、社会を動かす政治・政策学の視点を統合して、問題の本質を捉え、具体的な解決策を導き出す「未来をデザインする思考力」を養います。
さらに、キャリアに直結するファイナンシャルプランナー技能士3級などの資格対策も充実しており、学んだ知識を実生活や仕事に活かすこともできます。皆さんの「学びたい」という情熱を、創価大学法学部で燃え上がらせてください。最高の仲間と出会い、世界を変える知識と哲学を身につける舞台が、あなたを待っています!
自立学習入門講座82
数字で企業を読み解く力を、基礎から実務へー株式会社簿記―
非常勤講師 土江 智佳子
現代社会における企業活動は、グローバル化やデジタル化の進展により、ますます複雑化しています。こうした環境の中で、経済活動を正しく理解し、体系的に記録・整理する力が求められています。その基盤となるのが簿記であり、簿記は会計学の根幹を成す学問領域です。
簿記を学ぶことによって、企業の財務状況を客観的に把握し、経営や投資に必要な判断材料を提供することが可能となります。
実際に、ある中小企業では、売上は順調にもかかわらず、資金繰りが厳しいという課題を抱えていました。簿記の知識を活用して財務諸表を分析した結果、売掛金の回収が遅れていることが原因と判明したため、取引条件を見直すことでキャッシュフローが改善し、経営の安定化につながりました。このように、簿記の知識は日々の業務や経営判断に直結する実践的な力となります。
さらに、簿記は経済学・経営学・金融学など関連分野の学びを支える基礎知識としても重要な役割を果たします。本講座で学ぶ意義は、経理・会計職に限らず、ビジネス全般において不可欠な「数字を読み解く力」を育み、学問的な体系を理解し、理論と実務を結びつける力を養うことにあります。
【株式会社簿記を学ぶ意義】
- 企業活動の記録と整理
複雑な経済活動を体系的に記録し、財務諸表を作成することで、会社の健全性や成長性を把握できます。 - 実務レベルの会計知識習得
簿記原理(日商簿記3級レベル)で学んだ基礎を土台に、より複雑な商取引や決算処理を理解し、会計基準に沿った実務的な処理能力を養います。 - 経営や投資に役立つ
経営者は会社の数字を正しく把握でき、投資家は企業の財務諸表を分析して投資判断に活かせます。
世界的な投資家ウォーレン・バフェットも会計の重要性を強調しています。 - キャリア形成への貢献
経理・会計職の理解が深まり、財務諸表を読む力が向上し、経営判断に必要な数字を理解できるようになります。 - 日常生活でも応用可能
家計簿や資産管理に簿記の考え方を取り入れると、無駄遣いを減らし、効率的にお金を管理することができます。
【学習効果(本授業で得られる力)】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 論理的思考力 | 仕訳や財務諸表を通じて、数字の因果関係を論理的に整理・分析する力 |
| 課題発見力 | 財務データから問題点や改善点を見出し、経営課題を抽出する力 |
| 計画力 | 決算処理や資金繰りを踏まえ、将来の経営戦略や行動計画を立案する力 |
| 実行力 | 簿記の知識を実際のビジネスに応用する力 |
| 発信力 | 財務情報をもとに、わかりやすく説明・報告する力 |
【学習スタイル】
・オンデマンドスクーリング
オンデマンド動画を繰り返し視聴できるため、理解を深めやすい構成となっています。なお、本科目「株式会社簿記」のオンデマンド動画の映像は、2023年に収録された講義(教科書:2023年度版使用)です。
・反復学習
株式会社の多様な取引を具体的にイメージしながら学ぶことで、理論と実務を結びつけられます。具体的な学習方法は、学習指導書をご参照ください。
【 キャリアと実務に直結する学びを】
本授業は、簿記の基礎から株式会社特有の会計処理までを体系的に学び、ビジネスに不可欠な「数字を読み解く力」を実践的に身につけることを目的としています。オンデマンドスクーリングによる柔軟な学習環境のもと、学生一人ひとりが自分のペースで理解を深め、将来のキャリア形成はもちろん、現在の業務に直結する実務力の強化にもつながります。
学習支援推進室コーナー
レポート作成講義【Bタイプ】を担当して
通信教育部准教授 清水 強志
今年度は、レポート作成講義のBタイプを2回、数年ぶりに担当させていただきました。本稿では、「アウトライン」を作成する大切さに絞り、講義内容を振り返りながら簡潔に報告させていただきます。
アウトラインを描く際に重要なこと、それは下書きをする前に「アウトライン」を作成しなければならないということです。また、「アウトライン」を考える前に、「結論」を決めておかなければならないということです。
通教のレポートでは、テキストを熟読し、課題に答えるために必要な情報を整理し終えたからと言って、すぐに「下書き」を書き始めてはいけません。つまり、「下書き」を書く前にじっくりと時間をかけてあることをしなければならないのです。そう、それが「アウトライン」の作成ということになります。アウトラインを十分に考え、明確にしてから下書きを描くことが、結果として、効率的かつ論理的にレポートを書くことにつながります。一見、アウトラインを丁寧に描くことは余計な手間暇(遠回り)と感じるかもしれませんが、「急がば回れ」なのです。
ところで、アウトラインとはどのようなものと考えていますか? 直訳すると、「外側の線」ということになり、何となくわかりそうですが、実は曖昧な方は少なくないのではないでしょうか。「デジタル大辞泉」によれば、アウトライン(outline)とは、「1 輪郭。外郭。2 あらまし。大要。3 テニスで、コートの外周の線」とあります。実は、「外側の輪郭」というのは、花や葉などの物理的なものに使います。一方、レポートでは、「あらまし、概要」というのが近いのですが、やや正確さに欠けていると考えています。また、「設計図」という説明も多く見かけますが、やや説明が足りていないように思います。誤解を恐れず述べれば、「まず、〇〇について書き、次に□□について、・・・、それゆえに、××と結論付けられる」という、「目次」に似た、全体の流れを示す設計図のようなものなのです。そして、一度描いて終わりというものではなく、何度も何度も練り直し、描き直すことが大切なのです。
通教では、「落書きアウトライン」や「付箋」を利用した方法などを紹介していますが、その方法は多様です。卒業までにさまざまな方法を試し、自分に合った「設計図」の描き方を探されるとよいと思います。私が本講義のなかで紹介した方法は、A3用紙などを利用して、取り上げるべき(あるいは、取り上げたい)項目をあえて紙面全体に散らばらせて(箇条書きにしないで)書き出した上で、情報を整理しつつ、何度も流れを検討し直すという方法です。そして、それらを別の用紙に改めて何度か書き直しながら、「設計図」を完成させるというものです。実際、この方法は、情報の整理にも役立つので、情報整理とアウトラインの作成を同時に行いたいという方もいるかもしれませんが、それは絶対にしないで下さい。アウトラインを描く前にレポート課題の問いに対応した結論を必ず明確にしておかなければならないという原則があるからです。
「結論が決まらないので、あとで決めても良いか?」という質問がありましたが、もちろん、「NO!」です。結論が決まらないと、必要な内容も並べ方も決められないのです。別言すれば、アウトラインを描く際には、結論から逆算して考えることも重要なのです。もし、結論が決まらないという場合には、まずは暫定的な結論を決めてからアウトラインを描き、アウトラインを考えているうちに結論が変わってしまったら、新しい用紙をつかって、新しい結論をもとにアウトラインを描き直せばいいのです。何度でも描き直すことが大切なのです。
ぜひ、完成度の高いアウトラインを描いてから下書きを書いてみて下さい。
参考文献
「コトバンク」https://kotobank.jp/
創価大学通信教育部、デジタル副教材「自立学習入門講座6」

学修支援だより【2025年12月号】
学修支援だより【2025年12月号】
Foreword
〈心に思索の灯を〉
図書館長・文学部教授 伊藤貴雄
冬になると、不思議と本が読みたくなります。
外の風は冷たくとも、ページを開けば、そこにはいつでも誰かの声があり、思索の灯がともっています。静かな時間にこそ、本との出会いは深まるのかもしれません。
古今東西の哲学書や文学の名著は、遠い過去の言葉のようでいて、私たち一人ひとりの心に問いを投げかけてきます。
「生きるとは何か」「正しさとは何か」「幸福とはどんな状態か」――そうした問いは、実は思春期からすでに始まっているものです。
学問とは、その問いを生涯かけて育てていく営みにほかなりません。
20世紀前半のドイツを代表する作家ヘルマン・ヘッセもまた、働きながら本を読み、詩を書き続けた人でした。
ギムナージゥム(中等学校)を中退した彼は、書店での仕事の合間に、片隅で文豪たちの作品を読みふけり、自分の内なる声を育てていきました。
やがてその「仕事と読書の往復」こそが、創作の原点となり、『車輪の下』や『シッダールタ』といった作品を生み出す力になったのです。
限られた時間の中で読む一冊が、やがて人生を形づくる――そのことを彼の生き方は静かに教えてくれます。
通信教育で学ぶ皆さんも、仕事や家庭の時間の合間に静かに本を開くことで、自分だけの“知の旅”を歩んでおられることでしょう。
どんなに忙しくとも、ほんの数行の読書が心を澄ませ、新しい発見を運んでくれます。
本は、時を超えて私たちを励まし、勇気づける最良の友人です。
このたび、Web第三文明にて新連載「哲学は中学からはじまる――古今東西を旅する世界の名著ガイド」(福谷茂 × 伊藤貴雄)を始めました。
一冊の本を通して、時代や文化の垣根を越え、哲学や芸術の魅力を語り合う対談です。
学生・社会人を問わず、「思索の喜び」をもう一度味わうきっかけとなれば幸いです。
どうかこの冬も、一冊の本とともに、心の灯を絶やさず歩んでください。
ページの向こうに、きっと新しい世界が待っています。
教職指導講座
特別支援教育の推進のために、教師に求められていること
教職キャリアセンター指導講師 清水 和彦
「特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです」と文部科学省においては定義付けられています。
2007年4月からは、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、特別支援学校に限らず、全ての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実することになりました。それから、20年近くになろうとしていますが、私が巡回心理士として保育園、幼稚園、小学校、中学校を訪問して感じることは、「遅々として進まず、課題多し」というのが率直な感想です。私見ではありますが、現在感じている課題について以下述べてみたいと思います。
① 接続での課題
進学時には、指導要録の抄本等を進学先に送られるのですが、確認されていないケースが多くあるようです。よって、スタート時の配慮がなされず、スタート時からつまずきが発生して、いろいろな不適応反応が出てきてしまうことが多くある気がしています。抄本の取り扱いやその内容を活かした「学校生活支援シート」等を作成して、組織として情報共有と支援の共同実践が望まれると思います。
② 人的配置の不足
支援が必要とされる子どもたちは、集団への適応が上手くいかない場合は、回避することは自然です。結果として、小人数対応の場や具体的支援を求められます。例えば、各学校には、空き教室を活用した不登校状態の児童生徒ための教室が用意されています。しかし、その教室には専任の支援スキルがある人が配置されていることは稀です。現在、正規職員の欠員も多くいる小学校や中学校では厳しい現実があるのかもしれません。
③ 支援スキルの不足
現場の教員の支援スキルの不足を感じます。仕事量が多いと言われている教師において、特別支援教育等の実践研修会に参加することは難しいのかもしれません。そもそも、特別支援教育の実践的な研修会が少ないという現実もあります。また、大学においても、特別支援教育の実践的な授業が少ないのも事実です。もっとも、児童生徒の特性は個々によって違います。その多様性に対して、適格な支援方法を研修や授業で身に着けることは至難の技と言えるかもしれません。
④ 合意形成に基づく合理的配慮の実施の少なさ
学年が進むにつれ、療育の効果も期待できなくなり、学力の低下も顕著になっていく場合も少なくありません。よって、自己肯定感も低下して、集団不適応をおこして不登校状態に至ることも少なくありません。そのようなことになることを防ぐためにも、合意形成に基づく合理的配慮なより、できることを増やすことは必要となってきます。しかし、合意形成に基づく合理的配慮は、保護者や本人の意思が尊重されないと効果は望めません。また、多くの場合、クラスメートの理解や協力が必要です。そのような環境が構築されていない場合、いざ実施となると「他の人に特別視されるのではないか」とか、「いじめのターゲットにされるのではないか」等々、不安になり躊躇されということもよく耳にします。よって、近視の人が眼鏡を活用するように、違和感なく、且つ当たり前のように合理的配慮が認知され、実施される社会を構築していかなければいけません。その構築の最前線が、学校現場だと私は思っています。
上記の課題のほとんどが一教師の努力によって解決できるものではないと思います。しかし、「子どものために、全力で」という強い信念と特別支援教育に関する確かなスキルに基づく実践意欲と実践力のある教師が一人でも増えていくことが解決に向かう一歩であることも事実です。その力を培うために、授業内容をしっかり学ぶことは当然として、できる限り学校サポーターや学校インターン制度を活用したり、ボランティアとして学校に赴いたりして、特別支援教育に関する理論と実践の往還を図っていってほしいと考えます。
そのようにして培われた力こそ、真の教師力の基盤となり得ると私は考えています。
オンデマンドスクーリングだより
憲法総論・統治機構論
法科大学院准教授 神尾 将紀
現在、本科目「憲法総論・統治機構論」のオンデマンドスクーリングの映像は、2018年に収録されたもので、藤田尚則先生(元創価大学法科大学院教授/創大1期生)の講義となっています(なお、その後の法改正や、改訂された教科書の該当ページについては、映像の中にテロップが入れられているかと思います)。2020年に、本科目を長年にわたり担当されていた藤田先生が逝去されたため、2023年度より、私が微力ながらも、本科目を担当しています。
本科目の教科書も、花見常幸先生(元創価大学法学部教授/創大1期生)と藤田先生の共著『憲法』(第3版、北樹出版、2022年)となっています。また、本科目の小テストも、教科書およびオンデマンドスクーリングの講義に即して、藤田先生が作成された(と伺っている)ものを(受講生の方々からのご指摘を受けて)部分的に修正しながら、そのまま使用しています。そして、レポート課題やオンデマンド試験などについても、藤田先生による過去の出題を踏まえ、本科目の教科書から出題しています。
一般に、大学での「憲法」の講義は、㋑総論(基礎分野)、㋺人権論(人権分野)、㋩統治機構論(政治分野)に大別されますが、そのうち、本科目は、㋑総論と㋩統治機構論を扱っています(もっとも、関連する限りで、㋺人権論について触れている部分もあります)。この点、日本国憲法については、小学校から高校までの間に、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大基本原理を学習することから、親しみのあるものだと思います。しかしながら、大学での「憲法」の授業は、より深く詳しく、日本国憲法に関する学説(憲法学者の見解)および判例(裁判所の判決)、ならびに、関連法令を専門的に学問するものです。それゆえ、ときどき受講生の方々から、本科目のオンデマンドスクーリングの講義や小テストが難しい、といった声を聴きますが、それも仕方がありません。私自身も、創大24期生(法学部・藤田ゼミ1期生)として、花見先生と藤田先生の「憲法」の授業を受講していますが、当時は、大変難しく感じました。その一方で、オンデマンドスクーリングでの藤田先生の迫力ある講義を受講し、感銘を受けたという受講生の方々の声も聴きます。
また、ご存じの通り、日本国憲法は、施行後80年近くになっても、まだ一度も改正されていませんが(その賛否はともかく)、最近ますます、新しい重要な判例(ただし、その多くは、人権論に関する判例です)が出てきていることから、近い将来(なおも私が本科目の担当者であればの話)、オンデマンドスクーリングの映像も(それに伴って、教科書や小テストも)全面的に作り直さないといけないと思っています。そうはいうものの、私事で大変恐縮ですが、本務の法科大学院での教育・研究との兼ね合いから、なかなか時間が取れず、もうあと数年間は、私の恩師・藤田先生のお力をお借りしたいと思っています。
さて、オンデマンドスクーリングの講義は、教科書に沿って行われていますので、オンデマンドスクーリングでの学修にあたっては、月並みですが、まずは教科書(の該当箇所)をよく読んで予習と復習をしっかり行うことが肝要だと思います。また、オンデマンドスクーリングの講義や教科書の中で分からない言葉が出てきたら、その都度、きちんと調べて理解していくことが重要となります。これは、「憲法」に限らず、法律科目全般に共通する学習の基本になります。国語辞典や百科事典のほか、定評のある法律辞典として、『有斐閣法律用語辞典』(第5版、有斐閣、2020年)と『法律学小辞典』(第6版、有斐閣、2025年)を挙げておきます。
小テストの正解は、オンデマンドスクーリングの講義の中か、教科書の中か、いずれかに必ずありますので、少し難しい問題もありますが、よく探してください。
課題レポートの作成にあたっては、「課題解説」に明記してある通り、原則として、教科書の(丸写しではなく)内容をまとめてください(報告型のレポートです)。教科書の内容をまとめることだけでも、十分な学習効果があります。それだけでは足りないという場合に限り、シラバスに掲示してある参考書も参照・引用してください。これら以外の教材や、インターネット上の情報は、あくまでも教科書の内容を理解するための補助的な手段にとどめてください。もちろん、インターネットを活用したAIによるレポートの作成は、論外です。
オンデマンド試験についても、教科書の(丸写しではなく)内容を適切にまとめていれば、「A」評価となります。要するに、本科目のレポートや試験は、みなさんの私見を尋ねているのではなく、日本国憲法に関する学説および/または判例の知識を問うているのです。
なお、大学(高等教育の段階)では、しばしば各担当教員により教育の指導方針が異なるので、他の科目については、その担当教員の指示に従ってください。
最後に、学問・教育の根本は、やはり人的交流ですので、みなさんのライフスタイルから困難な場合もあるかとは思いますが、無理のない範囲で、①対面スクーリング(夏期)>②リアルタイムスクーリング(秋期)>③オンデマンドスクーリング(年4期)>④テキスト学習という優先順位で、学修方法を選択していただければ、幸いです(①と②のスクーリングは、私自身が担当しています)。

ブック・スクウェア
『スマホ時代の哲学』―「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険-
通信教育部教授 劉 継生
現在の高度情報化社会において、スマートフォン(以下、スマホ)は必要不可欠な情報端末として急速に普及しています。日常生活の中で、スマホは仕事や勉強、コミュニケーション、ネットショッピング、電子決済、娯楽などの目的で、子供から高齢者まで様々な人々に利用されています。これはスマホが私たちに多くの恩恵をもたらすことができるからです。例えば、スマホを使用することで、いつでもどこでもインターネットにアクセスできるようになり、膨大な情報資源であるインターネットは水や空気のように私たちの身近な存在となっています。
スマホを手放さずに生活する現代人のライフスタイルについて、本書は次のように述べています。スマホは、一日の間に時間が許す限り何度でも使用され、始まりも終わりも意識されることがありません。車での移動や電車通勤の際、食事中、さらには寝起きの布団の中でもスマホが利用されています。スマホがこれほどまでに現代人と密接に結びつくようになったのは、人々の「つながりたい」「退屈を解消したい」「刺激を求めたい」といったニーズに応えているからです。また、誰かと対面で会話をする際に、スマホの新着情報を確認したり返信を行ったりするために会話が一時中断されることがしばしばあります。これは、スマホの向こう側とのやり取りを優先していることを示しています。信号待ちやスーパーのレジでの待機、会場に座っているときに、興味を引くものがなくて退屈を感じると、人々はスマホを取り出し、SNSを開いたり、誰かにメッセージを送ったり、動画や記事をシェアしたりします。つまり、自分の身体は物理的に特定の場所に存在していても、自分の意識はスマホを通じて別の場所(サイバー空間)に飛び込み、両者が空間的に分離している状態です。
スマホの使用が増加している背景には、心理的な要因が存在します。本書では、ストレスを軽減するための手段としてこの点が指摘されています。「VUCA」(ブッカ:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の4つの単語の頭文字)と呼ばれる不確実な社会を生き抜くためには、常に変化を求められ、自己を絶えず向上させながら、不安定な状況を克服する必要があります。このような精神的な不安定さや苦労から生じるストレスに対処する方法として、本書は注意を細分化し「快楽的なダルさ」に浸る手法を提案しています。具体的には、スマホを通じて無料の娯楽にアクセスし、そこから得られる断片的な感覚刺激で自分を取り囲み、注意を分散させることです。要するに、スマホを利用して自分の注意を緩め、緊張した感覚を分解し、そこから生じるぼんやりとした感覚に一種の癒しが存在するのです。
一方、快楽的なダルさに浸る方法には副作用が存在します。TikTokでショート動画に触れたり、YouTubeで様々なコンテンツを視聴したり、SNSでメッセージを交換したりすることから、様々な感覚刺激やコミュニケーションが確かに得られます。しかし、スマホの世界から切り離された瞬間、退屈や虚無感に陥ることになります。また、指先のタップで画面を次々と切り替えることにより、アクセスした大量の情報を消化しきれず、すぐに解釈できない謎として残り、釈然としないモヤモヤが生じます。さらに、退屈や不安を「つながり」や「シェア」で埋めることで、自分の意識があちこちに飛び散り、注意が寸断されてしまいます。このような思考パターンが習慣化すると、一つのことに没頭して懸命に取り組む集中力が失われます。
退屈やモヤモヤ、注意の散乱といった問題は、実際には自分自身と向き合うことができないために生じています。その原因は「常時接続の世界」で孤独が失われたことにあると本書に指摘されています。不安や退屈に耐えられず、何らかの感覚刺激やコミュニケーションを求めてスマホを過度に利用する生活に慣れると、自分自身と過ごすための時間的余裕がなくなります。実際、失った自分を取り戻すためには、自分が一人にいる孤独の時間が必要です。孤独とは、心が静まり、自分と向き合い、自分自身と対話している状態を指します。しかし、孤独の確保はスマホを使えば使うほど困難になります。本書は、スマホ時代において孤独がますます重要であると考え、それを確保する手段として「趣味」に取り組むことを提案しています。何かを作り、何かを育てるという趣味的な活動は、スマホから一時的に切り離されることを自発的に可能にします。
私たちは毎日、朝から晩まで始まりも終わりも意識せずにスマホを使用しています。このような行動がもたらす新たなライフスタイルについて、様々な視点から考察することが可能です。本書は、哲学的な視点から、スマホが手放せないという前提のもと、過剰な感覚刺激やコミュニケーションが引き起こす問題、失われた孤独を取り戻す方法などについて詳しく述べています。スマホの利用時間が増加していることに悩む私たちにとって、本書は読む価値があると考えられます。
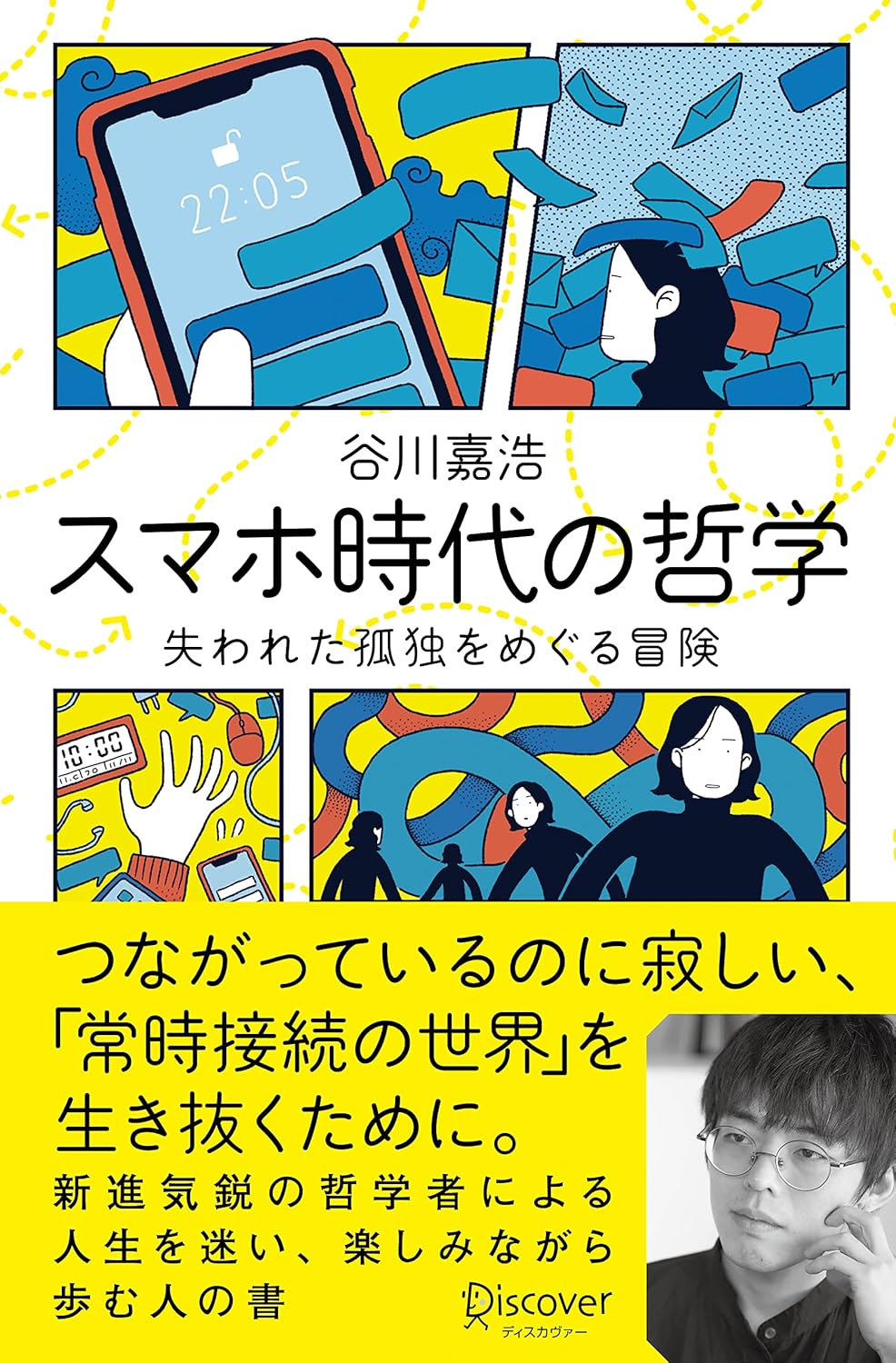
学修支援だより【2025年11月号】
学修支援だより【2025年11月号】
Foreword
創価大学理工学部の新たな挑戦
理工学部長 黒沢 則夫
創価大学理工学部の新たな挑戦
創価大学理工学部は、2026年度より「グリーンテクノロジー学科」と「生命理工学科」という二つの新学科を設立し、「情報システム工学科」を含めて三学科体制となります。通信教育部で日々研鑽に励む全国の学友の皆さまに、新学科が目指す未来についてご紹介させていただきます。
新学科設立の背景
創価大学理工学部は、これまで情報システム工学科と共生創造理工学科の二学科体制のもと、教育研究を推進してまいりました 。共生創造理工学科においては、この10年間で、地球環境問題への取り組みとなるマレーシアやアフリカとの共同研究の始動 、ならびに生命科学分野における日本を代表する「糖鎖研究拠点」の創設 という、目覚ましい発展を遂げてきました。地球環境問題と最先端の生命科学という現代社会が直面する二大テーマは、それぞれが極めて専門性が高い分野です 。一つの学科で深く探究するには限界があるため、それぞれの専門性を高め、時代の要請に応える人材を育成すべく、二つの学科に分化・新設するという決断に至りました 。
1. グリーンテクノロジー学科:地球の未来を守る技術と知恵
グリーンテクノロジー学科では、「環境にやさしい工学」を柱に、地球環境問題の解決に焦点を当てた教育研究を行います 。再生可能エネルギーや資源循環技術を研究することで、地球が未来にわたって存続できるための基盤を築きます 。また、環境ビジネスや国際法といった分野をカリキュラムに加え、開発した優れた技術を「社会にどう応用し世界へ広げていくか」という、技術を社会実装する力を養います 。これらの教育・研究は、「地球社会の平和と持続可能性」という創立者の思想の実践に他なりません。
2. 生命理工学科:一人ひとりの幸福を追求する次世代生命科学の担い手
生命理工学科は、生命・医療・福祉・健康の四分野を横断的に学びます。現代の医療現場で不可欠な医療機器は、医学ではなく理学・工学の専門家によって開発されており、本学科はこの「医理工連携」を強みとします 。遺伝子治療や再生医療、創薬技術などの研究は、難病に苦しむ人々を救うだけでなく、生活の質を高めることに繋がり、これは「生命の尊厳」と「人間一人ひとりの幸福」という創立者の理念を科学的に探求するものです 。
この新たな挑戦が、持続可能な社会の実現と、一人ひとりの生命が輝く未来を築く礎となることを確信しています。通信教育部の学友の皆さまが日々深めている学問への探究心と人間主義の精神が、新学科の目指す未来とも響き合い、私たちが共に人類の幸福に貢献していけるよう、心からご期待申し上げます。

教職指導講座
今年度の教員採用試験に向けた相談を振り返って
教職キャリアセンター指導講師 杉本 信代
この夏、教員採用試験に多くの方々が果敢に挑戦されました。それに向けた論文・面接対策講座や相談活動を通して感じたことを整理して振り返ってみたいと思います。
論文対策 書くことに苦手意識がある場合、どうしたらよいでしょうか。
そもそも、文章を書くことが得意な人はそんなに多くはいないと思います。私も得意ではありません。校長論文など書かねばならない機会には、いつも逃げ出したい気持ちになりました。そこで、以下、自分なりに身に付けた方法です。参考にしてください。
1.読書の習慣をつける。
2.好きな文章を見つける。
3.その文章を自分のノートに書き写してみる。
→ 日常的に「読んで 書く」ことを積み重ねていきましょう。
4.各行政の過去問の課題をテーマにして、まず書いてみる。
→基本的な様式や、文章構成(序論・本論・結論)の書き方が身に付いているか、日常の学びの質が問われます。
5.自分が書いた文章を他人に読んでもらい、率直に感想を聞く。
→言いたいことが伝わるかどうかを試してみましょう。
6.課題のテーマに正対しているか(課題をよく理解した上で書いているか)を前提に自分が書いた論文を何度も読んで推敲していく。
7.本番は、鉛筆を使って自分の字で書くので、原稿用紙に、直接書く練習をする。
8.最後は、決められた時間制限を設けて書いてみる。
小論文の問題は、基本的に今日的な教育課題に関するものです。それらの課題に対する教育行政の考え方の理解度が問われます。下記に挙げた東京都の評価の観点にあるように、その理解度は、単に学習指導要領解説などの行政の資料を述べるだけでなく、回答者が具体的に展開できているかどうかが重要です。教職課程全体の学びの質が問われるものです。過去問を踏まえて学習指導要領解説総則編や生徒指導提要から関連する箇所を適宜要約引用し、それを具体的に教室でどのように実践するかを考えてみましょう。現時点では、何かしら子どもとかかわる経験を積んでおくように努めてみてください。
参考に、以下は今年度(2025)の東京都教員採用試験の場合を示します。
- 試験時間 70分
- 文字数 910~1050字
- 問題数 1題
- 評価の観点 課題把握力 教師としての実践的指導力 論理的表現力 文章構成力 国語力
問題
各学校では、児童・生徒が互いのよさを見付け、多様な考えを尊重し合うことができるよう、教育の充実を図っています。
(1) 児童・生徒が互いのよさを見付け、多様な考えを尊重し合うことについて、あなたの考えを、理由を明確にして述べなさい。
(2) (1)の考えを踏まえ、あなたは教師としてどのように取り組んでいくか、志望する校種と教科等に即して述べなさい。
面接試験対策 人前で話すことが苦手な場合、どうしたらよいでしょうか。
面接という場の緊張感を想像して、こうした相談を受けることが少なくありません。自信をもって、落ち着いて相手が何を聞いているのかを適切に把握できれば、面接試験をクリアしていけるでしょう。そのための基本的な取組を以下に示します。
1.まず、どうして教師を目指しているのか、じっくり考える。そして、そのことを人に話してみる。
2.次に、もし教師になれたら『どんな子どもたちを育てたいのか』自分の言葉で語ってみる。
上手く表現できない時は、文科省や、各行政の教育委員会が示している施策を改めて読んで勉強する。
3.これまでの自分の経験に中で、頑張って取り組んできたことを思い出し、文章にしてまとめてみる。
⇒ 自分の良いところを認識すると、自信が湧き、気持ちが落ち着きます。
4.日頃の会話の中で、聞かれたことに対して、始めに結論を述べるよう意識して話すようにする。その後に、その根拠や理由を述べる習慣を身に付ける。
⇒ 質問に正対してください。どんなに深い考えでも、聞かれていないことを話すと質問に対する理解力がないと取られる場合があります。
5.教育実習の経験をした後は、その振り返りをノート等にまとめておき、聞かれた時に慌てずに話せるよう準備をしておく。
参考に、今年の東京都の面接試験で質問された内容の一部を紹介します。
Q 子供たちを自主的な学びへと向かわせるためには、何が大切だと思いますか?
Q 保護者から、「先生の授業がつまらないと子供が言っています。どうにかなりませんか?」と言われたら、あなたはどうしますか?
Q どのような学級を作りたいですか?
そういう学級にするためにあなたはどのような取組をしますか?
Q クラスに不登校の子がいるとします。あなたはどう対応しますか?
Q ある生徒が相談したいことがあるので、先生のLINEのIDを教えてくれませんかと言ってきました。あなたはどう対応しますか?
Q 「チーム学校」との言葉があるように、教職員皆で力を合わせて取り組んでいきますが、あなたはチームの一員として大事なことはどんなことだと考えますか?
Q 精神的に落ち込むようなことがあった時、どうしますか?
気分転換する方法などを持ち合わせていますか?
何か落ち込んだ時に、乗り越えた経験などありますか?
上記は、あくまでも対話的な面接の中での質問です。
2~3人の面接員とのやり取りの中では、スムーズに応えられる時もあれば、思わず口ごもってしまうこともあります。上手く応えられなかった時は、自分の中で仕切り直しをして、次の質問には改めて誠実に応えていけば大丈夫です。そのへこたれない様子を面接員は評価してくれます。
試験には合否があります。残念なことに不合格の結果であっても、教員採用試験は毎年あります。試験に取り組む中で、自身の知性も精神も大いに鍛えられると思いますので、諦めずに挑戦していって欲しいと願っています。日常生活の中で、働きながら学ぶことは大変なことですが、苦労こそが人格を磨く宝となります。創立者より頂いた創価大学の指針の一つである「労苦と使命の中にのみ 人生の価値(たから)は生まれる」の言葉は、通教生の皆さんの生き方そのものです。私達指導講師も、教採対策講座等を通して皆さんを応援していますので、どうぞ大いに活用してください。
最後に、創立者池田大作先生の言葉を紹介します。
「 自分らしく 誠実に 」
君は君 あなたはあなた 同じようにはできない
よきことは学び どこまでも自分らしく
誠実に ベストを尽くしていけばよいのだ。

学修支援推進室コーナー
レポート作成講義【Aタイプ】を担当して
通信教育部講師 黄 國光
1. レポートの質は「戦略的な読書術」で決まる
質の高いレポートを作成する上で最も重要な鍵は、参考文献を深く的確に理解するための戦略的な「読書術」にあります。優れたレポートとは、単に情報を並べたものではなく、文献の深い読解から得た知見を基に、書き手自身の論理的な考察を展開したものです。しかし、多くの通教生は「どこから読めばいいのか」「重要なポイントが分からない」「読んだ内容をどう活かせばいいのか」といった悩みに直面します。特に、限られた時間で効率的に学習を進める必要のある通信教育で学ぶ皆さんにとって、効果的な読書術の習得は不可欠です。本稿では、レポートの質と効率を飛躍的に向上させる強力な武器として、まず森の全体像を捉え、次に個々の木々に注目するような「トップダウン的な読書術」を提案し、その具体的な技術を解説していきます。
2. 「トップダウン的な読書術」が効率的な読解を可能にする
「トップダウン的な読書術」とは、まず文章の全体構造や骨格を最初に把握し、その後に細部を深く理解していく効率的な読書法です。これは、初めて訪れる街で、まず地図を手に入れて全体の位置関係を把握してから目的地へ向かうアプローチに似ています。はじめに目次や見出しに目を通すことで、文献がどのようなテーマをどのような順序で論じているのか、大まかな「知の地図」を頭の中に描くことができます。この地図を持つことには二つの大きな利点があります。第一に、レポートの目的にとって重要な部分を見極め、読む力の配分を戦略的に調整できることです。第二に、主要な概念とそれを支える具体例やデータとの関係性、つまり情報の階層構造を意識しながら読み進められるため、内容の理解度が格段に深まります。この方法は、やみくもに一行ずつ読み進めるよりも、はるかに効率的かつ効果的に、著者の論理の全体像を的確に捉えることを可能にするのです。
3. 「通読」:森の全体像を把握する技術
読書の第一段階である「通読」の目的は、細部にはこだわらず、文献の全体像と論理の流れを掴むことにあります。この段階では、個々の木々(細かな情報)を記憶するのではなく、森全体(文献の構造と主題)の姿を捉えることを目指します。
本格的に読み始める前には、まず以下の「プレビューイング(下読み)」を行いましょう。
- 著者と時代背景の確認: 著者の専門分野や所属、文献が書かれた時代背景を数分で調べておくと、内容を理解する上でのヒントになります。
- 目次の熟読: 目次をじっくりと眺め、全体の構成を頭に入れます。
- 序論と結論の確認: 「まえがき」や「はじめに」で著者の問題意識や目的を、「あとがき」や「結論」で最終的な主張を確認します。
本文を読み進める際は、見出し、太字、図表などに注目し、各章・各節の導入と結論部分を意識して読むと効果的です。途中で理解が難しい部分があっても立ち止まらず、付箋を貼るなど印をつけるに留め、まずは一定のペースで最後まで読み通すことに集中してください。この通読を経ることで、著者の中心的な主張は何か、どの章が議論の核心か、といった文献の骨格が見えてくるはずです。
4. 「精読」:木々を詳細に分析する技術
レポートの質に直結する第二段階が「精読」であり、通読で見定めた重要箇所を、批判的な視点を持って深く分析的に読み解く作業です。精読では、単に書かれている内容を受動的に受け入れるのではなく、著者と対話するように能動的に読み進めることが求められます。常に「この主張の根拠は妥当か」「提示されているデータは信頼できるか」「結論に至る論理に飛躍はないか」といった問いを自身に投げかけながら、テキストを吟味してください。特に学術的な文章は、「主張」「理由」「根拠(データや事実)」という3つの要素で構成されていることが多いため、それぞれの繋がりを意識することが重要です。曖昧な専門用語は辞書等で正確に理解し、文章を引用する際は、その部分が著者全体の主張の中でどのような役割を持つのか、前後の文脈を十分に考慮する必要があります。精読した内容が本当に自分のものになったかを確認するために、その部分を自分の言葉で要約したり、図で構造を整理したりするアウトプット作業も非常に有効です。
5. 読書と執筆を繋ぐ「情報カード」の活用
読書で得た知見をレポート作成に効果的に繋ぐためには、読書と執筆の橋渡しとなる「情報カード」の作成が不可欠です。文献の重要なポイントや自分の考えを自分の言葉でまとめ、引用したい箇所はページ番号と共に正確に書き留めておきましょう。この一手間が、後の執筆作業を格段に効率化します。さらに、複数の文献を読むことで、テーマに対する理解はより多角的になります。それぞれの文献の共通点や相違点を整理し、なぜ見解が異なるのかを比較検討する中で、あなた自身の独自の視点が育まれます。最終的には、これらの知識や分析を、レポート全体の論理構成の中に的確に配置していくのです。その際、他者の主張である引用と、それに対する自分の分析や考察を明確に区別し、両者のバランスを取りながら説得力のある論述を組み立てていきましょう。
6. 戦略的読書術は一生の知的財産となる
本稿で紹介した戦略的な読書術は、単に文字を追う受動的な作業ではなく、目的意識を持った能動的な知的活動です。まず「通読」で全体像を掴み、次に「精読」で重要箇所を深く分析し、その過程を「情報カード」に記録するという一連の技術は、質の高いレポートを作成するための確かな土台となります。さらに、複数文献の比較検討を通じて、他者の見解を尊重しつつも自分自身の独自の視点を育て、説得力のある論述を組み立てる力が養われるのです。この読書法は、通信教育で学ぶ皆さんが直面する「時間的制約」と「学習効果の最大化」という課題を解決する、非常に実践的な方法です。最初は少し手間がかかるように感じるかもしれませんが、継続することで必ず習得できる一生ものの技術です。優れた読書スキルは、レポートという当面の課題を乗り越えるだけでなく、皆さんの生涯にわたる学習の基盤となる、貴重な財産となるでしょう。
【推薦図書】
1. J・モーティマー・アドラー、V・チャールズ・ドーレン(著)、外山滋比古・槇未知子(翻訳) 『本を読む本』講談社学術文庫、1997年
2. 梅棹忠夫(著) 『知的生産の技術』岩波新書、1969年

学修支援だより【2025年10月号】
学修支援だより【2025年10月号】
Foreword <1>
折り返し地点後の充実した学びに向けて
通信教育部副部長 足立 広美
「‘学ぶ喜び’の視点」
今年度の通信教育部の学びもいよいよ折り返し地点を過ぎ、後半に突入しました。日々の仕事や家庭との両立を図りながら学び続けることは、決して容易なことではありません。そのような状況下でも、一歩一歩着実に学びを積み重ねてこられた皆さんの姿は、本当に尊く、深い敬意を表します。
「学ぶ喜び」は人生を豊かにする光
さて、皆さんは「学び」という言葉をどのように捉えているでしょうか。創立者池田大作先生は、通信教育部開設40周年特別寄稿の中で、「学べば『世界』は広がる。『学ぶ』こと自体が『喜び』であり『幸福』です。『学ぼうとする決意』は、即『希望の光』であり、『学び抜こうとする執念』は即『勝利の光』である」※1と述べています。
この池田先生の言葉は、まさに私たちの学びの真髄を突いています。目の前の課題に追われる「苦しみの学び」や、提出期限に焦る「焦りの学び」と感じることもあるかもしれません。しかし、それらの経験もまた、「喜びの学び」「幸福への学び」へと向かうための大切なプロセスだと捉えることができます。「新しい知識や視点を得て、”なるほど!”と膝を打つ瞬間、疑問や苦しみの原因が見え、改善へとつながる瞬間」これこそが、教育学者の汐見氏が言うところの「脳の中に新しい情報処理の回路ができる」※2という「本来の学び」であり、私たちに「喜び」をもたらすものです。
もし今、「苦しみの学び」の渦中にいらっしゃる方がいるとしたら、ぜひそれを「喜びの学び」「幸福への学び」へと向かうための大切なプロセスだと捉え、充実した学びを継続していただきたいと心から願っています。
AI時代における「考える学び」の重要性
そして現代においては、生成AI(ChatGPTなど)を活用した「学び」についても、真剣に向き合う時期に差しかかっています。AIの進化は目覚ましく、私たちの学習環境にも大きな変化をもたらしています。しかし、AIがどれほど進化しても、私たちの「考える力」の重要性は決して揺らぎません。
経済学者の柳川氏は、「情報処理で重要なのは、大量の情報の中から自分に必要なものを的確に選び、不要な情報を上手に捨てること」※3だと指摘しています。そして、この情報の取捨選択においては、「日頃から頭の使い方を工夫している人とそうでない人とでは、大きな差が生じる」と、日頃から「考える癖」をつけることの重要性を述べています。AIが膨大な情報を提供する時代だからこそ、私たちはその情報に踊らされることなく、自ら問いを立て、批判的に吟味し、取捨選択する能力を磨く必要があります。
さらに柳川氏は、情報が溢れる現代社会においては、「確固たる正解を求めるのではなく、情報を頭の中で整理しながら問題意識を少しずつ変容・深化させていくこと」、そして「そのプロセス自体に楽しみがある」とも語っています。池田先生、汐見氏、そして柳川氏といった方々の共通する主張から見えてくるのは、「学び」に伴う喜び、面白さ、楽しさといった前向きな感情の重要性です。AIを単なるツールとして利用するだけでなく、AIが提示する情報を活用しながら、自らの思考を深め、新たな発見をするプロセスそのものを楽しむ。これこそが、これからの時代に求められる、創造的な「学び」のあり方ではないでしょうか。
学びの後半戦へ、自信をもって
後半の学修は、これまでの学びの集大成とも言える大切な時間です。通信教育ならではの孤独や不安が再び顔を出す瞬間もあるでしょう。ですが、皆様の挑戦は決して一人ぼっちではありません。同じように全国、世界各地で学ぶ仲間がおります。自分自身が選んだこの道を信じて、また一歩を踏み出してみてください。
どうか、「学ぶことの喜び」を感じながら、充実した「学び」の時間を過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。
引用・参考文献
※1 創価大学通信教育部編(2023)『創価大学 創立の精神を学ぶ―通信教育部編』学校法人創価大学,362頁
※2 汐見稔幸(2022)『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』河出新書,86頁,118頁
※3 柳川範之(2018)『東大教授が教える知的に考える練習』草思社,3頁,51頁,161頁
Foreword <2>
戦後80年の節目に想うこと —— 「記憶の歴史」の大切さ
教務部長 西田 哲史
私の専門は経済史という歴史学の分野になります。今夏、コロナ禍以来久しぶりとなる研究出張で2週間ほどドイツ各地の文書館に滞在する機会がありました。滞在時期が8月だったこともあり、ドイツの主要メディアでも広島・長崎への原爆投下とその惨劇を取り上げた特番が放映されていました。いうまでもなく、本年は第二次世界大戦終結から80年という節目の年であり、日本より3か月ほど早く終戦を迎えたドイツでも、各地でさまざまな記念行事が開催されました。
戦後、イデオロギーの対立を背景に国家の東西分断という状況があったものの、1990年に統一を果たして以来、多くのドイツ人にとって、戦争が眼前で起こるなどということは、あまり想像できない遠未来のことでありました。しかし、こうした認識はロシアによるウクライナ侵攻によって大きく変わりました。フランス・パリに本拠を置くイプソス(Ipsos)が2025年4月に世界規模で実施した世論調査によると、ドイツにおける回答者の27%が「国家間の軍事衝突」を最大の懸念事項としてあげており、1年前の2024年4月の22%と比較すると5ポイントの上昇でした。隣国のオランダやフランスでも、それぞれ29%と25%と国民の不安は急増しています。ウクライナと国境を接するポーランドに至っては、回答者の39%が「国家間の軍事衝突」を最大の不安要素と感じています。(Ipsos, 2025)
近年、欧米を中心に世界各地の右傾化が顕著となっています。ドイツでは、排外主義的な主張を掲げる極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の台頭に象徴されるように、国民の間でも過去に対する向き合い方、すなわち過去に対する歴史的責任のとらえ方について温度差が見られます。そうしたなか、ドイツの首都ベルリンでは、「解放の日」(Tag der Befreiung)と呼ばれる5月8日が、今年に限り公的な祝日と制定され、記念式典が行われました。シュタインマイヤー大統領は連邦議会で演説し、自身の確固たる信念として「過去と向き合う者は未来を放棄しない」と述べ、ナチスの教訓を踏まえて民主主義を守っていく必要性を訴えました。(Steinmeier, 2025)
大統領が発したこの言葉から、かつて創立者池田大作先生と対談されたヴァイツゼッカー元大統領が、終戦40周年の節目に連邦議会で行った演説の中で語られた言葉——「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります」——を想起しました。(ヴァイツゼッカー,2009,p. 11)国際情勢が揺れ動く今、「人類の平和を守るフォートレス(要塞)」を自負する創大通教で学ぶ皆さんには、改めて平和と民主主義の価値を再確認し、過去の記憶を正しく未来に伝える使命があることを強く自覚してほしいと心から願っています。
参照・引用文献:
Ipsos, What Worries the World – April 2025, https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct /news/documents/2025-05/what-worries-the-world-april-2025.pdf(2025年8月29日アクセス)
F-W. Steinmeier, "Wir alle sind Kinder des 8. Mai", https://www.bundespraesident.de /SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2025/05/250508-Ende-2WK.html(2025年8月29日アクセス)
ヴァイツゼッカー,リヒャルト・フォン(永井清彦訳)(2009)『新版 荒れ野の40年 ヴァイツゼッカー大統領ドイツ終戦40周年記念演説』(岩波ブックレットNo. 767)

教職指導講座
「教師が最大の教育環境となるために」
教職大学院准教授 堀内 省剛
はじめに
本学の通信教育部は伝統があり、多くの卒業生が教員採用試験に合格し、学校現場等で活躍されています。「教師は最大の教育環境である」という言葉は、教師の人間性、人格、そして、子どもへの限りない愛情こそが、子どもたちの成長にとって最も重要であるということを意味します。働きながら学ぶ通信教育で苦労したからこそなりえる、「人格的に磨かれた教員」の存在は、子どもの幸せの実現に欠くことのできない貴重な存在と考えます。
新たな教員採用の制度について
現在、教員採用の制度も大きく変わってきています。例えば、東京都では、教員免許非保持の社会人が受験し、教育委員会が定める年限内に教員免許を取得することで、採用されるような形態での教員採用試験も実施されております。
(東京都)「社会人特例選考」=年齢が 25 歳以上で社会人経験 2 年以上の方対象。教員免許なしで受験ができ、免許取得期間猶予者は選考合格後2年以内に免許を取得すれば、免許取得後に採用となります。
東京都公立学校教員採用ポータルサイト▶
本学の通信教育部では、このような教育採用の新たな制度を利用したい考える社会人のニーズに応えていくため、社会人特別枠での教員採用試験受験者を対象に 10 月特別入学制度を実施していますので、ぜひ、活用していただきたいと思います。(今年度の出願受付は終了いたしました。)
本学の教職大学院の紹介
創価大学に教職大学院が設置されたのは、2008年4月1日(平成20年度)です。それ以降、本学の教職大学院で学んだ多くの修了生が、日本全国の学校現場や行政機関等において、様々な立場で活躍されています。
さて、本学の教職大学院には、大きく分けて二つのコースがあります。その一つが、教育に関する職を10年以上経験した現職教員、又は協定を締結している都道府県・政令指定都市教育委員会及び学校法人等から大学院派遣研修として推薦ないし命令を受けた者が学ぶ、「人間教育実践リーダーコース(1年間)」です。このコースでは、学校や地域で中核的・指導的な役割を果たすスクールリーダーを育成することを目指しています。そして、もう一つが、人間教育実践リーダーコースの出願資格に該当しない現職教員や大学等で教員免許状を取得した者(取得見込みの者も含む)が学ぶ、「人間教育プロフェッショナルコース(2~3年間)」です。このコースでは、実践的指導力と豊かな授業力を備えた各学校の有力な一員となりうる教員を養成することを目指しています。
本学の通信教育部出身者も教職大学院へ
本学の教職大学院には、通信教育部で教員免許状を取得された方(教員になられた方)も数多く進学しております。そして、教職大学院が設置される際、創立者の池田先生からいただいた三指針である「子どもの幸福を目指す慈愛の教育者たれ!」「生命の尊厳を護り抜く正義の教育者たれ!」「平和の世界を創造しゆく英知の教育者たれ!」を胸に、教職大学院の学修に真摯に取り組まれ、その後、学校等において指導的な役割を果たされております。
教職大学院の入学者に期待すること
本学の教職大学院では、次のような方を求めています。
1.優れた教員となるための資質としての基礎学力を有し、かつ教育への強い関心と学習意欲を有する方
2.他人が幸せになることや成長発達することを心から喜べる人柄の方
3.ものごとを柔軟に捉えることができ、かつ常に自己更新していこうとする学習姿勢を有する方
教職大学院の主な特色
・教育現場の課題が学習課題:グループごとに課題を設定し、解決方法を共同で追究します。
・学校現場との連携を重視した学習:自らが学校の諸課題に主体的に取り組む資質や能力を培います。
・ティームティーチング方式での授業:バリエーションに富んだティームティーチング方式により授業を行います。
・教育委員会等との連携:教育委員会や学校現場の教員と連携しながら授業を行います。
・ディスカッション、プレゼンテーションの重視:すべての授業で学習者の主体性を重視した授業を行います。
教職大学院の修了認定・学位授与
教職大学院の教育目標に基づき、所定の期間以上在学し、所定の単位を修得した者について修了認定し、教職修士(専門職)の学位を授与します。併せて、単位の修得に応じて、専修免許状を取得することができるのも、大きな魅力の一つといえます。
【教員免許の取得について】
結びに
牧口常三郎先生の著わされた『創価教育学体系』の中核をなすものは、子どもの幸福こそが教育の目的であるという理念です。その理念は、創価大学の創立者である池田先生の教育思想にも、脈々と受け継がれ、創価大学の建学の精神並びに創価大学教職大学院の指針にもつながっております。その理念を体現すべく、通信教育部で懸命に学ばれている皆様に心より敬意を表するとともに、今後のご活躍を心より祈念いたします。
結びに、この紙面をお借りし、本学の教職大学院の紹介をさせていただきましたが、ぜひ、進学についてもご一考いただくことができましたら幸いです。
学修支援推進室コーナー
学術文章作法の特徴とレポート学習の注意点
通信教育部教授 劉 継生
通信教育部で求められるレポートは学術的な文書であるため、その作成には問いを立て、客観的な根拠に基づいて論理的に進めることが必要です。つまり、客観的な根拠を取り入れながら内容を展開し、議論を深め、問題を解決することが重要です。ここで言う「客観的な根拠」とは、個人の主観的な考えや特定の立場にとらわれず、物事の存在や成立を明示するための理由や証拠を指します。具体的には、テキストや参考文献、学術誌、インターネット、新聞などの情報源から集められる資料、データ、事例、研究成果などが含まれます。もちろん、これらの根拠を自分のレポートに取り入れる際には、その信頼性を確認する必要があります。根拠が不十分であったり、適切性を欠いたりする場合、学術的な文章としては認められません。このように、レポート作成時に守るべき方法や規則をまとめて「学術文章作法」と呼びます。
レポートを他者に認められる学術的な文章として成立させるためには、論理的に作成しなければならないとよく言われています。実際に、「論理的」という概念や思考法は、最も重要な学術文章作法でもあり、以下の三つの意味が含まれています。まずは、レポート全体に関する論理的な構成が挙げられます。つまり、レポートは序論、本論、結論の三部から形成されています。序論は、何を対象として、どのように考察、分析、論証を行うかを示すことです。本論は、序論で取り上げた問いに対して、根拠となる素材や資料を収集し、説明を組み立て、議論を展開することです。結論は、議論の結果をまとめ、問いに対する答えを提示し、問題解決を明確に述べることです。
次に、パラグラフにおける論理的な構成です。本論は、見た目上は複数の段落で構成されています。実際には、それぞれの段落は一つの主題を扱っているパラグラフです。パラグラフのつながりによって、主題から主題へと本論の内容が展開されるようになっています。パラグラフとは、一つの主題とそれを支える複数の補足から成る意味的なまとまりです。言いたいことや主題を示す文は題目文と呼ばれ、詳しく言い直したり根拠を示したり限定したりする文は補足文と呼ばれます。補足文の支えが弱まると、題目文が成立しなくなります。逆に、補足文が十分であれば、題目文が強く伝わることが可能です。
第三に、文と文の間に存在する論理的な関連性です。一つのパラグラフは複数の文から成り立っています。通常、一つの文は主語や述語などの文法的な役割を果たす言葉によって構成され、一義を表現することが可能です。しかし、作成した文が成立するかどうかは、前後にある文との関連性に依存します。その関連性は、文と文の間の因果関係や相関関係、並列関係、対立関係、補足関係などを指し、接続詞を用いて表現されることが一般的です。前後との関連性が欠けている文は、無用な存在となり、削除または書き直す必要があります。文と文の関連性が強まるほど文章は論理的になり、伝わりやすい効果が生まれます。また、文を作成する際に新しい概念や専門用語を使用することがあります。学んだ概念や専門用語を初めて使用する際には、意味のズレや不一致が生じないように注意が必要です。
もう一つの重要な「学術文章作法」について考察します。それはレポート課題に対する問題意識を形成することです。問題意識が形成されなければ、客観的な根拠を収集したり、論理的な文書を構築したりすることは不可能です。なぜなら、レポート課題における思考の枠組みは問題意識の中に含まれるからです。問題意識の形成とは、レポート課題や課題解説、テキストを精読した上で、集めた多様な情報や素材を自分の既存の知識に照らし合わせ、知恵を生かし、思考を深めたり、関連性を広げたり、ひらめきを得たりすることを指します。これにより、「何が問題なのか」、「問題の構造はどうなっているのか」、「どのような因果関係が存在するのか」という問いに対する解答を導き出し、レポート課題の意味合いを明確にすることが可能になります。
実際に、私たちはレポート課題における問題意識に導かれる形で、問いを立てたり、論理構成を考えたり、アウトラインを構想したりします。したがって、明確な問題意識を持つことで、自分の脳内にすっきりとしたイメージが生成され、より良いレポートを作成することにつながります。一方、問題意識が不明確で、思考が混沌とした状態では、レポートを書きたくても書けません。なぜなら、テキストを何回も読み、たくさんの情報を検索しても、かき集めた情報はバラバラの断片に過ぎず、論理的に組み立てて体系化するすべはないからです。
レポートを作成する過程では、私たちは自らの読解力、分析力、要約力、表現力を何度も試し、実践することになります。したがって、レポート作成は、自分の思考力や問題解決能力、創造力を向上させる貴重な機会でもあります。通教生の皆様には、このような意識を持ってレポート作成に取り組んでいただきたいと考えています。

ブック・スクウェア
墳墓記
通信教育部教授 坂本 幹雄
髙村薫の作品は、かなり前に『太陽を曳く馬』(2009)を本コーナー(『学光』2010年4月号)で紹介した。まず同書以降、標題作に至るまでの作品(エッセイ等を除く)をかんたんに紹介しよう。『太陽を曳く馬』は合田雄一郎刑事シリーズの第4作である。同シリーズの第5作は『冷血』(2012)。同書はトルーマン・カポーティの『冷血』をオマージュした作品である。
さらに第6作『我らが少女A』(2019、毎日新聞出版)と続いている。同シリーズの最新作であるから少し紹介しておこう。本文を引用しよう。
「当時、捜査員の誰かがターナーの絵のようだと言ったとおり、武蔵野の風景は空と水と、そこから生まれる水蒸気を含んだ空気の光が作り出しているに違いない。/しかしいま、合田の網膜、あるいは海馬に広がる野川の景色に、ターナーの光はない。一幅の風景画のような景色であれ、ひとたび事件の現場になったが最後、すべてが被害者と加害者によって眺められたものとなり、刑事は是も非もなく彼らの眼に憑依する。」(58頁)
同書は「合田雄一郎、痛恨の未解決事件」(帯)となっているが、完結編なのかどうかは不明である。なお同書は本年、文庫化(上・下)されている。
同シリーズのほかに『四人組がいた。』(2014)、『土の記』(上・下)(2016)がある。著者の文体は、硬質重厚で知られるが、『四人組がいた。』(文藝春秋)は(私が読んだ中では唯一)軽妙なタッチで読みやすい作品である。
『土の記』(新潮社)の上巻の帯に「……古希を迎えた伊佐夫は、/残された棚田で/黙々と米を作る」とある。『土の記』は入手したものの、「米作りの話かあ。テンション上がらないなあ」と読む気がしなくなり、長らく積読状態であった。そして読後、よくあるように「もっと早く読めばよかったなあ」と思った。標題の『墳墓記』も『土の記』同様、何か地味そうな感じがしたが、積読だとまた後悔すると思い、今度は入手後すぐに読んだ。
では帯を引用してまず内容紹介をしよう。
「地に沸き立つ声、声、声/男が、定家が、鬼が、夢を見る/髙村文学の極限と愉楽がここに」
「老いて死に瀕した一人の男が、/意識の塊と化して長い長い仮死の夢を見る。/そこに沸き立つのは高らかな万葉びとの声、野辺送りの声、/笑い転げる兎や蛙の声、源氏物語や伊勢物語の声、古今・新古今の歌の声、都を駆けるつわものたちの声、/そして名もなき女たちの声––––。/古文と現代文の自在な往還を試みた渾身の長編小説」
長編とあるがそう長くはないだろう。
本文の比較的読みやすいリズミカルな個所を少し引用しよう。源平合戦の部分である。
「時は寿永四年三月二十四日の卯の刻––––とくれば平曲は壇ノ浦。豊前の国、長門の壇ノ浦にて源平の矢合わせとぞ定めける。ばらららん。喉を潰した盲僧の嗄れ声はそのまま瀬戸内海の波音になり、曰く、まだ明けやらぬ沖を眺むれば、幾万幾千の島中を西へ西へと突き進む、判官義経率いる源氏の兵船、総勢三千余艘。ばららん、ばららん。対する平氏は……」(32頁)
しかし古文と現代文の往還とあるように全体的にはそう読みやすくはないだろう。
題材は日本の古典文学が中心であるが、西洋の古典文学や『アラビアのロレンス』や『冒険者たち』などの映画も出てくる。
「……男は長い長い夢を見る」(3頁)と夢の世界の話が始まる。読み始めて、これでストーリーがあるのかと思わされる。しかしやがて主人公の人生が次第に明らかとなってくる。そして『土の記』同様(ほどではないが)、衝撃の展開となる。
一気に読んでしまった。最後に定家の次の一首が引用されている。
「ふきはらふもみぢのうへの霧はれて峯たしかなる嵐山哉」(179頁)
もっとゆっくりと古典の世界を味わいながら読むべきだったと思う。
髙村薫の作品は、初期のようなミステリーではなくなっても、結局、ミステリーの趣を残していて、新作が出たら、やはり読まずにはいられないなと感じた。
『墳墓記』
著者:髙村薫
出版社:新潮社
発行年:2025年
ISBN:78-4-10-378411-1
頁数:179頁
価格:1,990円+税
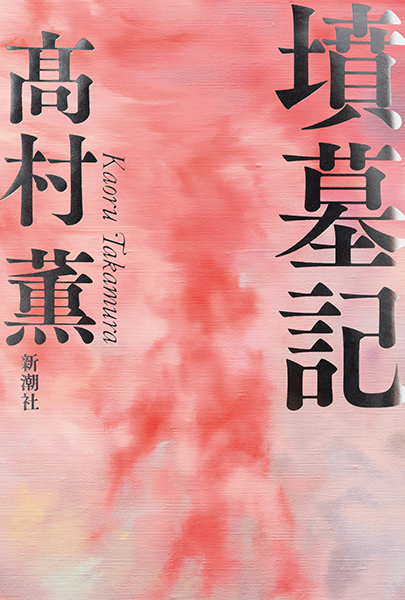
学修支援だより【2025年9月号】
学修支援だより【2025年9月号】
Foreword
共感が育む看護の力──患者の生きる力と、自ら学び続ける力
看護学部長 佐々木 諭
看護学部には、創立者からいただいた「看護学部指針」があり、学生・教職員は常にその指針を胸に、学修と教育に取り組んでいます。その指針の一つに、「生きる力を引き出す励ましの心光る看護」があります。今回は、「生きる力を引き出す」ための「励ましの心」とは何かについて、「Empathy(共感)」と「Sympathy(同情)」という二つの言葉を参照しながら考えていきましょう。
看護の実践において、「Empathy(共感)」と「Sympathy(同情)」の違いを理解することは、患者と真に向き合うための重要な出発点です。Sympathy(同情)とは、患者のつらさや悲しみに対して「かわいそうだ」と感じること。もちろん、苦しんでいる人を前にしてそのように感じるのは、人間として自然な反応です。しかし、同情はしばしば相手の感情に自分が巻き込まれ、冷静さや客観性を保つことが難しくなります。さらに時に、患者を「支えられる側」「弱い存在」として見てしまい、目の前の患者の尊厳や可能性を損ねるおそれもあります。
それに対してEmpathy(共感)とは、相手の立場に心を寄せながら、その感情を理解しようと努めることです。共感は単なる「感情の共有」ではなく、「相手をこの世に一人しかいないかけがえのない存在として尊重し、理解しようとする姿勢」にあります。看護師が共感的に患者と関わることで、患者は「自分の思いが受け止められている」「理解されている」と感じ、安心感を得ることができます。
この共感の力は、患者の「生きる力」を引き出す鍵となります。病に苦しむ患者にとって、共感的に話を聴いてもらう経験は、「自分自身が尊重されている」という実感をもたらします。そしてその中で、少しずつ希望や役割を見いだしていくことがあります。共感は、患者に「まだ自分にできることがある」「自分の人生には意味がある」と思い出させてくれる、励ましのかたちでもあるのです。
共感は、看護師が患者の内なる力を「引き出す」ための重要な資質であり、それを磨き続けるには、感受性や対話力を絶えず育てていく必要があります。この力は一朝一夕に身につくものではありません。患者一人ひとりの語りに丁寧に耳を傾け、その背景にある人生観や価値観、感情を理解しようとする日々の実践のなかで、少しずつ培われていくものです。また、常に自身の人間性を磨き、すべての人々の尊厳を守りぬくための内面の強さも求められます。だからこそ、看護師自身が「学び続ける姿勢」を持ち続けることが大切になります。
通信教育部で学ぶ皆さんは、家庭や仕事と両立しながら、日々たゆまぬ努力を重ねておられることでしょう。その姿勢こそが、まさに「共感する力」を育む土台になっていることと思います。創立者の言葉に、「苦難に負けず、労苦を重ねた分だけ、心は鍛えられ、強く、深くなり、どんな試練も乗り越えていける力が培われていく。さらに、人の苦しみ、悲しみがわかり、悩める人と共感し、同苦し、心から励ましていくことができる」とあります。この創立者の言葉のままに、日々挑戦し、学び続けられる皆さんの姿に心から敬意を表します。そして、皆さんのまわりにいつも「励ましの心」が光り輝いていくよう心より願っています。
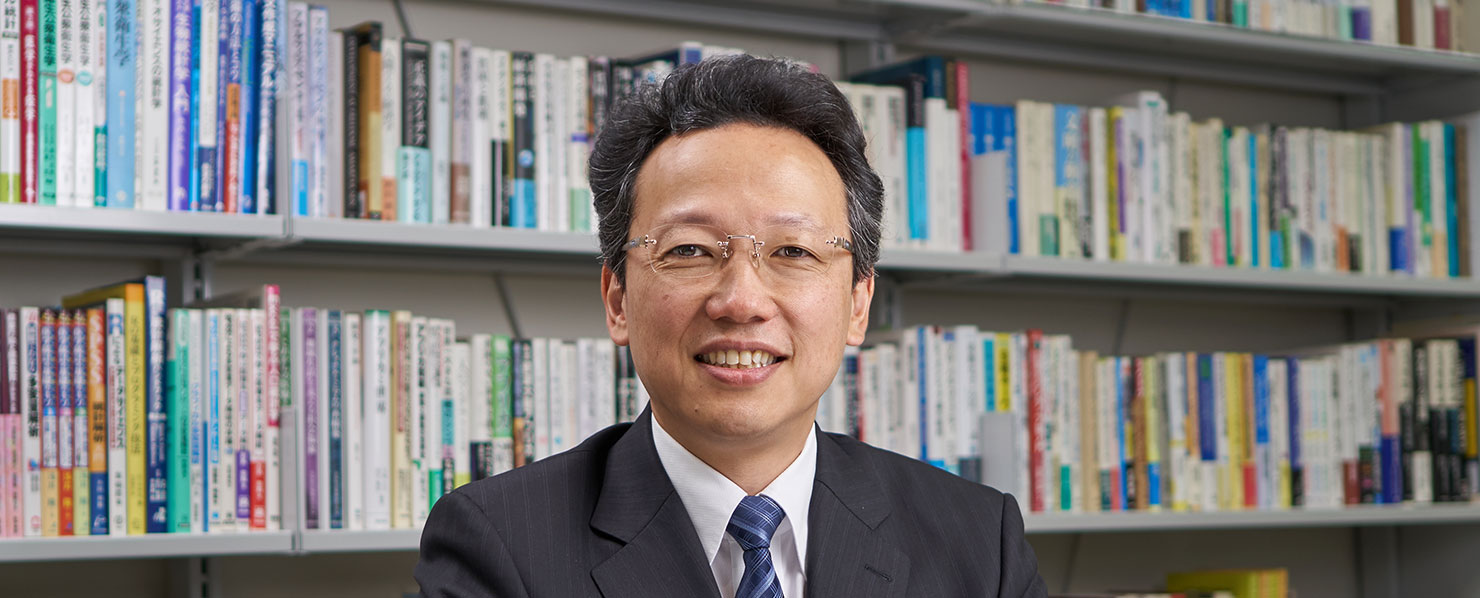
自立学習入門講座80
国際人権法を学ぶ姿勢について
法学部教授 飯田 順三
【国際人権法の発展】
国際人権法は国際法の一分野として発展してきました。現在では、多くの大学で国際人権法という名称の講義が開講されています。歴史的にみると国際人権法は、第二次世界大戦後に、人権が国際的に関心のある事項となってきたことと並行して、国際法学に含まれていた人権の分野が独立して発展してきました。
そもそも国際法というのは国家間のルールなので、国家が中心となる規範体系です。つまり、国家の中の個人というのは国家が統治する客体であって、個人が国際法上の主体となるという考え方はありませんでした。ところが、第二次大戦中のナチスドイツによる強制収容所内での悲惨な出来事が戦後明るみになるにしたがって、人権を擁護できなかったという反省の念が西欧各国において生まれました。また、国内の人権侵害は、例えば難民を生み出すなどのように、周辺国にも影響を与えます。つまり、国際関係が不安定になる要素となりうるものとして国内の人権問題を捉え直そう、そして、個人にも国際法上の法主体性を付与すべきではないかという考え方が登場しました。
【国家と国際人権法】
ところで、人権は誰によって侵害されるのでしょうか。もちろん、個人間でのトラブルなどによって人権が侵害されることもあり得るでしょう。あるいは、会社やその他の組織における人権侵害ということも考えられます。しかし、最大の人権侵害は、国家による個人への人権侵害、あるいは国家と国家の戦争から起きる人権侵害であると捉えることができます。つまり、国家に対する個人を守る規範体系が国際人権法であるいえるのです。いいかえると、国家の悪に対抗する規範が国際人権法であって、本質的に国家を性悪説に捉える性質を内包しているのが国際人権法といえるでしょう。個人の人権を侵害する国家に立ち向かうのが国際人権法なので、国家というに存在に対抗しながら国際人権法は成長し発展してきたのです。
【国際人権法の学問的特徴】
国際人権法を学ぶというのは常に実践的でなければなりません。学問というのは、書物などを読んで思考し、その考え方や理論を実践することが、学び方の基本型ですが、国際人権法は特に「実践」の部分が重要になってきます。いくら国際人権法の知識を得たとしても、一人の人を救えない、一人の人の人権を守ろうとしないのであれば、国際人権法を学ぶ意義は無いに等しいのです。このような視点から、われわれ国際人権法を学ぶ者は、自らの小さな一歩で良いので、人権を守る行動を取らねばなりません。「国際人権法は実践的な学問である」ということを肝に銘じて国際人権法を学んでいってください。
【国際人権法の体系】
国際人権法を学ぶプロセスは、その全体の構造あるいは体系を知ることから始まります。おおまかにいって次のような体系になっています。国際人権法の中身については、テキストはじめメディア教材およびスクーリングで学びますので、ここでは詳細は述べませんが、ごく簡単に触れましょう。
まず、国際連合憲章(以下、憲章)があります。国連憲章は、国際連合(以下、国連)を成立させている文書ですね。そもそも国連設立の目的は、一言で言って世界平和の達成です。そのためには、国連は、人権分野に限らず、経済、交通、通信、教育、安全保障など様々な分野にわたって重要な役割を有しており、憲章はこれらの分野について規定していいます。
その中にあって、人権に関しては抽象的に規定されています。たとえば、憲章第1条3項では「人種、性、言語又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」が、国連の目的であると規定しています。このように、憲章の人権規定は抽象的にしか規定されていませんので、人権擁護に特化し具体的な国際的な文書の作成が必要であると考えられました。それが、「人権に関する普遍的宣言」です。これは、日本では世界人権宣言と呼ばれています。しかし、この宣言は国際法上の法的拘束力がないものとして作成されました。なぜなら法的に国家を拘束する文書となると、かなりの時間を掛けなければ各国家は合意しないからです。
そこで、世界人権宣言が法的に拘束力はないので、次に、法的拘束力のある国際文書として国際人権規約が採択されました。これは自由権規約と社会権規約の二つの文書として成立しました。したがって、国際人権規約は、憲章および世界人権宣言を具体化した内容になっています。
国際人権規約の内容をさらに細分化したものが、個別の人権条約です。ジェノサイド禁止条約、女性差別撤廃条約など、多くの個別人権条約が作られてきました。
以上のように、憲章の下に世界人権宣言、国際人権規約、そして個別の人権条約が連なっています。国際人権文書は、このような構造になっているのです。
これらの国際人権文書のほかに、国際裁判や各国の国内裁判で争われたいわゆる人権判決も国際人権法の対象となります。これらの判決は、国際人権文書が具体的に適用された事例ですので、国際人権文書という「規範」と現実に起きている「事実」との相互関係を知る上で重要な情報となります。
【国際人権法の実践的内容】
国際人権文書の権利部分、つまり実体法を知った上で、さらに、履行確保措置あるいは実施措置と言われるものを学びます。これは規範内容が実戦的に確保されていくための具体的な方法のことで、国際人権文書の規範の中に埋め込まれています。国内法では、法規範は何々法という実体法で規定され、その権利の実施は手続法と呼ばれる法に委ねられます。たとえば、民法は実体法で民事訴訟法は手続法です。しかし国際法では、ひとつの条約中に実体法と手続法が同時に規定されている場合が多いのですが、特に国際人権法では、実体法の内容を確実にするために、実施措置と呼ばれる仕組みも規定されます。つまり、国際人権法は、その権利内容を実現するために、実体的な権利規範だけでなく、さまざまな具体的な方法も同時に規定されているのです。
さらに、国連の諸組織が、国際人権法の規範内容を確保する役目を担います。たとえば、女性差別撤廃条約については、女性差別撤廃条約委員会であるとか、子供の権利条約ではこどもの権利条約委員会などといった組織が、ぞれぞれの条約が履行されるように各国に働きかけます。このような側面も国際人権法で学びます。
国際人権法の学び方としては、以上述べた国際的な人権擁護に関する法制度の歩みを理解し、それぞれの規範の中身および履行措置の手続きを知るという方法が一般的です。
【国際人権法の裁判事例】
上で述べたように、国際的な人権文書の内容を知ると同時に、この分野の裁判事例を理解することが同時に重要なポイントです。一般的に法学の分野では、著名な『判例百選』と呼ばれる判例集が刊行されており、学習する上で重要な教材となっています。たとえば、国際法領域では『国際法判例百選』がありますね。また、『国際私法判例百選』も刊行されています。ところが、『国際人権法判例百選』はまだありません。人権分野の判例は、『国際法判例百選』がカバーしています。みなさんが憲法で学んだ二風谷事件や塩見事件は国際人権法でも重要な判例ですので、憲法分野の判例を理解する必要があります。
一方、国際人権法領域で大いに参考になるのが、欧州人権裁判所の判例です。これについては、単行本として判例集が刊行されていますので参考にしましょう。そのほかの国内裁判についても、国際人権法の学習では目配りが必要となってきます。したがって、国内外を問わず、人権に関する裁判事例は見逃さないようにするのがポイントです。
さらに、新聞に掲載されている人権関連の記事にも注意を払いましょう。これらは今まさに問題となっている生きた情報ですので、積極的に入手して国際人権法の理想と現実を知っていきましょう。
【本学の国際人権法講義】
本学法学部の国際人権法は、1995年度開始のカリキュラム改正をおこなうに当たり、平和と人権を守るのが創価大学の使命であるならば、国際人権法を開講すべきだとの考えから、私が提案しました。提案した限りは担当せよとの先輩教員の助言によって、今日まで私が担当しています。早いもので、この科目が本学で設置されてから、本年2025年で30年になります。当時のカリキュラムは通年制でしたので、ほぼ全部の科目が4単位科目であり、1年かけて学ぶのが制度でした。また、この科目は3年生からの履修でしたので、1997年から、通年4単位科目として開講しました。その後、全学的に半期集中型のカリキュラム編成に移行するにあたり、国際人権法も2単位科目に衣替えして今日に至っています。
1995年ごろは、米国でも著名な大学で、すでに国際人権法講座が定着していました。たとえば、ハーバード大学では1984年、イエール大学では1989国際人権法講義が開始されています。しかし、日本では国際人権の分野は、国際法がカバーする領域と一般的に学者間で理解されていたようです。したがって、国際人権法という名称で科目を開講していた大学はあまり見かけず、国際人権法の概説書や教科書も今ほど刊行されていませんでした。その意味では、本学の国際人権法講義は先駆的な試みであったといえるでしょう。創立者池田先生の平和と人権の精神が脈打つ創価大学であったればこそ、その精神が本学の教員に受け継がれた結果として開講された科目であると捉えることができると思います。
【おわりに】
最後にもう一度、国際人権法の学び方の基本を確認しましょう。国際人権法は実践的な学問です。知識だけ獲得して現実に人を助けることができないのであれば、国際人権法を真に学んだことになりません。通教生の皆様は、現実社会の中で日々奮闘しながら、人を思う心を持ち学ばれていると思います。国際人権法を深く知り、日常生活において、さらに人権を守る実践を続けていきましょう!

学修支援推進室コーナー <2>
オンデマンドスクーリングだより -西洋哲学史Ⅰ-
非常勤講師 山崎 達也
宇宙が《ある》とはどういうことか
夜、星空を見上げるときの驚嘆はどこからくるのだろうか。この問いは2600年の時間を超えて私たちを哲学の始原へと導く。そこで私たちは同じ驚嘆を抱いた人たちに出会う。
宇宙の《はじめ》とは何か。彼(タレース)は「水!」と発した。しかしなぜ「水」なのか。それに関する彼のテキストは遺されていない。だからこそ、私たちは彼といっしょに対話することができる。「水」とはそもそも何か、私たちはこんな問いを考えたことはない。こうした何気ない問いが私たちを哲学へと誘う。
宇宙は美しい。その美しさをいかに非の打ちどころなく表現できるのか。彼(ピタゴラス)はできると語る。では、どのように? 彼はその美を音階(ハルモニアー)として描写した。星々は秩序にしたがって回転しながら、全体として音を奏でている。彼はその音の饗宴をシンフォニアと呼び、毎晩それに浴していた。私たちも実は聴いているはずなのだ。なのに聴こえない。私たちの魂は世間のあまりに人間的なことに関わっているから、その純粋性を失っていると彼はそう警告する。カタルシス(浄化)こそ、哲学なのだ。
宇宙のリズム(リュトゥモス)は自らを更新する。宇宙は一瞬のうちに死して生まれると語った者(ヘラクレイトス)もいる。この妙を彼は「太陽は日々に新しい」と詠った。私たちの生命は宇宙のリズムに共振し、つねに新しくなっている。生命は自己を成長させる理(ロゴス)をもっている。それが自然のあり方なのだ。人間が自然を見るのではなく、自然が人間を見ている。
宇宙は《ある》。この《ある》とはそもそも何か。こんな途方もない問いなど、通常思いつかない。でも《ある》がなければ、それこそ宇宙も《私》も存在していない。このことに気づいてしまうのが哲学徒なのだ。彼(パルメニデス)はこの《ある》に酔いしれた。《ある》には絶対に《あらぬ》は含まれてはならない。《ある》は《ある》でしかない。考えてみれば当たり前のことだ。でも、私たちはその《当たり前》に気がつかない。《ある》は私たちの足下にあるのに。
《ある》は深淵として現れる。私たちはつねに深淵にさらされている。でも人間知性は《ある》の深淵を捉えることができないのではないか。私たちはここで知性を放棄し、神的狂気(マニア―)に身をゆだねるしかないのだろうか。哲学が成り立つ限界に眩暈(めまい)とともに立ちながらも、彼(プラトン)は不変の真理が存在するという信念を揺るがせにしなかった。彼はその真理を《イデア》と呼んだ。《ある》といわれるのはイデアのみ、私たちの周辺にある事物はすべてイデアの影にすぎない。彼に言わせると、私たちは夢を見ながら生きているのだ。影を実在と見てしまう性(さが)を人間はなかなか捨てることはできない。だから人間は迷う。そして世界は迷う。
イデアはこの世界を超えている。しかし彼の弟子(アリストテレス)は日常経験のリアリティーを主張し、師の学説を批判する。私たちは何かを見、何かを聞く。この経験によって私たちの日常は成り立つ。日常の事実は頑固である。しかし彼はその頑固さを神秘と見て、どこまでも追究した。その原動力はあくまでも人間知性でなかればならない。彼はそれを疑わなかった。
何が本当に《ある》のか。私たちの眼の前に一つの白い机がある。その色を青に変えても、赤に変えてもそれが《机であること》は変わらない。「この机」を彼(アリストテレス)は《実体》(ウーシア)と呼んだ。彼は《ある》を実体論として考え始めた。それは哲学の歴史のなかで大きな転換点だった。
宇宙はなぜあるのか
「はじめに神は天と地を造った」(創世記1:1)。この命題のもつ強さは計り知れない。さきにアリストテレスは人間知性を徹底的に遂行し、経験を超えたものを捉えた。宇宙は偶然に動いているわけではない。しかしもし偶然であるなら、宇宙のあの美しさは説明できない。ある一定の秩序にしたがって、究極目的を目ざして宇宙は動いている。その目的は自らは動くことなく、自己以外のすべてのものを自らへと動かす。それこそ彼が見た神であった。
しかし聖書に描かれる神はこの宇宙を造り、しかも私たち人間を救済する慈悲の神である。なぜ宇宙が造られたのか。それは人間を救済するためである。ここに一つの問いが発生する。哲学は人間を救済できるのか。救済のためには哲学とは別の学が必要なのではないか。彼(トマス・アクィナス)はそう考えた。その学は「聖なる教え」と呼ばれた。すなわち神学である。哲学はここに新たに岐路に立たされる。人間知性はここで自己自身を信じなければならない。信仰と知との相克は私たち自身の問題である。そう捉えたとき、この問題が真に問われることになるだ。ここに哲学は生まれ変わる。
宇宙がなぜあるのか、その答えを私はたちは「信仰」に席を譲ることなく、どこまでも知性でもって考えていなければならない。かえって、「信仰」をも哲学的に考えていくべきであろう。この問いを解決できるのは私たち人間だけである。哲学を学ぶ意義はここにある。
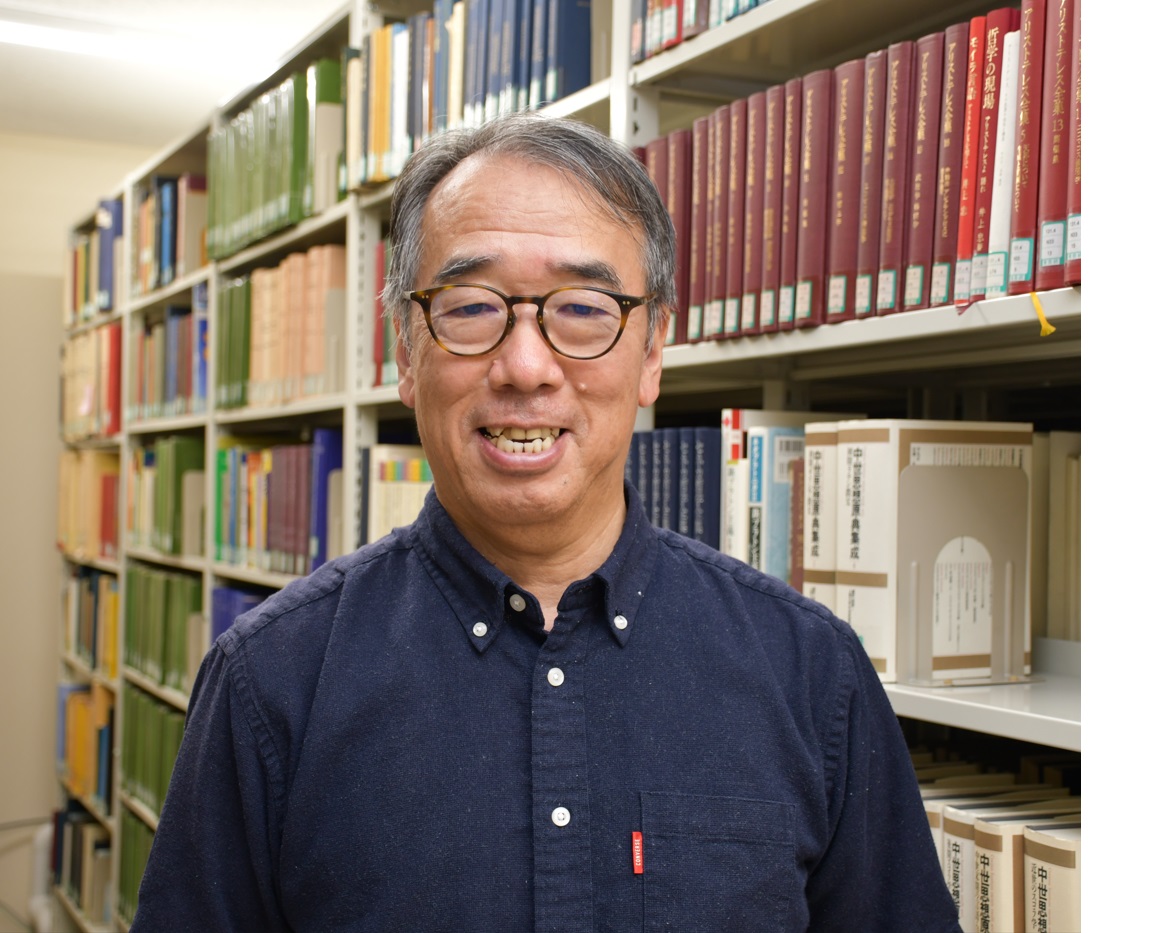
学修支援だより【2025年8月号】
学修支援だより【2025年8月号】
Foreword
夏期スクーリング開講式挨拶
通信教育部長 吉川 成司
学の光を求め人生のヴェールを開きゆこう
職場や家庭でさらに地域でお忙しくされながらも、たゆみなく勉学の歩みを進めておられる通教生の皆さんに最大の敬意を表したいと思います。猛暑の折、また遠路にもかかわらず、ようこそ創価大学へお越しくださいました。
昨年の夏期スクーリングも記録的な猛暑でしたが、参加された通教生の皆さんは、異口同音に対面での授業や友人との交流に喜びを語っておられました。今年も活気に満ちたキャンパスの光景が目に浮かぶようです。対面授業にはオンライン授業にはない臨場感があります。ある時は真剣な知的触発があり、またある時には和気に満ちた雰囲気を直接体験し共有できます。今年も、燦々たる夏空のもと、創価大学の広々としたキャンパスで、日本中、世界各地から集う同学の友と、充実した学び合い、触れ合いの思い出を刻んでいただきたいと思います。
来る2026年は通信教育部開設50周年の佳節であり、創価大学全体の学部改組に伴い、通信教育部では新たに経済経営学部ビジネス学科が立ち上がります。そのほか法学部法律政治学科、教育学部心理教育学科、文学部の4つのコースと、さまざまにリニューアルされます。通教生の皆さんとともに、創価大学全体としても次の新しき50年に向けて、未来をひらく力強い挑戦が始まっています。
さて、今から20年前の2005年5月、創立者は通教開設30周年を記念して、「『生涯学光』の心で勝利の人生を!」と題するメッセージを寄せてくださいました(『学光』350号掲載)。そのなかで、19世紀のイギリスの思想家であるジョン・ラスキン(1819‐1900)の言葉が紹介されています。「大胆にヴェールをあげよ。光を正視せよ」と。この言葉は、産業革命後の新たな時代を展望し本質的な価値とは何かを論じた論文、『この最後の者にも』のなかで語られている言葉です。
ちなみに昨年、「今に生きるラスキン」と題する展示会が大阪大学中之島芸術センターの主催により開催されました。それによると、彼は産業革命による生産の効率化を問題視し、分業化の中で人が歯車の一つに矮小化された結果、仕事そのものへの喜びが失われてしまったことを指摘しているとのことです。すなわち、製品を量産し収益を上げることだけが、果たして人の生きる豊かさといえるのだろうかというのです。
さて現代では、日常的にヴェールを身にまとう機会はなかなかありませんが、高度情報社会に生きる私たちは、“情報のヴェール”に閉じ込められている場合があるかもしれません。それは「フィルターバブル現象」と言われています。皆さんもご経験があるかと思いますが、インターネットで検索をすると、動画の視聴や品物の購入など、次々に“おすすめ”情報が飛び込んできます。また、閲覧と無関係なネット広告は目に余るばかりです。このように、インターネットを通じて得る情報が狭まり、あたかもバブル、すなわち半透明の泡のフィルターで視野が狭まり、個人と個人そして社会全体の分断・対立を引き起こしかねないことが危惧されています。
ラスキンの箴言を受けて、創立者は、「希望の光を、まっすぐに見つめながら、わが人生のヴェールを大きく開いていってください。皆さまの勝利の輝きこそが、創価教育の『勝利』であり『光』なのであります」と、万感こもる励ましを送ってくださっています。
“学の光を求めて人生のヴェールを開きゆく”との方途を示してくださった創立者のご指導は、高度情報社会を生きる私たち現代人にとって重要な示唆を与えるものではないでしょうか。今回の夏期スクーリングにおいても、人生のヴェールを開きゆく勉学へ挑戦を心より念願するところです。
最後になりますが、猛暑が続く中でのスクーリングですので、くれぐれも体調管理にご留意されますようお祈りいたします。

ブック・スクウェア
潮音
通信教育部准教授 開沼 正
本作品(全4巻)は宮本輝が手がけた「初の歴史小説」という触れ込みで、いくつかのメディアには紹介されている。著者がどのような経緯で歴史小説を書く気になったのかは分からない。ただ主人公の川上弥一は富山の薬売りという設定である。著者は幼少期に富山で過ごしたことがあるらしく、富山の薬売りの販売システムに興味を持ったことが、この小説を書くきっかけの一つにはなったようである。
弥一は「おわら風の盆」で有名な八尾の紙問屋の家に生まれた。「嘉永四年(一八五一)、二十歳」(第1巻8ページ)とあるので、満年齢なら天保2年(1831)の生まれとなる。ちなみに幕末に活躍した人物には、この頃の生まれが多い。年齢的に30~40代で、人間としての活動量がピークを迎えるからだろう。
弥一が16歳のときに富山藩の「反魂丹役所」から富山城下の薬種問屋・高麗屋に奉公するように命じられた。それ以来、売薬行商人(いわゆる富山の薬売り)として生きた。富山の薬売りは全国に販売のネットワークをもっており、弥一は薩摩藩の担当(薩摩組)を命じられた。
薩摩藩は、他地域の人間が藩域に出入りすることに神経質である。「関所でのお改めの厳しさ。藩内での行動の規制。奉行所の監視。怪しいと睨まれれば内密裏に斬り殺される。幕府の隠密とて容赦しない。(第1巻67ページ)」とされ、薩摩に派遣される者は「冥途の飛脚」とも言われている。
小説は、弥一を訪ねてきた「あなた様」に対して回想話をするかたちで進んでいく。時代については「ことしは明治十三年」(第1巻321ページ)とあるので、著者自身は明治13年を念頭に置いていると思う。しかし冒頭部(第1巻6ページ)では「明治と年号を変えて(中略)十三年」とあるので明治14年という解釈もできる(瑣末なことだが……)。
明治の10年代がどのような時代だったのかというということで、高校日本史の教科書を見ると、明治10年には西南戦争が終わり、不平士族による反乱が一段落したとある。それ以降は国会を開設し、憲法を制定しようという運動が盛んになった時期でもある。「私擬憲法」と呼ばれる民間発の憲法草案も多く作成された。東京の多摩地域でも「五日市憲法」と呼ばれる憲法草案が1968年に民家の土蔵で発見されている。
歴史小説といえば歴史上の人物が主人公となるのが一般的である(捕物帳などのような、いわゆる「探偵小説」的なものは除く)が、この小説では庶民が主人公となっている。富山の薬売りは全国でも有名だが、小説の主人公となったのは稀だろう。
弥一は、もともと政治に関心があったわけではない。また政治に大きな影響を与える立場でもない。しかし政治に無関心ということではなく、世情を見ながらの行動をしている。いや、仕事の都合上、政治に関心を持たざるを得ないといった方が正しい。
幕府や諸藩が情報統制をするなかで、正確な情報をいかに選びとれるか。情報リテラシーの大事さについても描かれている。ネタ元はどこか。何のために流されたのか。複数の情報を比べてみたか。いつの情報か。などなど。弥一たちの商売にとっても正確な情報を得られるかどうかは死活問題なので、ひとつの事件に対していくつもの情報を集めている。情報に対するそうした姿勢は、時代を問わず重要である。
作中で紹介される素朴な料理も魅力的である。池波正太郎ばりとまではいかないかもしれないが、味わってみたくなる(第2巻148ページなど)。たとえば「じゃこ入りの味噌汁をかけた飯をかきこみ……」(第2巻196ページ)というくだりを読んだときには、思わず即席の味噌汁にじゃこを入れて、炊飯器に残っていた冷や飯を加えて、まさに「かきこ」むように食した。これが実に美味かった。余分なカロリーを摂ってしまったという後悔もあったが、小説中の一場面に加われたような気持ちにもなった。
弥一は仕事の関係で薬の原料など、流通の事情を知るようになった。他にも富山に集まる食材の流通経路などにも触れられている。富山は富山だけで成り立っているのではなく、多くの地域と関わりをもっていたことが分かる。さらに日本全体をみても、外国との付き合いが限定されていたと思われがちの当時の日本ですら、外国との関わりがあってこそ人々の生活が成り立っていたということも分かる。まさに人生地理学的な考察である。
ネタバレになることは避けたいので、本書のあらすじを全て追うことはしないし、もともと本稿の限られた字数では不可能なことである。代わりにというわけではないが、本書に一貫して流れているテーマらしき言葉を紹介する。それは「才ではない。大きな心だ」(第1巻102ページ、227ページなど)という言葉である。時代の変革期には特に大事になってくることだと思う。
登場人物が多いのは、作品を丁寧に描きこんでいるからだろう。私は人物の相関図を作って楽しんでいたが、各巻の巻末には「主要登場人物」のリストがあるので、参照してほしい。
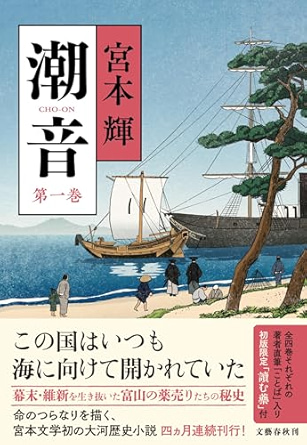
潮音 第一巻
著 者: 宮本輝
出版社: 文藝春秋 (2025/1/20)
ISBN : 978-4163919362
文 庫: 488頁
価 格: 2,200円+税
※潮音 第四巻まで出版
学修支援だより【2025年7月号】
学修支援だより【2025年7月号】
Foreword
50年の歩みと未来への飛躍――経済経営学部ビジネス学科の誕生
経営学部長 吉元 浩二
通信教育部には、年齢や国籍、職業を超えて、全国はもとより世界各地から多くの通教生が入学し、学びに挑戦されていると伺っております。その真摯な姿勢に、私たち教職員も大いに励まされております。
創価大学の通信教育部・経済学部は、1976年の開設以来、実に50年近くにわたり多くの学びの志士たちを送り出してきた、本学通信教育の礎とも言える学部です。そして2026年、いよいよ本学通教部において新たな進化を遂げます。これまでの経済学科に加えて、通学課程で人気の高い経営学部を統合し、「経済経営学部ビジネス学科」として新たなスタートを切ることになりました。
この新学部の誕生により、理論的思考を磨く経済学と、実践的課題に挑む経営学が融合し、社会やビジネスの現場で求められる「問題解決能力」と「論理的思考力」の両面を兼ね備えた人材の育成が可能となります。現代社会は「VUCA(不確実・不安定・複雑・曖昧)」と呼ばれる時代に突入し、組織における意思決定力、柔軟な対応力、そして創造的なマネジメント力が求められています。まさにそのような時代に応える学びとして、経営学の追加は大きな意義を持つと考えています。
2025年度からは、工業簿記、マーケティング、人的資源管理論、環境経済学といった科目が加わり、2026年度からは通学部で提供されていた多くの経営学の重要科目が、通信教育でも学べるようになります。これにより、通学の制約を超え、社会人として働きながらでも、より専門的かつ実用的な知識の習得が可能になります。
さらに本学では、創立者・池田大作先生の哲学を根幹に据えた「人間主義経済」「人間主義経営」という、世界でも類を見ない教育理念を学ぶことができます。「人間を中心に据え、社会に必要な価値を創造し、他者に貢献する人材」の育成は、創立者が一貫して示されてきた教育の原点です。
私自身、この学部改編の構想段階から関わる機会をいただきましたが、何よりも意義深いと感じるのは、「リスキリング(学び直し)」という社会的要請に、通信教育部ならではの柔軟性と多様性で応えることができるという点です。変化の激しい現代において、①環境変化に対応する力、②キャリアアップや転職に生きる知識、③そして学び直しが世界標準となりつつある今、「継続的な学び」は社会人にとって新たな常識となりつつあります。
池田先生はかつて、「ビジネスが平和構築のために貢献をなそうとするならば、「人間の論理」 のもとにリードせねばならない」と語られました。私たちはこの精神を体現し、社会に貢献する人材の育成を通じて、持続可能で幸福な社会の実現に貢献してまいります。
これからも、通信教育部・経済経営学部は、全ての学び手の挑戦を応援し、「世界市民」の育成に尽力してまいります。

教職指導講座
教員採用試験第二次試験に向けて
教職キャリアセンター指導講師 町田 千恵美
~自信をもって伝えられるものは何か~
いよいよ教員採用第二次試験に向けて、皆さんも様々な準備に取り組まれていることでしょう。なかでも、面接対策は、自分が教員になる!との決意を固め、これまでの経験を存分に生かして『教師としての資質を見つめ、鍛える最大のチャンス』です。
昨年も7月から8月に通信教育部での教員採用試験二次対策講座が実施されました。担当講師として皆さんと模擬練習をした際、一番多くお伝えした言葉は『もったいないですよ!』でした。面接対策講座の最初は、「自分の考えをどのように間違えずに話すか」という点を意識しすぎて、自信のない様子となったり、ぎこちない話し方となったりする場面が多く、お互いに不安感でいっぱいのスタートでした。面接対策は『話し方の練習』ではありません。
しかし、その後、お一人お一人にじっくりお話を伺うと、日々挑戦されている職場での経験や成果、教職を目指すきっかけとなった出会いや目標、具体的に実践されていることなど、その方ならではの良さや強みが次々と語られ、本当に素晴らしい内容ばかりでした。例えば、IT企業に勤めていた方で、企業の学校ボランティアでパソコン講師として授業に参画、子供たちとよりよい授業を目指して創意工夫に取り組んだ体験や、お子さんの学校PTA活動で配慮を必要とする児童が安心できるようイベントを立ち上げ、サポートに取り組まれた経験など、すべてその人らしさが伝わってくるエピソードです。
「その内容をお話しにならないともったいない」とお伝えしたところ「こんなことは、誰でもやっているから、大したことではありません」「当たり前だと思っていました」との声も多く聞かれました。ご自分が意識していなくても、実は、周りの人から見ると当たり前ではない、素晴らしいその人の実践や強み、長所であると、この機会を通して自分自身を再発見されることも面接対策で大切なことではではないでしょうか。
教員採用試験では、企画力、コミュニケーション力、多様な専門性など、民間企業でも求められる力や人間性が重視されています。また現時点での授業力や子供を見取る力など、教育実習期間の経験や学びについて問われる場面も多くあります。
まさに、面接は、それぞれが大切にしたい価値観や実践内容、そして自身の強みについて経験を通して伝えられる絶好の機会です。具体的な体験をもとに一番説得力をもって面接官に伝えられることは何か、しっかりと自分の言葉で伝えられるよう、自分の「経験」や、「記憶」を「記録」としてしっかりと見える化し、準備をしておきましょう。
記録に残そう(経験の見える化)
・なぜ教師を目指すのか(体験や出会い)
・自分の長所・短所
・教職に生かせる自分の良さ
・職場等で努力したこと、努力していること
・教職に活かせる成果、取り組み
・失敗や困難をどのように乗り越えたか
・教育実習で学んだこと(授業、子供たちとの関わり、チーム学校など)
・自身の教職への思い、教師として大切にしたいこと、
〇どの内容でも、自分が伝えたいキーワードを決めておきましょう!
・自治体研究をしっかりと(受験する自治体への理解は必須)
・教育目標・理念・方策 ・目指す教師像、求める教師像
・自治体の「教育振興基本計画」 ・自治体の「教育に関する大綱」
・自治体の「いじめ防止基本方針」・自治体の「人権教育基本方針」
・自治体とのこれまでの関わり ・自治体の印象、魅力
・生徒指導(児童生徒理解)
・いじめ、不登校、配慮の必要な児童生徒への対応 ・安心安全な教育環境づくり
・ 教育課題について自分の考えをもとう
現在の教育現場には、学びの多様化、インクルーシブ教育、情報活用、チーム学校、学校における働き方改革などをはじめ取り組むべき様々な課題があります。今日的な教育課題について、昨年度、採用試験に合格されたSさんは、教育実習での子供たちとの関わり、指導担当教員から学んだこと、学校現場の悩みや課題を振り返り、これらの実践を整理し、教育課題についての自分の考えをまとめていきました。具体的な事例を通し、自分の言葉で面接の場面で伝えることができるよう取り組まれ、「自分が納得する言葉や表現ができるように」と最後まで準備をされていた姿が強く印象に残っています。経験を通して得たことを書き留めておくと大変参考になります。
・つながりを大切に
面接対策は、一人では難しいことが多いです。自分の良さよりもマイナス面ばかりが気になると行き詰ってしまいます。実際の面接場面での表情や話し方など、自分では気づかないことも、たくさんあります。ぜひ、家族をはじめ職場の友人・上司、通教の仲間、教職キャリアセンター講師など、たくさんの方の応援を得て、目指すゴールに向かって挑戦していきましょう。
また、地元の実習校でお世話になった先生方との出会いやつながりも大切にして頂きたいと思います。今後も、教員採用試験に向けての相談など、力強い応援団になってくださる方々です。
昨年度の教員採用試験でも、50代の方も含めた多くの通教生が見事、合格を勝ち取られました。年齢や経験の有無で合否は決まりません。通教生のみなさんが、どのような厳しい状況の中でも目標を達成しようとする姿勢、体験に勝るものはありません。自分はこうやって勝った、と通教生の最強のネットワークで、皆で励ましあいながら挑戦してまいりましょう。今年も7月から教員採用試験二次対策講座が実施されますので、大いに活用してください。教職キャリアセンター一同、これからも皆さんの応援団として、ともに頑張ってまいります。

自立学習入門講座79
『「健康・医療心理学」を学ぶために』
教育学部教授 遠藤 幸彦
1. はじめに
私たちの人生において、健康で幸福な生活を求めることは大きな目的ともいえるでしょう。WHО憲章にもあるように、健康とは身体的、精神的、社会的ウェルビーイングの状態、それらが十分に満たされた状態と考えられます。それを支えるものとして、保健医療、福祉、教育、司法、産業などのさまざまな領域の活動があり、それぞれが大きな役割を果しています。本年度から開講された「健康・医療心理学」では、心身の健康と不調に関わるさまざまな問題について、主に保健医療領域での活動に必要な知識を学ぶものです。また、その知識は他の領域においても役立つものとなります。そして、生老病死という私たちが避けて通れない問題にも通じるテーマを思索する機会ともなるかもしれません。
本稿では、「健康・医療心理学」で学ぶことの中から、「メンタルヘルス」と「生物-心理-社会モデル」という2つのキーワードを選び、臨床的な視点を踏まえて解説いたします。ここで、その全体像を説明するものではありませんが、基本となる概念ですので学びを進めていく上での一助としてください。
2.メンタルヘルスについて
本学の創立者池田大作先生は、早くから心身両面にわたる健康の重要性に着目し、心の豊かさや強さについて論じられてきました。すなわち、1970年代当時の「健康不安時代」と呼ばれた風潮について、現代人の過度のストレスやこころの病などの背後にある現代文明、現代社会の人間疎外の問題を取り上げ、精神的な健康の確立の意義を指摘されています。これは、今日でいうメンタルヘルスの意義を多角的な視点からとらえ、予防的な観点をも視野に入れた提言ともいえます。
わが国では2000年前後の自殺者の増加に伴い、特にメンタルヘルスへの取り組みの重要性が強く認識され、2006年には「自殺対策基本法」が制定されました。そして、保健医療領域その他のさまざまな領域の連携による取り組みが推進されてきました。その問題の背景にある、精神疾患の存在や失業などの経済的要因の影響などについての認識が広まり、うつ病などの治療体制の充実やリワーク・プログラムなどの復職支援、経済対策、自殺予防教育などの取り組みが行われています。その他、ひきこもり問題、アルコール依存症などの嗜癖問題、母子保健などのさまざまな課題についても、予防や治療などの包括的な取り組みが推進されています。
その一方で、精神的な問題を抱えることは、心の弱さであるとか、気の持ちようであるなどと単純化して捉えられる傾向もいまだ存在します。また、本人の意志や努力次第で解決できるものと軽く考えられていたり、誤解されていることもあるようです。そのため、精神科を受診したり、その他の支援機関に相談することがためらわれる場合もあります。たとえば、病院を受診してきた方に、「いつから具合が悪かったのですか?」と尋ねてみると、「何年も前からです」といった答えが返ってくることも少なくありません。あるいは、いつまで通院するのか、と周りの人からたしなめられたり、服薬は体に良くない、と言われることもあるようです。それぞれの事情もあるとは思いますが、そこにも何かの誤解が潜んでいるかもしれません。
ところで、うつ病の人に接する際の心がけのひとつとして、「がんばれと言ってはいけない」ということがいわれているのをご存じの方も多いと思います。うつ病になってしまったのは頑張りが足りないからだという誤解や偏見があると、うつ病で元気のない人に「がんばれ」と言ってしまうかもしれません。あるいは、そうしたことは誤解であると頭でわかっていても、身近な人がうつ病で元気がなさそうにしているのをみると、ついつい「がんばれ」と声をかけたくなるかもしれません。しかし、そう言われた本人は、頑張りが足りないのだと自分を責めてしまうこともあります。しかし、実際には頑張りすぎたために不調に陥っている人も少なくありません。そういう人には、「がんばってきましたね」という言葉こそがふさわしい励ましともなります。あるいは、希望を失っている状態の時には、「必ず良くなりますよ」という温かな励ましの言葉が必要なのかもしれません。さらに気をつけなければいけないのは、「がんばれと言ってはいけない」という原則が、いつの間にか「励ましてはいけない」という意味に誤解されている場合があることです。そのような場合、励まさない、放っておく、という態度につながることもあります。しかし、うつ病とはどのような病気であるのかを正しく理解することによって、上に述べたように、その人にふさわしい励ましや配慮に思い至ることもあるものです。
このように、メンタルヘルスについて学んでいくなかで、思わぬところに誤解や偏見があることに気づいたり、常識と思っていたことを考え直すこともあるかもしれません。それらは、当事者の方たちへの支援を考えるうえでの一助にもなるでしょう。そして、メンタルヘルスの課題や取り組みを理解することは、「健康・医療心理学」を学ぶ意義の一つであると思います。
3.生物―心理―社会(Bio-Psycho-Social:BPS)モデルについて
精神科医のジョージ・エンゲルによれば、人間には生物的側面・心理的側面、社会的側面が相互に影響しているとされます。そして、不適応や疾病なども、これらの3つの側面の相互作用としてあらわれるものと捉えられ、「生物―心理―社会モデル」が提唱されました。
例えば、中学生の子供は、思春期を迎え第二次性徴という生物学的な変化を迎えています。そして、親離れ・反抗期という心理的な発達課題に取り組み始めます。また、社会的にはとても身近な場所にあった小学校を卒業し、より広いコミュニティからの生徒が集まる中学校に通うことになります。このことは「社会」との関係の変化につながる意味を持ちます。このように、「生物―心理―社会的モデル」という視点にたつことで、一人ひとりの持つ多様性を包括的に理解しつつ、そこに生じている課題に対して、さまざまな具体的な取り組みを考えていくことにつながります。
また、マイク・オリバーらによる障害の「社会モデル」という視点も重要です。従来、「個人モデル」あるいは「医学モデル」と呼ばれる立場から、障害は個人の問題として捉えられ、治療やリハビリテーションへの取り組みも、自己責任によるものと位置づけられていました。それに対して、「社会モデル」においては、障害を個人の問題と捉えるのではなく、社会に存在する障壁との間に生じる問題と捉える視点が特徴です。そして、インクルージョンの理念が広まり、合理的配慮などの取り組みが推進されるようになりました。
ここで架空の男子大学生Aさんを例にして解説してみましょう。
| 高校時代のAさんは真面目な努力家で成績も上位だった。志望大学に合格して他県での一人暮らしを始めた。入学後、周囲の学生が、サークル活動やアルバイトなどの話題で仲間を作り始める中、なかなか仲間の輪に入れなかった。1人授業を受けて下宿に戻るという生活が続き、孤立感を深めていった。やがて気分が重くなり、食欲もなくなり、授業を休んで部屋で寝ているようになった。両親からは時折連絡があったが、心配をかけてはいけないと思い、そうした状況を相談してはいなかった。入学時からAさんの担当となっていた教員は、教務課からの連絡を受けて欠席が多いことに気がついた。 |
さて、Aさんの欠席が続いていることに気がついた教員は、どのような対処ができるでしょうか?まずは、Aさんと面談をして状況を確認したいところです。面談によって、その生活状況や心身の状態などを話し合い、うつ病などの疑いがあるようなら、大学の保健室へ相談に行くことを勧めた方が良いかもしれません。保健室は、「生物ー心理ー社会」の中の「生物」の側面をつかさどる役割があります。そこで、本格的な治療が必要と判断されれば、保健室から大学外の医療機関やその他の相談機関へ紹介されることになるでしょう。また、何らかの障害の可能性があれば、障害学生のための相談窓口で相談し合理的配慮の申請など学修上の支援を受けられる場合もあります。あるいは、そこまでの状態ではなく、対人関係の問題としての解決できるものと判断されれば、学内の学生相談室でカウンセラーと話をするようにと勧められるかもしれません。学生相談室は「心理」の面から支援を行う部署です。その他、教育面での支援を行っている部署での相談も併せておこなうことが役に立つ場合もあるでしょう。
ただし、いずれの場合でも、そうした窓口に自分で相談に行けるかどうかという問題があります。必要な人に必要な支援が届くかどうかということは、しばしば課題となることです。そのため、場合によっては相談窓口まで誰かが同行した方が良いかもしれません。あるいは、ちゃんと相談に行けたのか、その後のフォローアップも大切な配慮の一つとも考えられます。また、休みが続いたことによって、必要な手続きができずに困っているかもしれません。そうした場合、欠席に気がついた教員が各部署に連絡をしたり、精神保健福祉士などの資格を持ったキャンパス・ソーシャル・ワーカーと呼ばれる立場の人が支援をしたり、各部署との連携を行うことが必要です。これらは、Aさんの生活する大学という環境、すなわち「社会」的な側面からの支援ともいえるでしょう。しかし、そもそもAさんはそうした相談のために大学に来ることすらできないかもしれません。そのような場合にはオンラインでの相談も考慮したり、原則的に本人の了解に基づいて各部署が連携して専門的な知見を共有しつつ、学内外の専門機関の活用や家族の協力などを含めて対応していくことが大切です。
以上、架空の事例をもとに「生物―心理―社会的モデル」について解説しました。そこでは、包括的な評価がなされ、対応が検討されることになります。特に複雑な課題を抱えた事例であるほど、こうした基本的な枠組みは、寄って立つ基盤として重要な意味を持ちます。それにより、多職種が連携して1人の人を理解し、具体的な取り組みとして障害の社会モデルが提示するようなさまざまな支援をおこなうことが可能となります。
ただし、社会の中でこうした取り組みが始まってから、まだ日も浅いのが現実です。実際の現場では、こうした制度の整備状況、人員配置、連携の課題などさまざまな事情があり、思うような支援、効果的な支援が提供できない場合もあるでしょう。そのため、近年では合理的な配慮を提供する側の課題によって、そこに障壁が生まれるという問題も指摘されています。また、さまざまな支援があっても、それが必要な人に届かないというジレンマがあることも、支援の現場ではしばしば問題となることです。そうした課題などから、いわゆる伴走型の支援というあり方も重視されています。
他方で、近年では「生物―心理―社会」モデルに対する批判も提出されています。たとえば、生物、心理、社会という側面の統合や、その本質についての理解の深化も求められています。ところで、架空の事例Aさんでは、その支援はあくまでそこに介在する「人」の関わりと関係者の連携であることを示しました。そうした「人」の存在があってこそ、いろいろな支援のための組織が協力することが可能となり、3つの領域の連携や統合も初めて実際に可能となるものと言えます。また、どのようなモデルであれ、その実践にあたっては、「人」の存在や役割を抜きに考えることはできません。そうした現場の活動を考えていくためにも、一人ひとりが「健康・医療心理学」について学ぶことが大切であると思います。
4.結びにかえて
以上、「メンタルヘルス」と「生物―心理―社会モデル」について解説しました。「健康・医療心理学」で学ぶことがらには、その他とても幅広い領域が含まれています。それらは私たちの日常生活にも大きな関わりのあるものや、社会的な関心を呼ぶ話題などの大きなテーマにも及びます。そうした学びを通して、身近なことから社会的課題に至るまで、自分なりに考え、主体的な意見を持つための基礎を作ることを期待しています。
参考資料
1)厚生労働省:わが国における自殺の現状と自殺対策についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001283310.pdf
2)障害学 理論形成と射程:杉野昭博 東京大学出版会 2007.

学修支援だより【2025年6月号】
学修支援だより【2025年6月号】
Foreword
夏期スクーリングを迎えて
通信教育部長 吉川 成司
~ 人生のヴェールを開きゆく学の光 ~
何よりもまず、職場や家庭でさらに地域でお忙しくされながらも、たゆみなく勉学の歩みを進めておられる通教生の皆さんに最大の敬意を表したいと思います。
さて、昨年度の夏期スクーリングは記録的な猛暑でしたが、参加された通教生の皆さんは、異口同音に対面での授業や友人との交流に喜びを語っておられました。
対面授業にはオンライン授業にはない臨場感があります。ある時は真剣な知的触発があり、またある時には和気に満ちた雰囲気を直接体験し共有できます。今年も、燦々たる夏空のもと、創価大学の広々としたキャンパスで、日本中、世界各地から集う同学の友と、充実した学び合い、触れ合いの思い出を刻んでいただきたいと思います。
来年の2026年は通信教育部開設50周年の佳節であり、創価大学全体の学部改組に伴い、新たに経済経営学部が立ち上がります。そのほか法学部、教育学部、文学部もリニューアルされます。次の新しき50年に向けて力強い助走が始まっています。
さて、今から20年前の2005年5月、創立者は通教開設30周年を記念して、「『生涯学光』の心で勝利の人生を!」と題するメッセージを寄せてくださいました(『学光』350号掲載)。そのなかで、19世紀のイギリスの思想家・ジョン・ラスキン(1819‐1900)の言葉が紹介されています。「大胆にヴェールをあげよ。光を正視せよ」と。この言葉は、産業革命後の新たな時代を展望し本質的な価値とは何かを論じた、『この最後の者にも』のなかで語られているものです。続けて創立者は、「希望の光を、まっすぐに見つめながら、わが人生のヴェールを大きく開いていってください。皆さまの勝利の輝きこそが、創価教育の『勝利』であり『光』なのであります」と、万感こもる励ましを送ってくださっています。
暑さ厳しき折、参加される皆さんにおかれましては体調管理にくれぐれもご留意ください。お一人お一人の人生においてかけがえのない貴重な学びの機会になりますようにお祈りいたします。

学修支援推進室コーナー
レポート作成講義【入門タイプ】を担当して
通信教育部教授 坂本 幹雄
レポート作成講義・入門タイプを担当して、毎回、必ず強調している点が2つあります。1つは項目別評価の重視、もう1つはパラグラフ・ライティング、トピック・センテンス・メソッドです。以下順番に述べていきます。
項目別評価
項目別評価は、「課題把握」、「教材理解」、「論理構成」、および「原稿作法・文章作法」の4項目からなります。心を込めて少し敷衍すると「課題の的確な把握」、「教材内容の正確な理解」、「明解な論理構成」、および「読みやすくていねいな原稿作法・文章作法」といった感じでしょうか。以下、順番に見ていきましょう。
課題把握は、スタート地点、進路および目的地の明示を要求しています。課題把握の基本は、学習の対象範囲と出題者の指示・要求をとらえることです。そのために『レポート課題解説』を必ず確認しましょう。テキストの第〇〇章等、学習すべき個所が明示されているはずです。次に何を指示しているのか、何を要求しているのか、述語・動詞に注目してみましょう。そうすると基本的に何をすればよいかがわかります。
出題者の指示について、いまここで仮説的に「述べよ」「説明せよ」「論ぜよ」の3本の柱を立てます。3つのちがいを自分の意見・見解の有無から確認してみましょう。「述べよ」は、テーマについて文章があればよいでしょう。自分の意見・見解の有無は『レポート課題解説』を確認しましょう。「説明せよ」は、テーマが理解できたことを明示できればよく、自分の意見・見解を入れないようにします。テーマについて基本的理解が求められているだけです。そして「論ぜよ」は、テーマを理解したうえで、明確な根拠・理由をもって、推論・導出し結論を示さなければなりません。「論ぜよ」は、基本的に「論証」を求めていて、水準の高い課題といえましょう。ここで「述べよ」について、繰り返すとこの「述べよ」が「説明せよ」か「論ぜよ」なのかは『レポート課題解説』を確認しましょう。
まず教材理解にはテキストの性格・性質を理解していることが大きく影響してきます。テキストは基礎を踏まえて応用というように、体系性があります。この全体像を把握することが求められるでしょう。またテキスト=学術書には、日常生活では使わないような専門用語があります。あるいは同一語でも専門用語と日常語が異なる意味の場合もあります。科目特性・学問分野独特の形式を把握できているかが問われます。著者の個性をとらえることも重要かもしれません。
さて教材理解に向けた学習法の一例を示しましょう。以下に示すようにテキスト(出題範囲)を最低4~5回は読むことになります。
(1)テキスト全体を1回は通読している(最低限、シラバス記載の個所は読みましょう)。
これを前提として以下出題範囲のみの読みからスタートします。
(2)全体像を把握するよう心がけて1回通読する。
以下は自分に合った方法でアンダーラインを引く、マーキングをするなどしながら読みましょう。
(3)もう1回読んで、わからない語句を調べる。
(4)キーワードを把握するように読む。見出しや索引も活用できるかもしれません。経済学の例で恐縮ですが、限界費用と平均費用がキーワードの場合、両者の関連を把握することも重要です。
(3)と(4)は合わせてもよいでしょう。以下は書く作業に入ります。
(5)各パラグラフのトピック・センテンス(後述)または中心的な主張と考えられる個所を把握するように読む。これを書き出してみましょう。
(6)各パラグラフの内容を自分なりのことばで言い換え・パラフレーズ・敷衍して書いていきましょう(ただし意味が変わらないように注意しましょう)。
教材内容が理解できたかどうか、レポートがひとまず書けたら、文意が通っているかどうか、必ず読み直しましょう。自問自答しながら読み直しましょう(機会があればレポートを手控えに他者への説明も有効でしょう)。音読も推奨いたします。
論理構成の基本中の基本は、まずしっかりとした1つの文(センテンス)を作ることです。主部と述部、主語と動詞を確認しましょう。主語+目的語+動詞いわゆるSOVは必ず確認しましょう。さらに論理構成については後述のパラグラフ・ライティングの個所で説明します。
原稿作法・文章作法については、読みやすさを重視しています。誤字・脱字、表記、語調等をチェックしましょう。
パラグラフ・ライティング
まずパラグラフの構造を理解しましょう。パラグラフとは、ひとまとまりの内容を持った文(センテンス)の集合を言います。1つのパラグラフに1つのアイデアとなります。パラグラフの表示は、行頭1文字分下げるという点で、「段落」と同じですが概念がちがいます。
1つのパラグラフは、1つのトピック・センテンスとサポーティング・センテンス(サブ・センテンス)(群)から成り立っています。なおこの2つのほかに接続文(進行文・連結文)があります。
トピック・センテンスとは、主題文・論題文・題目文・中心文・主要文・要約文等、要は中心アイデアを明示した文です。1つのパラグラフには、1つのトピック・センテンスとなっています。
サポーティング・センテンスは、支持文・補強文・補足文等です。サポーティング・センテンスの内容は、素材の要請に応じて様々でしょう。意味、証拠、事例、前後関係、因果関係、相関関係、目的手段関係等々。
トピック・センテンス・メソッド
まずレポート作成の構想を立てましょう。メモ・スケッチをしましょう。そしてアウトライン・基本設計図へと進みましょう。こうして全体像を組み立てます。基本設計図には主要論点・骨格・柱がいくつかあるはずです。それがトピック・センテンスになっていく可能性が高いはずです。素材の要求に対応してトピック・センテンスを何にするのかじっくりと考えてみましょう。
トピック・センテンスの見通しが立ったらパラグラフを作っていきましょう。書きやすいパラグラフから作っていってもよいでしょう。
最後にトピック・センテンス・メソッドによる良きレポートの完成を願い、ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
参考文献
坂本幹雄2019「レポートの評価基準について―「項目別評価」の観点から考えてみよう―」吉川成司・平井康章編『自立学習入門 新訂第2版』(43-80)所収、創価大学通信教育部。

ブック・スクウェア
『シン読解力』
通信教育部教授 山本 忠行
著者は現在、国立情報学研究所社会共有知研究センター長を務めています。もともと数学者であり、人工知能や教育工学の研究をしている人物です。著者が2018年に出した『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』という本は、内容の固さにかかわらず30万部以上を売り上げて、2019年度のビジネス書大賞を受賞しました。その後も読解力やAI(人工知能)の問題について積極的に執筆活動を続けています。2018年の本ではAIの可能性を探ることを目的とする「東ロボくん」プロジェクト、AIが東京大学の入試を突破できるかという試行錯誤のノウハウを応用して開発したリーディングスキル測定テストをもとに大規模な日本人の「読解力」調査と分析を行い、今の子どもたちが教科書の文章を理解できていないことを明らかにし、読解力を鍛えないと、AIに仕事を奪われると警告したことで、社会に衝撃を与えました。
今回紹介する『シン読解力』はChatGPTという生成AIの登場をきっかけに執筆されたものです。7年前には「東ロボくん」では不可能としてあきらめていた課題をやすやすとこなしてしまうChatGPTにショックを受けた著者は、生成AIにさまざまな試験問題を解かせてみます。すると、さまざまなことがわかってきます。
たとえば、7年前には画像を選ばせるような試験問題が出るとお手上げだったのに、今は簡単に正答を選ぶことができます。著者はこの結果に「あ然、ぼう然」だったと言います。さらに画像認識技術は医療にも応用され、人間以上に正確な診断ができるようになってきました。しかし、気をつけなければなりません。それは「平気でウソをつく」ということです。600字でトルキスタンの歴史的展開を述べよという問題を与えたところ、一見するとそれなりにまとまった文章がでてきたと言います。しかしながら、この解答をある予備校の先生に採点してもらったら、何と0点だったそうです。そのコメントの一部は「得点を与えられる箇所がありません。一見すると日本語がそれなりに自然で、それっぽい答案になっていますが、よくよく読んでみると、史実の指摘がありません。ほら吹きです」と書いてあったのです。
生成AIは、すでにいろいろなところで利用されています。会社や企業で使っているところもあるでしょう。英語で論文を書くときに便利な道具として利用している学者もいます。AIが創り出したものに、著作権があるのかどうかも議論されています。その便利さに頼り過ぎると、人間が怠惰になったり、予想しない問題に直面するおそれもあります。重要なのは、どうやって上手につきあうかになります。
なぜ、AIがとんでもない文章を生成してしまうのかというと、膨大なデータを統計処理、確率計算しているだけであり、意味は理解していないからです。問われたことに対する良質のデータを読み込んでいなければ、それ以外のデータをもとに、もっともらしい文章を出力します。読み込んだデータにウソが混じっていれば、出てくるものはウソに基づくものになります。
AIはウソか、真実かを検証できません。というのは、物事の真偽判断というのは単純ではないからです。「今日は雨が降っています」という文が正しいかどうか、文だけでは判断できません。「田中さんはアメリカへ留学したことがあります」という文が正しいかどうかは、「田中さん」がどういう人かを知っている人にしか分かりません。生成AIは大量のデータから自然な言語を生成するように作られていますが、AIに真偽判断能力を求めることはできないのです。したがって、真実性を見極めるのは、利用者の責任となります。
また、AIには「外れ値の罠」が潜んでいると著者は言います。AIは収集したデータを統計処理しています。データが正規分布しているとして、一般に利用されるのは偏差値が30~70ぐらいの範囲です。どんなに頑張っても20~80までです。この範囲から逸脱するのは0.3%ほどになるわけですが、めったに発生しないこの部分への対策を無理に考慮しようとすれば、全体の精度を下げてしまうことになるので、非現実的です。これが「外れ値」です。これはあらゆる事象にあてはまります。自動運転が急速に実用化されつつありますが、事故をゼロにすることはできないと言われます。現実世界では、確率は低くても予測していないことが起きることは避けられません。
この本の書名は『シン読解力』となっています。なぜ「シン」なのでしょうか。これは前作が誤解を受けたからだといいます。著者が「読解力」としているのは、文芸や評論を読む力ではありません。読めばわかるはずの平易な文章、知識や情報を伝達する文章を正確に読み取る力です。これはAIが生成する文の大半が該当するからです。これからの時代はさまざまな仕事でAIをどう使いこなすかが問われることは間違いないでしょう。AIは仕事の時間短縮、効率化につながるはずですが、AIの落とし穴に翻弄されない力を身につけるにはどうすればよいかを論じた本です。
著者:新井 紀子
『シン読解力』
ISBN:978-4492762677
出版社:東洋経済新報社
文庫:296頁
本体1,800円+税

学修支援だより【2025年5月号】
学修支援だより【2025年5月号】
Forward
尊厳について考える
副学長・経済学部長 西浦昭雄
数年前、古くからの友人から薦められた本にドナ・ヒックス著『Dignity』(ワークス淑悦訳、幻冬舎、2020年)があります。Dignityは、一般的に「尊厳」と訳されます。
この尊厳について、「世界人権宣言」は第一条において「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」(国際連合広報センター)と謳っています。SDGs(持続可能な開発目標)においても、すべての人々の尊厳は重視されています。
さて、同書の中でヒックスは、「尊厳とはどのようなものか、例を挙げて説明してください」と問いかけるとほとんどの場合、会話が止まるというエピソードを紹介しながら、尊厳と尊敬は違うことを指摘しています。そして、「もし周りにいる私たちが、そんな子どもたちが成人へと成長していく過程でも、この尊厳というひとつの真理を手離さず大切に育み続けることさえできたなら、もしすべての人間に備わっている生来の価値を感じ続けることさえできたなら、もっと当たり前のように子どもたちを大切に扱い、傷つかないよう彼らを守ってあげられるでしょう」(26~27頁)と述べています。しかし、現実には、ロシア・ウクライナ紛争、イスラエル・パレスチナ紛争といった国際的な紛争に加え、SNSでの誹謗中傷、ヘイトスピーチ、ジェンダー差別など、日常の中で尊厳が傷つけられる場面が後を絶ちません。このような状況だからこそ、尊厳の大切さを学び、自覚する教育が不可欠だと考えます。
創価一貫教育のミッションステートメントには、「生命の絶対的尊厳を基調とした人間主義」が掲げられています。また、創大には、「人類の平和を守るフォートレス(要塞)たれ」という「建学の精神」があります。生涯教育を掲げる創大通教は、尊厳という普遍的価値を社会に広げていく上で、ますます重要な役割を担うことになるでしょう。私たち一人ひとりが尊厳について深く考え、行動することで、誰もが安心して暮らせる社会を実現できると信じています。

教職指導講座
今年の教員採用試験に向けて
教職キャリアセンター指導講師 小堂 十
今、大切なこと 「教育の使命」
創大創立時に2体のブロンズ像が創立者より寄贈され、その台座それぞれに言葉が刻まれています。
「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」
「労苦と使命の中にのみ 人生の価値(たから)は生まれる」
この言葉に何度励まされたことでしょうか。私自身も、通信教育での教員免許取得を目指し、アルバイトと勉学の日々の生活の中、時に暗澹たる気持ちになることがありました。そんな時、冒頭の言葉を思い浮かべ、自分自身を奮い立たせたものです。
ここ数年、教員の仕事に対しブラックや働き方改革の遅れ等、批判的な声が高まる中、教員不足の問題が全国で続出しています。大学や私の許にも関係者から連日SOSの声が届きます。
最近、友人や地域の人と教育の仕事に携わっていることを話すと、以前は「大切なお仕事ですね。頑張ってください。」と称賛と励ましの声をかけていただいたのが、今は「大変なお仕事ですね。お体を大切に。」という憐れみと励ましにも似た言葉が返ってきます。確かに教職は大切でも大変な仕事でもあります。
しかし、教育の目的やそれに携わる教職としての使命は、基本的には変わりません。教育とは「何のため」か。それは、個人と社会すべての人々の幸福(ウェルビーイング)のため。教職は「何のため」か。それは、子供たちとの日々の関わりを通じて一人一人の可能性を引き出すため。その目的や使命は何と崇高なものであり、人を育て地球の未来を築く生き甲斐のある仕事です。これは、日本の未来に留まらず、平和な世界を築いていく大きな力になります。その尊き使命感を胸に抱き、みなさんが日々の学修に取り組まれることに最敬礼するばかりです。
時代を読み解き、相手を知る
2025年も既に5月。早い地域では今月に1次試験があるところもあります。1次試験の準備はいかがでしょうか。また、3年生での前倒し受験に挑戦する人は、短期決戦のため、かなり集中した受験対策が必要です。合否は別にしても、受験することで試験にも慣れ、悔しさを味わうことで合格へのモチベーションを高めることもできます。
様々な影響から、教員採用試験受験者低迷の傾向があるため、自治体によって教員確保に向けた取組が行われています。何をするにしても相手を知ることが大切。相手とは、自分が受験する自治体であり、そこで求められる教育目標や教師像に向き合い、自分なりの考えを明確にしていくことが大切です。出題傾向にも特徴があります。
今回は、既に1次試験が実施されているlため、「教職教養対策」に絞って、解説していきます。この勉強は1次試験対策だけでなく、次に続く面接試験対策にもつながります。そのためのポイントを整理しましたので、ご確認ください。
|
「生徒指導&特別支援教育(教育原理)」 |
① 教育原理・教育時事・法規領域とリンクした「生徒指導提要」中心に |
| 「教育時事」 |
① 国の「教育振興基本計画」 第4期教育振興基本計画 |
|
「教育法規」 |
① 教育基本法 |
|
「学習指導要領」 |
① まずは「総則」からスタート |
上記が、ここ数年の採用試験で採り上げられた出題傾向のベスト3です。これらを見ると、現在の学校現場での課題と向き合い、これに対してどのように考え、どう対応できるかの力を問われていることが分かります。教科書通りの答えとして基本的な事項はおさえたうえで、自分が現場に立った時に、どうするかを考えることで2次面接への対策にもつなげていきましょう。
創立者の池田大作先生も苦学の中で勉学にいそしんでいました。しかし、戦後の不安定な世の中、恩師である戸田城聖先生を支えるため大学を中退し、戸田大学での学びと訓練の道を選択されました。まさしく「労苦」を選んだからこそ自身の「使命」と出会い、その後の偉大なる勝利の足跡を歩まれました。
免許取得・教員採用試験合格という2つの山がみなさんの眼前にはあります。山を乗り越えるには、いろんなルートがあるように、みなさんがこの山を乗り越え方も様々かと思います。
是非、お一人お一人が今、ご自身の置かれた立場や環境を見据えた上で、持続的・計画的に進めていくことを願っています。私たち教職キャリアセンターは、そのための羅針盤になれればと日々着任しています。具体的な相談がありましたら、是非お声かけください。お待ちしています。

学修支援推進室コーナー
オンデマンドスクーリングだより➀
通信教育部 准教授 加納直幸
『グローバリー・ヒストリーとSDGsから見た貧困と開発』
本科目の日本語版教科書である『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』の著者、ロバート・C・アレン氏は「なぜ現代世界には豊かな国と貧しい国がうまれたのか?」と問いかけている。そして、その原因を歴史、制度、文化、地理的条件に加えて、技術革新、グローバル化そして経済政策の持つ歪んだ特性とその影響にこそあると強調しています。(本書P.ⅸ)さらにアレン氏の主張の基盤となっているのが“グローバル・ヒストリ―”という観点です。それは、世界に厳然と存在する“貧困と格差“を解決するためにも「いまやグローバルな存在のわれわれにとって、グローバルな視点、つまり特定の国々や地域の枠にとらわれない発想で、地球規模での歴史が語られなければならない。」(同P.ⅶ)と主張します。つまり私たちに、地球市民(global citizen)または世界市民(citizen of the world)の一員として、世界の全ての国と人々に”貧困と格差の問題“の当事者としての自覚を持つこと強く促しているといえます。
また、私たちが日常生活の中でよく耳にする「持続可能な開発目標」(SDGs : Sustainable Development Goals)は2015年9月に国連総会で採択され、2030年までの達成を目指した17つの国際目標のことです。これは2000年9月の国連ミレニアム・サミットで採択された8つのミレニアム開発目標(MDGs Millennium Development Goals)で達成されなかった目標の一部を引き継ぐ形で、2015年9月の国連サミット総会で加盟国の全会一致で採決されたものです。それは、17のゴールと169のターゲットから構成されており、日本国外務省HPの説明で二つの開発目標を比較してみると以下の通りになります
【MDGsの8つの目標】(出所:外務省HP、 (ODA) ミレニアム開発目標(MDGs) | 外務省)
【SDGsの17の目標】 (出所:外務省HP、「持続可能な開発目標」(SDGs)について)
見ての通り、MDGsよりSDGsの方が、より具体的かつグローバルな視点を取り入れ、実現可能性を高めた開発目標になっており、解決すべき課題が明快かつ具体的になっています。それは、MDGs(2001年~2015年)が国連の専門家で策定され、途上国の目標とされたのに対し、SDGs(2016年~2030年)は国連全加盟国で交渉しながら資金や技術等の実施手段を重視した上で、全ての国の目標とされたからです。
現代世界の特徴は、インターネットの利用環境さえあれば、その恩恵を受ける全ての人、企業、国家等が、情報の発信者となり、同時に受信者(受益者)ともなれるということです。このことはまた、全ての人、会社、国家等が地球全体の問題群解決の責任を負っているともいえるでしょう。一例として、もし環境や気象関係のセンサーが付いたスマートフォンを世界中に販売出来て、国連開発計画(UNDP)のような信頼できる国際機関で分析と対応策をとることができるなら、世界規模の環境と気象のセンサーのグローバル・ネットワークができます。携帯するスマートフォンが何かの異常を感知した瞬間に情報発信を行い、しかるべき機関で情報の集積と分析、そして対策の実施などが行われば、ほぼリアルタイムで様々な災害を最小化できる可能性がでてきます。もちろん、地震観測ネットや台風予想進路など、国際的なネットワーク等が既に存在しますが、もっとモニター性能を向上させたスマートフォンが普及すれば、関係する地域に住む人々にとっての危険性を最小化できる可能性がさらに高まります。アフリカ地域でいえば、降雨状況、地表温度、バッタの発生の有無、エボラ出血熱などの疫病発生等の情報発信と対策が、その時のその地域の被害を最小化し、その拡大防止に貢献できるかもしれません。つまり貧困の最小化に貢献できる可能性が出てきます。
さらに人工知能(AI)の発明で新たな格差が出現すると指摘されていますが、それは、AIを使いこなせる側(人、企業そして国家)が、使いこなせない側を政治・経済的、社会的に支配する可能性が、出現しているからです。それでは、「貧困」や「開発」の格差はどうでしょうか。収入、就業形態、所有物の有無等の物差しで計測できる「貧困」は、「開発」に比べて認識しやすいといえます。「貧困」の反対語は「裕福」だと答える人は多いでしょう。しかし、「開発」とは何かといわれて「〇〇だ。」と説明することは難しいのではないでしょうか。「開発」の反対語は「貧困」でしょうか。それとも「未開」でしょうか。その一つの答えとして「人間開発指数(HDI)」があります。これは国連開発計画(UNDP)が毎年発表するもので各国の人間開発を一人当たりの国民総所得(GNI)、平均余命、教育・識字の複合統計としてまとめたものです。これは、現在の経済的状況と、未来の豊かさを担保する識字率と教育レベルを表したものです。一言でいえば、「現在と将来の幸福を担保(保障)する指数」といってもよいかもしれません。開発とは単に貧困の削減や撲滅のことだけでは決してありません。この「持続可能な開発目標(SDGs)」は、「国連加盟国すべての開発目標」であるとされた時点で、全ての国々と人々の現在と将来の幸福のために、全ての国連加盟国が負う責任と義務であることを機会あるたびに再認識しながら、『開発と貧困の経済学』を学んでいって下さい。

学修支援だより【2025年4月号】
学修支援だより【2025年4月号】
Foreword 1
新入生歓迎挨拶
通信教育部長 吉川 成司
旺盛な探究心で学びの道への挑戦を
新入生の皆さん、創価大学通信教育部へのご入学、誠におめでとうございます。教職員一同、心から歓迎しお祝い申し上げます。
2026年にわが通教は開設50周年を迎えます。これまでの労苦と使命の礎に立ち、更なる高みを目指して共々に前進を開始してまいりましょう。
さて、今から30年前の1995年5月、通信教育部開設20周年を記念して、創立者・池田大作先生のご指導が『学光』に特別寄稿として掲載されました。創価教育の父・牧口常三郎先生がみずから苦学された経験をもとに、勉学の機会を広く提供しようと、女性への通信教育の先駆けともいえる『女学校講義録』を編纂しておられたことをふまえて、次のように励ましてくださっています。「牧口先生自身、皆さんの大先輩であり、通信教育の重要性を知っておられた大教育者であることを、どうか皆さんは誇りにも励みにもしてください」。
同特別寄稿ではさらに、後にアメリカ16代大統領となるリンカーンが、一労働者として働くさなか偶然見つけた『イギリス諸法律註解』全四巻を繰り返し学びきったことを紹介し、彼の口癖、「書物を手に入れて注意深くこれを研究しなさい。勉強せよ、勉強せよ! 勉強が第一である」を紹介してくださっています。
これらを通して、創立者は、「どうか通信教育部で学ぶ皆さんは、このまたとないチャンスに、探究心旺盛に学問に挑戦し、かけがえのない思い出をつくってください」と期待を寄せてくださっています。
通信教育部には、環境問題、データサイエンス、人生100年時代など現代的な教養に関する科目も開講されます。教職、FP、簿記、日本語教師などの資格取得を目指す方のためのコースが設けられています。そして、このような豊かな学びが自宅でできる、オンラインでの学修環境が整っています。さまざまな現実と格闘しながら、また、ときにくじけそうな心を鼓舞しながら学びゆく通教生の皆さんのご健闘を衷心よりお祈りいたします。

学修支援推進室コーナー 1
「自立学習入門講座」(78-83)の予定とその概要
学修支援推進室
通信教育部では、通教生皆さんが学習を円滑で効果的に進められるよう、授業とは別に、レポート作成を中心にさまざまなアドバイスを提供しています。
その一つが「自立学習入門講座」です。そこでまず「自立学習入門講座」の年間予定についてお知らせしますので、レポートの書き方学習の参考にしてください。
冊子としての『学光』の発行は年3回、春・夏号、秋号、冬号の3冊が予定されています。こちらにはレポート作成講義に関する内容が掲載されます。
レポート作成講義は通信教育で学ぶときの基本となるレポートの書き方に関する講座です。夏期スクーリング期間中は対面で、それ以外の期間はオンラインで開催します。『学光』の各号には、それぞれAタイプ、Bタイプ、Cタイプの内容について解説が掲載されます。レポート作成講義に参加予定の方は、受講前に読んでから参加するか、受講後に読んでいただけると、理解が深まるはずです。『講義資料』はポータルサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。Aタイプはレポートを書くための準備段階です。レポートを書くための情報をどのように読み取ればよいか、読書メモや情報カードの利用法について学びます。Bタイプではパラグラフ・ライティングの基本を学ぶとともに、論理的なレポートの構成をどのように組み立てていくのかを練習します。Cタイプでは、レポートの仕上げ段階として、説得力のあるレポートに推敲し、仕上げていく段階となります。
「自立学習入門講座」は、ポータルサイト上の「学修支援だより」でも掲載されます。
冊子とは別に、通信教育部のポータルサイトには「学修支援だより」のページが開設されその中にあります。今年度は7月、9月、1月の3回が予定されています。こちらでは通信教育部で開講されている科目に対応したレポートを書くためのポイントと注意点が示されます。7月号には「健康・医療心理学」、9月号には「国際人権法」、1月号には「株式会社簿記」が掲載される予定です(科目が変更となる場合があります)。この科目を履修している人には有益な情報となるでしょうが、履修していない人にとっても、レポートはこうやってまとめればよいのか、テキストはこうやって学ぶのか、など他の科目を学ぶときにも参考になることは間違いありません。
以上、「自立学習入門講座」が通信教育部で学ぶ方々がレポートを書くときに少しでも役立つよう担当教員も努力してまいります。
『学光』に掲載される、タイプ別のレポート作成講義は、さまざまな形態でも行っています。入門タイプを中心に4月~5月にかけて、またそれ以外のタイプについては6月~11月にかけて、リアルタイムのオンラインで実施する計画です。夏期スクーリング期間には対面でも実施する予定です。なお、ポータルサイトでは、レポート作成講義をいつでも何回でも視聴できます。このほかにも、通信教育部の専任教員全体で取り組んでいる、オンラインで行う個別の「学修相談」があります。
通信教育で学ぶ上で、もっとも課題となるのがレポート作成です。上に紹介しましたようにさまざまなサポートを用意していますので、ぜひご活用ください。
学修支援推進室コーナー 2
学修支援のための年間スケジュール
文学部 教授 髙橋 正
日々強まる日差しに春の暖かを感じる季節となりました。その暖かさに誘われて花の芽がどんどんと大きくなるように、通教生の皆様も、勉学への意欲がますます高まってくるのを感じていらっしゃることと思います。
通教で学ぶにはまず履修登録をすることが必要です。履修の仕方、科目試験やスクーリングの申込など手続きは大丈夫でしょうか? 「通教学生ポータルサイト利用マニュアル2025」や「履修登録の手引き 2025」さらに「スタディハンドブック2025」に必要な手続きが掲載されています。手続きが面倒だと思う人もいるかもしれませんが、マニュアルをしっかり読めば手続きできますので、学修への準備を進めてください。
学修支援推進室では、皆さんの学びへの情熱に応えるべく、今年度も以下に述べるような充実した支援をおこなって参ります。

レポート作成講義を開催
通教生が学修を進めていく際にまずつまずいてしまうのが、レポートの提出です。レポートとは何か、1200字以上も書けるのだろうか、どのように書いたら合格できるのか? そのような不安を少しでも解消するためにも、レポート作成講義をぜひ受講してください。この講義には、入門・A・B・Cの4つのタイプがあります。各タイプの内容については、「レポート作成講義の各タイプの概要」の記事をご覧ください。開催日時や講義タイプ、オンライン・対面の違いは次の通りです。
- 春の開催 昨年度までは、新入生ガイダンスと同日に行っていましたが、講義の時間が十分に取れないなどの状況があり、ガイダンスとは別に、次の日程で行います。特に新入生の方や3年次編入の方は必ず受講するようにしてください。
4月13日(日) 10:30 入門タイプ リアルタイム・オンライン
4月26日(土) 10:30 入門タイプ リアルタイム・オンライン
5月3日(土) 10:30 入門タイプ 対面 創価大学にて
5月3日(土) 13:30 Aタイプ 対面 創価大学にて
5月18日(日) 10:30 入門タイプ リアルタイム・オンライン
5月18日(日) 10:30 Aタイプ リアルタイム・オンラインリアルタイム・オンラインでは、教員に直接に質問することもできます。5月3日(土)は大学でオープンキャンパスが開かれており、それに合わせて対面で2つのタイプのレポート作成講義を午前と午後に行います。
- 科目試験実施日の前日の土曜日午前にA~Cタイプの講義がリアルタイムのオンラインで行われます。日時と講義タイプは次の通りです。
6月7日(土) 10:30 Aタイプ
7月12日(土) 10:30 Bタイプ
9月6日(土) 10:30 Aタイプ
10月18日(土) 10:30 Bタイプ
11月22日(土) 10:30 Cタイプ - 対面で実施する夏期スクーリングの期間中に次の日程で18:30より作成講義を行います。
8月10日(日) 入門タイプ Aタイプ
8月15日(金) 入門タイプ Aタイプ Bタイプ
8月20日(水) Bタイプ Cタイプ
教室や担当教員などについては、夏期スクーリングの各期ガイダンスでお知らせします。
事前の申し込みが必要ですので、学光ポータルの「学修サポート」のメニュー内にある「各種ガイダンス・レポート講義・個別相談・懇談会申込」の「レポート講義」から申し込んでください。
Webレポート作成講義の利用も
4タイプのレポート作成講義はWeb上の映像でも24時間いつでも学習できます。対面やリアルタイムオンラインで行われる講義と時間が合わない場合などで、ご利用をお勧めします。講義内容で分からない箇所があれば理解できるまで何度でも視聴が可能です。学光ポータルの「学修サポート」メニューの中の「WEBレポート作成講義映像」からタイプ別を選んで受講してください。
「学修支援室だより」を学びの力に
毎月、学光ポータルに「学修支援室だより」を掲載していきます。学光ポータルの上方にメニューがありますのでそこをクリックしてください。このメニューの中に、「自立学習入門講座」のコーナーがあります。大学で効率よく学ぶにはどのようにしたらよいのかなど、学びのスキルや意欲を高める記事を掲載していきます。 今年度は4・7・9・1月号に掲載する予定です。
「学修支援室コーナー」の5・9・12月号では、各学部で開いている「オンデマンドスクーリング」についての記事を掲載します。5月は経済学部の「開発と貧困の経済学」、9月は文学部の「西洋哲学史Ⅰ」、12月は法学部の「憲法総論・統治機構論」のオンデマンドスクーリングを取り上げる予定です。オンデマンドスクーリングはどのように行われるのか、どのように取り組んだらよいのか。そのような不安を持っている方はぜひ読んでみましょう。
さらには、担当者による「レポート作成講義」を6月(入門)・11月(Aタイプ)・1月(Bタイプ)の順で掲載する予定です。レポート作成に困っている方はぜひ参考にしてください。
機関誌『学光』の活用を
今年度も3回、春・夏号、秋号、冬号を冊子で発刊します。春・夏号では、鈴木学長と吉川通信教育部長の新入生への挨拶を掲載します。また、夏期スクーリングに備えて注意する点や夏期スクーリングのイベントや学修支援についてお知らせします。
秋号では、夏期スクーリングの開講式での学長挨拶や学光祭の様子をお伝えします。冬号では、来年度のカリキュラム変更点などを詳しくお伝えする予定です。
さらに、各号では、「自立学習入門講座78-81」が掲載される予定で、優れたレポートを書くにはどうしたらよいのかについて学ぶことができます。
「教員による学修相談」の実施
今年度も、オンラインで、通信教育部専任教員による学修相談を行います。上半期は4月から7月に、下半期は、9月から1月に、各教員が月に原則2回行います。毎月の始めに、学光ポータル内の「教員による学修相談」で、翌月の担当教員や相談日時・質問内容をお知らせしますので、それぞれ確認のうえご予約してください。一人30分以内という時間の制限はありますが、教員と直接に話しができる機会をぜひご利用ください。
デジタル副教材『レポート学習のための自立学習入門講座』と『自立学習入門第3版』の活用を
学光ポータルの「デジタル副教材」の中に、これまで機関誌『学光』に掲載されてきた、「自立学習入門講座」のバック・ナンバーが収納されています。レポートを書く過程で、困ったことや分からないことがすぐに解決できるように内容項目ごとに整理されており、大変に学びやすくなりました。レポート作成やテキスト学習のときにぜひご利用してください。
また、昨年度より新設された科目「学術文章作法」の教科書である『自立学習入門第3版』がデジタル副教材にありますので、この科目を自由聴講で履修するときなどに活用してください。
学修支援推進室では、今年度も、皆さんの学修が大きく進展し、卒業を目指して、一人一人が自己の力を伸ばしていけるように、全力で支援に取り組んで参りますのでよろしくお願いします。
学修支援推進室コーナー 3
4タイプの「レポート作成講義」の概要
通信教育部准教授 平井 康章
通信教育部での学びの多くの部分は、レポートを作成することを通して学び深めていくレポート学習になります。そのためレポート学習を攻略できるかどうかが卒業へのカギを握っているといえます。そのレポート学習に取り組んでいただくための学修支援プログラムの一つが「レポート作成講義」となります。
ここではレポート作成講義として用意されている4つのタイプ(入門タイプ・Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ)それぞれについての概要を紹介します。対面およびリアルタイムのオンライン講義に加え、365日24時間いつでも視聴できる「WEBレポート作成講義」も公開しています。
なお「レポート作成講義」の開催予定は各タイプの説明の最後に紹介しています。それぞれの参加申込方法は、学光ポータルの「学修サポート」メニュー内「各種ガイダンス・レポート講義・個別相談・懇談会申込」の「レポート作成講義」から申し込んでください。WEBレポート作成講義は、学光ポータルの「学修サポート」メニュー内に「WEBレポート作成講義映像」を用意しています。
1 入門タイプ
入門タイプは、レポート課題を把握してからレポート提出までの流れ(全作業工程)について概説します。まずこちらを受講してレポート学習の全体像をイメージしていただければと思います。
入門タイプの講義ポイントは①レポート学習の進め方と留意点、②レポート学習の前半と後半の学習課題、③それぞれの作業工程において、「読む・書く・考える」能力を高める基本的なアカデミック・スキルについて解説します。
①では、学術的なレポートと作文・エッセイ・小説との違い、レポート学習の心得、不正レポートと罰則について説明します。
②では、レポート学習の前半(1週間・15時間程度の学習量)の2つの重点課題として、「レポート課題の意味を的確に理解するスキル」「テキストの内容を正確に読み取るためのスキル」を示します。そしてレポート学習の後半(1週間・15時間程度の学習量)の重点課題は「論理的なレポートを執筆するためのスキル」、「下書きを見直してレポートを完成させるスキル」の習得であることを示します。
③では、レポート学習の全工程で「読む・書く・考える」際に必要となる代表的なアカデミック・スキルを紹介します。個々の具体的なアカデミック・スキルについてはA・B・Cタイプでより詳しく扱います。
入門タイプの形式と開催日時
【オンライン】4/13(日)、 4/26(土)、 5/18(日)各回とも10:30~12:00
【対面・創価大学会場】5/3(土)10:30~12:00、 8/10(日)18:30~20:00、 8/15(金)18:30~20:00
2 Aタイプ
Aタイプの講義ポイントは、①レポート課題の意味を的確に把握するためのスキル、②テキストの内容を正確に読み取るためのスキル、この2点についての説明です。
①については、レポート課題のゴールをピンポイントで予測するために、「出題の意図」や「要求されている解答の種類」を読み取るためのコツ、「考察条件」と「考察の種類」を正確に把握するためのコツ、などを解説します。
②については、テキストの全体像をつかむための「トップダウン的な読書術」、内容を正確に読み取るための「パラグラフ単位の精読術」、レポート課題(問い)に対応した解答を探し出すための「探索型の読書術」、思考を深めるための「批判的な読書術」など、4種類の学術的な読書術を説明します。また、こうした読書術と密接に関連する「読書メモ」の取り方や「情報カード」の作り方の技法についても解説します。
Aタイプの形式と開催日時
【オンライン】5/18(日)、 6/7(土)、 9/6(土)各回とも10:30~12:00
【対面・創価大学会場】5/3(土)13:30~15:00、 8/10(日)18:30~20:00、 8/15(金)18:30~20:00
3 Bタイプ
Bタイプの講義ポイントは、レポート全体を明確な論理に基づいて執筆するためのスキルをわかりやすく説明することです。レポート全体のアウトライン(思考の見取り図)を作成するコツ、全体(2,000字)を「序論・本論・結論」の3つのパートに区分して構造的に組み立てるコツ、レポートの基本単位となる「パラグラフ」の要件や、わかりやすいパラグラフを作るための「叙述パターン」の特徴、などに焦点を当てます。ここで紹介するアカデミック・スキルをどこまで習得し使いこなせるようになるかが、レポートの完成度を左右することになります。
Bタイプの形式と開催日時
【オンライン】7/12(土)、 10/18(土)、各回とも10:30~12:00
【対面・創価大学会場】8/15(金)18:30~20:00、 8/20(水)18:30~20:00
4 Cタイプ
Cタイプの講義ポイントは、①下書きしたレポートを見直して磨きをかけ完成品にするまでのスキルを体系的に説明する、②レポートの説得力を高めるための代表的な「論証形式」についての知識を伝える、この2点になります。
①については、論理構成面からの推敲、文章作法に則った推敲、原稿作法とルールに則った推敲の3つの観点から、推敲作業のポイントと具体的なスキルを体系的に説明します。
②については、論理的な観点からみた「妥当な論証形式」とダメ論証の違い。「分類と定義」、「敷衍(ふえん)的な説明や例示」、「因果関係」、「比較・対照」といった頻繁に使用されるパラグラフ・ライティングの技法について具体的に説明します。
Cタイプの形式と開催日時
【オンライン】11/22(土)10:30~12:00
【対面・創価大学会場】8/20(水)18:30~20:00
教職指導講座
教員採用試験に向けて
教職指導講師 栗本 賢一
桜花爛漫の春がやってきました。2025年度も創価大学通信教育部(以下、創大通教)の学びに勇んで挑戦していきましょう。
さて、本年度、教員採用試験(以下、教採)に挑戦する皆さんもたくさんいらっしゃると思います。そこでいくつかアドバイスします。
教採受験に向けて ~絶対にあきらめない!最後までベストを尽くす!!~
教採の実施日が全国的に早まっています。
2025年は静岡県の5月10日(土)を皮切りに、6月末までに都道府県・政令指定都市の過半数で実施されます。その後7月6日(日)に東京都と神奈川・千葉・埼玉で実施となります。
残された時間はもうそんなに多くはありません。教採受験の勉強をあまりしてこなかったという人も、やってはきたけれどまだまだ足りないという方も「絶対にあきらめない!最後までベストを尽くす!!」を合言葉にしたいと思います。
理由は3つあります。
第一に、そう決意した方が学びに真剣に取り組めるからです。
何事もそうですが、中途半端な決意は中途半端な結果しかもたらしません。「合格を目指して頑張る」という強い決意が、学びへの意欲と自身の中にある無限の可能性を引き出してくれます。あきらめない気持ちを持って学ぶ、その真剣さの中で身に付くものがたくさんあります。そしてそれが真に自身のものとなり、将来教壇に立った時に役に立ちます。仮に本年度合格しなかったとしても、来年度合格への布石となり自身の財産として残ります。
第二に、全国的に合格倍率が下がってきているからです。
昨年実施された教採の小学校の最終倍率を見てみると、東京都は1.2倍、千葉県が1.1倍、埼玉県は1.7倍と軒並み2倍以下で、数年前までと比べてかなり低くなっています。教員採用数はそれほど減らないのに受験者数は減っている、これは大きなチャンスです!しかもこれは「最終倍率」であって、一次試験合格率はさらに高くなります。
二次の面接試験(ここは通教生の皆さんにとって強みです)に持ち込むためには、なんとしても一次試験を突破しなければなりません。残された時間は少ないですが、今からでも決して遅くはありません。過去問を中心に、できることに全力を傾注したいものです。
第三に、創大通教での日々の学びで実力が付いていることを確信してほしいからです。
先日、通教卒業生で小学校の本採用教員として勤務しているお二人と語り合う機会がありました。さまざま話を聞く中で、お二人に共通している思いがありました。それは、「通教は大変なこともあったがとても楽しかった。なるほど、そうだよなと、納得できる学びが多かった」ということです。
また、「今、教員として勤務する中で感じるのは“人間性”が大事だということ。“人間性で勝負”ということである。創大通教では、単なる知識や技術の習得だけではなく“人間教育”を学ぶことができた。先生方や仲間との交流を通して“人間性”を磨くことができたと実感している」という点でした。
私は心から感動しました。そのとおりだと思いました。レポート作成への挑戦や科目修了試験の突破、スクーリングで学んだ感動など、これまでの学びのすべてが自身の血肉となって刻まれています。それはいつまでも消えるものではありません。それを持って一次試験に臨む。自ずと結果が付いてくると信じます。
「教採対策講座」や教職キャリアセンターの「教職個別相談」を活用
教採準備を進めていく中で、疑問や質問、あるいはもっと深めたい学びなどたくさん出てくると思います。それらを解決するために「教採対策講座」や「教職個別相談」をフルに活用してください。
「教採対策講座」では、面接や場面指導、小論文などのポイントを学びます。すでに本年1月から開催してきましたが、4月からも開催するので通教事務局からの案内に注視してぜひ申し込んでみてください。
「教職個別相談」をまだ利用したことがないという人は、ぜひ一度利用することをお勧めします。ネットから「教職個別相談 教職キャリアセンター 創価大学」に入っていただくと「教職個別相談」のページとなり、そこに担当講師一覧が出てきます。その中から講師を選び、名前をクリックすると予約カレンダーに移動します。オンライン相談も可能です。ご自身の都合と合わせて予約したい日時をクリックし、「対面orオンライン」で「オンライン」と記入してください。
講師との個別面談では、教採についてのさまざまな質問にお答えしたり面接練習をしたり、あるいは小論文を添削したりなど、一人一人のニーズに応じた対応をします。どの講師もかつて教採の面接官の経験があるので的確なアドバイスをもらえるでしょう。
結びに
この原稿に向かっているつい先ほど、通教事務局から本年度の教採合格者数(卒業生も含む)が100名を超えたと発表されました。101名です(3月30日現在)。通算すると3,967名が合格しました。創大通教48年の偉大な歴史です。
創立者・池田大作先生は「最後の事業は教育」とおっしゃいました。なんとしても教採を勝ち抜いていただき、子どもたちの幸福の実現のために教育の道で共々に頑張ってまいりたいと思います。
なお、教採一次、二次試験について「学光」の以下の号で詳述しています。ぜひ参考にしてください。
「学光」vol.6(2023年度 冬号)
教職指導講座 「教育実習・教員採用試験に向けて」
「学光」vol.7(2024年度 春夏号)
教職指導講座 「『教職の道』実現のために」
「学光」vol.9(2024年度 冬号)
教職指導講座 「2026年度教員採用試験に向けて」
*「学光」は通教ポータルサイトの「デジタル副教材」から読むことができます。
ブック・スクウェア
わかったつもり-読解力がつかない本当の原因-
通信教育部 准教授 清水 強志
今でも、大学2年生の時に、留学生から受けた質問のことを鮮明に覚えています。「夏目漱石のこの文章はおかしい。ここは『が』ではなく、『は』ではないのか?」というのです。確認したところ、特におかしくありませんでした。そこで、問題ないと伝えたところ、留学生からは「なぜ正しいのか?」と…。しかし、私には「日常的な言い回し」としか言いようがありませんでした。この時、実は、日本語の文法の規則を厳密・正確に学んだ上で(ここではこのような理由から「が」を用いる等)、日本語を読んだり、話したり、書いたりしているわけではないということを理解しました。
さて、今回の「ブックスクエア」の執筆にあたり、早速、大きな書店に赴いたところ、1冊の本が目にとまりました。『わかったつもり-読解力がつかない本当の原因-』。黄色い帯には、「続々重版! 驚異のロングセラー ほとんど宣伝してないのに、口コミで20万部突破! 仕事・受験に役立つ1冊」とありました。私自身、日頃から「わかったつもり」は、さまざまな意味で「危険」と考えておりましたので、このタイトルだけでも興味がわきましたが、「後から考えて不十分だというわかり方を、『わかったつもり』」(西林 2005, p.40)と呼ぶ著者は、この「わかったつもり」が本を読む際の「よりわかる」状態への妨げになっていると強調していることに、一層強い関心を抱きました。
ところで、私自身、「学術文章作法」の授業のなかで、本の読み方・考え方などを教えていますが、いまだにうまく説明しきれていないように感じています。とはいえ、私は考えることが非常に好きで、また社会現象やモノゴトを理解することは日常的な行為です。しかし、私自身、「読む/考える」ということについて、言語的な説明を受けたことがありません。むしろ私のこのスキル・態度は、冒頭で述べた「日本語」の例のように、子供の時からの経験やサスペンスドラマなどの視聴に加え、何よりも、学生時代の指導教授による説明(についてのクリティカルシンキングの結果)やゼミにおけるレジュメ発表の際の質問や指摘を受け、「整合性」や「妥当性」を吟味しつつ、実践的に、かつ、(ある意味で)無自覚的に身につけてきたものだからです。
そういう意味でも、著者が「この本は、文章をよりよく読むためにはどうすればよいのかを述べたもの」(西林 2005, p.3)と、簡潔に説明する本書の「よくわかるための読書の仕方」(実際には、これは社会現象やモノゴトの考え方にも適用できると筆者は考えていますが)」の具体的な「指南」は、非常に興味深い内容でした。そこで、今回は2005年に出版された本ですが、ロングセラー(「2025年1月30日 38刷発行」)になっている本書を紹介することにしました。目次は以下の通りです。
―――――――――――
第1章 「読み」が深まらないのはなぜか?
1.短い物語を読む
2.「わからない」と「わかる」と「よりわかる」
3.「わかったつもり」という困った状態
第2章 「読み」における文脈のはたらき
1.文脈がわからないと「わからない」
2.文脈による意味の引き出し
3.文脈の積極的活用
第3章 これが「わかったつもり」だ
1.「全体の雰囲気」という魔物(その1)
2.「全体の雰囲気」という魔物(その2)
3.「わかったつもり」の手強さ
第4章 さまざまな「わかったつもり」
1.「わかったつもり」を作り出す“犯人”たち
2.文脈の魔力
3.ステレオタイプのスキーマ
第5章 「わかったつもり」の壊し方
1.「わかったつもり」からの脱出
2.解釈の自由と制約
3.試験問題を解いてみる
4.まとめ
引用文献など
―――――――――――
実際、著者が指摘するように、「わかる」ためには、すべての文法も単語も明確になっているだけでなく、それに関わる「知識」を知らなければなりません。アカデミックな世界における言語は日常語とは異なることが多く、かつ、専門用語が多用されているので、教科書や参考書を読む際には、辞書や専門辞書を活用しなければならないと強調されるのは、そのためです。しかし、それだけでは不十分で、さらに「文脈」のはたらきが大切だと著者は強調しています。ここでいう文脈とは、「物事・情報などが埋め込まれている背景・状況」(西林 2005, p.50)のことです。
どのような時に「わかったつもり」になりやすいのか、どのようにしてこれを乗り越えるのかという著者の主張は、ぜひ、本書を読んで確認してほしいところですが、次の点だけはあえて触れておきたいと思います。著者は「浅いわかり方から抜け出すことが困難なのは、その状態が『わからない』からではなくて、『わかった』状態だから」(西林 2005, p.40)であり、また、この「『わかったつもり』が、そこから先の探索活動を妨害する」(西林 2005, p.41)からだと述べています。なお、強調しますと、著者は「わかったつもり」の状態には、「物足りない読み」だけでなく、「読み飛ばし」等による「(理解が)間違った読み」も含まれることも指摘しています。
本書は、読書法についての抽象的な解説本ではなく、例文を取り挙げて、実践的に学べる点も、非常に素晴らしいです。第1章では、かつて小学校2年生の国語の教科書(東京書籍「新しい国語」2年下 平成元年度版)に掲載されていた「もしもしお母さん」を取り挙げ、読み終わったあとに2つの質問を投げかけるところから始まります(わからない点はなかったか、この物語をもっとわかりたいと思うか)。
本書への関心は高まりましたでしょうか?^^ ぜひ、「なかなか読みが深まらない」という通教生に、実践的に読んでほしい1冊です。
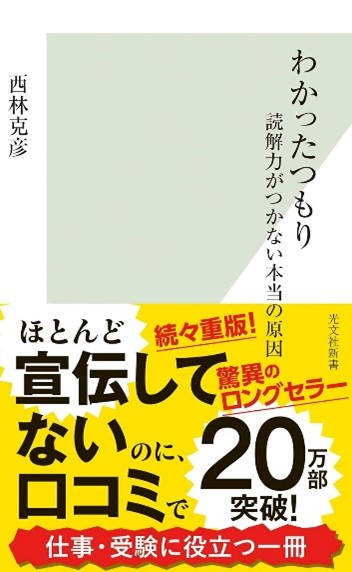
わかったつもりー読解力がつかない本当の原因ー
著 者: 西林克彦
出版社: 光文社 (2005/9/20初版)
ISBN :9784334033224
文 庫: 216頁
価 格: 700円+税


