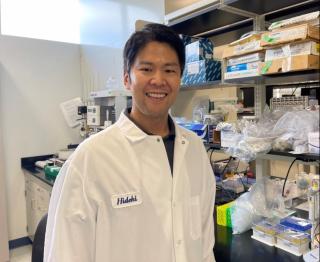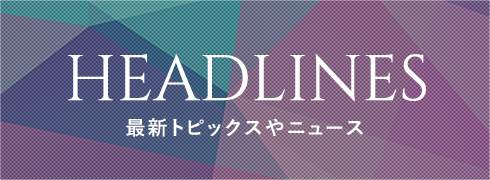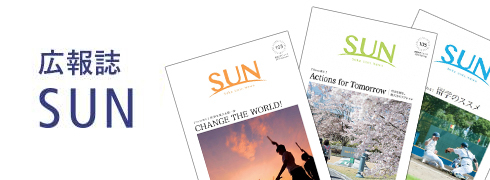SDGsやサステナブル社会をテーマとする2つの学生小論文コンテストで、見事入賞を果たした経済学部4年の渡邊幹大さん。審査員に高く評価された独自の視点や提案は、創価大学で過ごした4年間のさまざまな経験に裏打ちされたものでした。卒業を控えた渡邊さんに、小論文に込められた経験と学び、学生時代の成長などについて話を聞きました。
第8回SDGs学生小論文アワード最優秀次席、NRI学生小論文コンテスト奨励賞の受賞、おめでとうございます。それぞれどのようなコンテストだったのか教えてください。

SDGs学生小論文アワードは、住友理工株式会社が2014年から開催しているコンテストです。今年は「“パーパス”を起点に企業を変えるには~存在意義はなぜ必要なのか」をテーマに論文の募集が行われました。NRI学生小論文コンテストは、野村総合研究所が未来志向のさまざまな題材を取り上げて行っているコンテストで、今回のテーマは「サステナブル未来予想図~次の主役はわたしたち!2050年の社会を描こう~」でした。
小論文の執筆を通して、大学で取り組んできた開発経済学の学びをより深めたいと考え、SDGsや持続可能な社会の構築をキーワードとするコンテストに挑戦しました。
小論文の執筆を通して、大学で取り組んできた開発経済学の学びをより深めたいと考え、SDGsや持続可能な社会の構築をキーワードとするコンテストに挑戦しました。
なぜ小論文コンテストに参加することにしたのですか?
この4年間、コロナ禍の影響で予定していた交換留学の中止やオンライン授業など、思うように学べないと感じることが多くありました。それでも、卒業前に創価大学でしか学べないことを追求し、「やりきった」と言える挑戦をしたい、大学での学びを形に残したいと思ったことがきっかけです。また、ずっと作文やレポートに苦手意識があったので、その苦手を克服して卒業したいという思いもありました。
2つの小論文はどのような内容で執筆されたのか教えてください。

SDGs学生小論文アワードでは、「アート思考」を用いたパーパスの再定義とインターナル・ブランディングによる実践を提案しました。
パーパスとは、企業や組織が何のために存在するのかという根源的な理由、存在意義を意味する言葉です。また、アート思考とは、自分を起点に問いを立て、創造性や感性を刺激する思考法をいいます。論文では、アート思考を取り入れることで独自性を持ったパーパスを再定義できること、さらに、パーパスを行動に繋げる手段として①見える化、②自分ゴト化、③行動化の3ステップによるインターナル・ブランディング(組織の理念や価値にメンバーが共感するよう促す活動)が効果的であることを主張しました。
NRI学生小論文コンテストの論文では、幼稚園から大学までの教育機関を起点としたコンポストで築かれる循環型コミュニティの可能性について論じました。土の中の微生物の力で生ごみなどを堆肥化するコンポストを教育施設に設置することで、コンポストに公共性を持たせ、環境教育の充実を図ることができます。サステナブルな未来を切り拓くためには、コンポスト化をはじめとする日常的なことから行動を始める重要性を強調し、論文をまとめました。
パーパスとは、企業や組織が何のために存在するのかという根源的な理由、存在意義を意味する言葉です。また、アート思考とは、自分を起点に問いを立て、創造性や感性を刺激する思考法をいいます。論文では、アート思考を取り入れることで独自性を持ったパーパスを再定義できること、さらに、パーパスを行動に繋げる手段として①見える化、②自分ゴト化、③行動化の3ステップによるインターナル・ブランディング(組織の理念や価値にメンバーが共感するよう促す活動)が効果的であることを主張しました。
NRI学生小論文コンテストの論文では、幼稚園から大学までの教育機関を起点としたコンポストで築かれる循環型コミュニティの可能性について論じました。土の中の微生物の力で生ごみなどを堆肥化するコンポストを教育施設に設置することで、コンポストに公共性を持たせ、環境教育の充実を図ることができます。サステナブルな未来を切り拓くためには、コンポスト化をはじめとする日常的なことから行動を始める重要性を強調し、論文をまとめました。
どちらのコンテストでも、ご自身の経験をもとに論を展開されたそうですが、小論文に生かされた創価大学での経験とは、どんなものですか?
SDGs学生小論文アワードの論文でポイントにしたアート思考やブランディングの手法は、滝山国際寮、創大祭実行委員会、キャリアサポートスタッフ(CSS)など、学内組織の運営で私が実践していたものです。アート思考の実践では、たとえば寮の年間テーマを決める際には、寮生が自分軸で寮や創価大学を見つめ、課題を検討し、一人一人から出されたキーワードを組み合わせて年間テーマに落とし込む、というプロセスを踏むことで、寮の活動に対するメンバーのモチベーションを高めていました。当時は「アート思考」という言葉も知らなかったのですが、就職活動中にその言葉を知って自分がすでにやってきたことだと気付き、経験を小論文に生かすことができました。また、コンポストも個人的に取り組んでいたことの一つで、環境保全のために自分にできることはないかと考え、国際寮の生ごみを使って作っていました。

寮役員のメンバーと
優れた論文には内容の独自性が重要ですが、今回は自分の経験をベースに書いたことでおのずと独自性が高まり、提案に説得力も生まれました。審査員の方にもその点を評価していただいていたので、とてもうれしかったですね。また、こうした実践ができたのは、「学生主体」の伝統があり、学生自身が考え、行動できる場が豊富な創価大学だったからこそだと思います。
小論文の執筆を通して、苦手分野だった書くことに果敢に挑戦し、文章力はもちろんチャレンジ精神も養われました。また、執筆中は自分の力で課題を設定し、独自の角度から問題に切り込もうと心掛けました。誰かに答えを求めるのではなく、自分で考え抜き、新しいアイデアや価値を創造する力を高めることができ、自分の成長を感じています。
小論文の執筆を通して、苦手分野だった書くことに果敢に挑戦し、文章力はもちろんチャレンジ精神も養われました。また、執筆中は自分の力で課題を設定し、独自の角度から問題に切り込もうと心掛けました。誰かに答えを求めるのではなく、自分で考え抜き、新しいアイデアや価値を創造する力を高めることができ、自分の成長を感じています。
経済学部ではどのような学びをしてきたのでしょうか。

西浦ゼミのメンバーと
開発経済学を専門に学んでいます。授業やゼミで学びを進める中で、開発は経済的側面だけで考えるのではなく、自然や環境にも配慮して進める必要があるという思いを強くしました。より多角的に開発経済学を理解するため、文学部、法学部、理工学部の授業も積極的に履修し、視野を広げることができたと感じています。
開発経済学を通して、途上国の貧困など弱い立場の人が抱える問題を、どのようなアプローチで解決できるかを考えてきました。その経験と学んだ知識を土台に、社会でも弱い立場の人の意見をしっかり集約しながら、課題をどう解決していくかを考えることに力を発揮していきたいと思っています。
開発経済学を通して、途上国の貧困など弱い立場の人が抱える問題を、どのようなアプローチで解決できるかを考えてきました。その経験と学んだ知識を土台に、社会でも弱い立場の人の意見をしっかり集約しながら、課題をどう解決していくかを考えることに力を発揮していきたいと思っています。
学びたいことに積極的にチャレンジする4年間だったんですね。
そうですね。ただ、最初からそうだったわけではないんです。高校時代は野球部で、本当に部活一色の生活を送っていました。大学では、高校ではできなかったことをしようと思ってはいたのですが、入学当時の私は長い文章や英語は「見るのもイヤ」という状態でしたね(笑)。そんな自分が、さまざまな学内活動や授業を通して力を付け、小論文コンテストという学外の場でも評価していただけるようになったのは、周りの先輩方や仲間、教職員のみなさんのおかげだと思っています。入学したばかりの頃、目標に向かって挑戦する先輩方の姿は輝いて見え、大きな刺激を受けました。その姿に近付こうとする私をサポートしてくれたのは、寮でともに生活していた先輩方です。勉強の仕方を一から教えてくれただけでなく、一緒に勉強し、学びを丁寧にフォローしていただきました。また、良い意味でライバル心を持てる同期の存在も大きく、勉強していても「あいつが寝るまでは」と意識したり、切磋琢磨する中で今の自分に成長できたような気がします。
創価大学を目指す後輩たちにメッセージをお願いします
創価大学には、成長したいという思いさえ持っていれば、挑戦できる環境がいくらでもあります。もちろん、挑戦にはいろいろな壁がつきものです。私もこの4年間、自分の実力不足で壁に跳ね返されたり、コロナ禍のような自分ではどうにもできない壁に道を阻まれたりする経験をしました。ただ、そこでうまくいかない悔しさやもどかしさを、次の挑戦の原動力に変え、頑張り続けたことが自分の成長につながったと思っています。みなさんも、もし壁にぶつかっても、悔しさから逃げずに努力してみてください。きっと卒業する時には、私のように入学時には想像もしていなかった自分になれるはずです。ぜひ創価大学で自分の可能性を無限に広げてほしいと思います。
PROFILE

渡邊 幹大 Kanta Watanabe
[好きな言葉]
さあ出発しよう! 悪戦苦闘を突き抜けて、決められた決勝点は取り消すことができないのだ。
[性格]明るい、楽観的、負けず嫌い
[趣味]
スポーツ、映画鑑賞
[最近読んだ本]
シャドウ・ワーク:生活のあり方を問う/イヴァン・イリッチ
ページ公開日:2023年02月15日